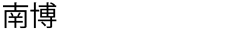何の理由もありませんが、私の父親のことを書きたくなりました。私の父親は生粋の京都人でした。
大学時代に東京に出てきたので、普段は標準語でしたが、心根までは変わりようがありません。生れ育ちは四条河原町、先斗町あたりで、実家はかなり大きな旅館を経営していたと聞いています。余談ですが、その旅館は戦後のドサクサでなくなってしまったのですが、戦前の京都で生まれ育つという情緒には、いったいどれだけの文化と美意識が含まれていたのか。それを想うだけで私など目眩がしてしまいます。実際私の父は歌舞伎評論の道に入りたかったほどの芝居好きで、芸事の良し悪しがよく分かる、一本スジが通った、真面目で極端な面はありましたが、緩い所は緩いという、なんともユニークな父親でした。 子供の頃、よく歌舞伎座に連れて行かれ、分からないながらも名優の演技を目の当たりにした私は、ある意味相当変わった子供だったのかもしれません。
私の父親の性格、または言動が、私の演奏に直接的、また、ときには間接的に関わっているのは確かです。更に、自分自身の成長という意味に於いて、いまだそのことを助け、同時に足を引っ張っているという、いい歳をして私はいまだ、父親の影響下にあると言っても間違いではないでしょう。
私の父親の口癖は、「人間二人だけでも情の世界」であり、「焦ったらあかん」であり、「ねばってねばってねばってねばってねばって続ければ必ず成功する」、この三つでした。最後の格言?は、やっとのこと、私なりに腑に落ちるところと腑に落ちないところを、この歳になって今更ではありますが、使い分けられるようになりました。簡単に言えば、粘ることは必要だが、成功とはいったい何かがいまだ私の中ではっきりと言い切れない部分があるからです。
ひるがえって前出の二つの口癖は、これまたいい歳をして、いまだ抜け切れていない部分があり、特に一例を挙げれば、「情の世界」に関して、アメリカに留学していた時分、大変な思いをしたものです。特段アメリカ人が薄情だと決めつけているわけではありませんが、彼の国の乾いた人間関係に、住み始めた最初の年に、ずいぶん圧状しました。当然ながら、歌舞伎的「情」の世界がアメリカ人に通じるわけもなく、女形が女装とは決定的に違うのとおなじで、随分と損な立場に置かれ、それに伴い私自身が徐々にアメリカ人的になっていかざるをえなかったのは、観光で訪れた訳ではないという、どうしようもない事情もありました。
話しはそれますが、アメリカ人にとって、何かしら人間関係に齟齬が生じ、お互いの行いの良し悪しが平行線を辿るとき、アメリカ人は「わすれれよう」と言って、本当にその事はその事後おくびにも出さないという面があります。
話しを父親のことに戻します。私の演奏する音楽は、一人でやるよりも、例えばサックス、ベースなどと一緒にやることが多く、しかもそこには一筋縄では括ることのできない一匹狼的輩が集まってきます。そんな集団の中でリーダーという役割を努めなくてはならなくなったとき、一言で言えば、優先すべきは音楽か「情」なのか、を明らさまに迫られる局面もあり、畢竟私はマイルス・デイビスでは勿論ないので、悩まざるをえなくなるわけです。様々な心的要素が絡み合う中、音楽そのものを優先するのか、はたまた父親の言うところの「情の世界」を優先するべきか、リーダーとしては最もあってはならない状態、つまり優柔不断に陥ることがあります。
私を悩ませるのは、バンドメンバーが下手くそだとか、気が合わないといった簡単な理由ではありません。先ほども使った言葉ですが、齟齬としか言いようのない状態、状況時に、私はどうしても「情の世界」に入り込むことが多い。しかし、何かしらの「齟齬」が生じた時、状況に応じて情そのものを忘れる方が物事をうまく運ぶことができることも多々あります。しかし私はそれがとても苦手なのです。なにもベタベタした人間関係を求めているのではありません。クールで在ること自体好きですし、ミュージシャンとしても格好がいい。しかしそういう時でさえ、齟齬を無視してまでも情を選んでしまう私は、極端であった父親の性格をそのまま受け継いでおり、更に「焦ったらあかん」というわりには、たまに焦っていた父親を目の当たりにしてもいますので、私も焦らなくていい時に焦る癖があり、これは逆説的ではありますが、父親の口癖の影響を、表からも裏からも受けてしまったといえるでしょう。
最後に、私の仕事にずっと反対していた父親が、後にも先にも一回だけ、新宿PIT INN に私の演奏を聴きに姿を見せたことがあります。もうずいぶん前の話ですが、何か特別の企画で、若手のミュージシャンが集い、ベースが斯界の重鎮というもので、詳細は私も忘れましたが、その企画をしたプロデゥーサーだったか、その時ちょうど来日していたブラウンフォード・マルサリスをスペシャルゲストとして、後半の演奏に参加するという話は、演奏前から来ていました。アメリカの超一流と演奏している姿を父親に見せることができれば、きっと私の仕事も認めてもらえるだろうという想いで、私は父親に無理を言って、その時PIT INNまで呼びつけました。
演奏が始まり、ちらりと客席を見ると、真ん前、しかもど真ん中の席に腕組みをして、私の顔をにらみつけている父親の姿がちらりと視界に入りました。演奏しにくいことこの上ないことはいうまでもありません。しかも、あのPITT INNの小さなテーブルには、既にビールの小瓶が乱立していました。
企画通りに、後半ブランフォードが姿を現し、客席は拍手喝采。しかし父親は腕を組んだまままんじりともせず私をにらみつけていました。
演奏後、楽屋で汗をぬぐってから、父親に一言挨拶をしようと客席の方に戻ると、相変わらず腕組みをしてステージをにらみつけている父親の姿がありました。
「オヤジ、演奏そうだった」
「ヒロシ!他の奴はどうでもええけどなあ、あのクロン×は上手い。ヒロシ!あいつとやれ。あいつと一緒に演奏せい」
「オヤジ、ここはジャズクラブで、しかも都内で一番有名な店なんだよ。そこで大きな声でクロン×っていうのはやめてくれ〜〜」
「クロン×はクロン×やないか。お前はあいつとやらなあかん。あいつには芸がある。ええ音や。ワシは歌舞伎しか分からんが、あのクロン×はすごい」
「他の奴はどうでもいいっていうのも大きな声で言うのやめてくれ〜〜」
「何が悪いねん、ワシは客やど。お前はあのクロン×のグループに入ったらええねん」
「そんなに簡単にいかない事情がいろいろあるんだよ」
「がたがたいうな、だーかーらーお前はあのクロン×と演奏したらええねん。分かったな」
そう言い捨てるやいなや、父親はすっくと立ち上がり、あっという間に出入り口の方に歩み寄りました。そしてなんと、入り口付近に立っていたトブランフォードに向かって、日本語で、「ワシの息子をよろしくお願いします」と頭を下げ、そのまますたすたと帰って行きました。