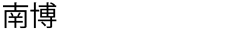某月某日
過日、忙しい間を縫って、しとしとと降る雨の中、ジャクソン・ポロック展に行った。午後の用事がなかなか終わらず、一度カウチにへたり込んだが、その日の夜しか空いていなかったので、無理に起き上がって竹橋の駅に向かう。焦ると碌なことはない。地下鉄の出口を間違えてしまい、近代美術館とはずいぶん離れた出口から外に出てしまった。皇居をグルリと十分の一回転し、やっと美術館の前に着いたときには十九時半を過ぎていた。入り口の係員に泣きついて何とか中に入れてもらい、さあやっと観賞というスタート地点にたどり着く。俗世を忘れるため、自分の自我を真空状態にするべく、立ったまま数秒自身を仮死状態とする。しかし、心頭滅却すれば放射能もまたラドン温泉とはならず、日々の雑事が頭をよぎる。しかし、うかうかしていたら、閉館は二十時である。やむを得ず、俗世間の見えない糸を断ち切れぬまま、作品と対峙した。う〜ん、何じゃこりゃ。よく観れば均整の果てに統合性がきちっと波打ってはいるが、画家はここまでの表現方法を選ばねばならぬのかと、先ずそこに注目した。ジャクソン・ポロックに限らず、画家は孤独だろう。音楽は、例えばソロピアノなどの演奏形態はあるが、やはりアンサンブルが主であり、対人間と音楽を、ある意味興行という名目の瞬間に創造することができる。しかし画家はひとりで絵を描く。しかも製作過程自体は興行ではない。類似点はある。音楽家が一人練習することは、絵画の世界と比べれば、作品を世に問うための営みとはかけ離れていることも、往々にしてある。雑音に近い指の練習など、製作とは言えない。そう考えてみると、展覧会というものは、既に画家自身が果たした興行の後を壁に架けているのであり、そこからのインパクトは、製作過程よりも若干おとなしくなってしまうのは仕方ないことなのだろう。特にボッティチェリのような画家と比べれば、ジャクソン・ポロックのような画風は、製作過程で興行していると、僕としては感じざるを得ない。
画家がうらやましい部分もある。絵筆、絵の具、タブローという制限はあれども、ピアノという合理性の塊のような楽器と比べれば、その表現は、もっと形而上的無限大に近づくことができる気がする。いずれにせよ、ジャクソン・ポロックの描いたものは、製作過程が一番面白く、完成した時点でその彼の絵自体は、興行が終わった後の寂しさが漂っているように感じた。すなわち何か食い足りない寂寥感のようなものを醸し出していたのだ。外が雨だったせいもあろうかと思うが、要するに、僕には彼の絵が解らなかった。アメリカのハイウエイを想起させるその線の多い画風は、僕には何かしらの地図に見えてしょうがなかった。要するに僕の審美眼が欠落しているのであろう。地図上のハイウエイのような線と、自動車事故で若くして死んだ彼の人生の終わり方に、何か共通するものを感じたのは僕だけだろうか。
雨がしとしと降る中、疲れきって家に帰った。