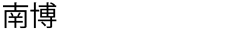某月某日
電脳空間がいっぱいのため、日記が更新できません。しばしお待ちを。
某月某日
とある仕事で、BILL EVANSの名演で知られる「MY FOOLISH HEART」を録音する事となった。この曲の入っているCD,「WALTZ FOR DEBBY」は、1961年のとある一日、神様がシニカルでいるのを一瞬やめにして、薄いかすかな微笑みをマンハッタン島に向けた瞬間に演奏されたのではないかと思われるような、はかなく、そして後世に残る名演の一つである。このCDの一曲目の「MY FOOLISH HEART」、読んで字の如く、ジャズを演奏するという事自体、実はバカみたいな事なのである。才能があればあるほど、また才能がなければないほど、どちらにしてもたどる道は同じだからだ。答えの無い日常をもがくのは、ミュージシャンでなくても、人間ならばそこそこ経験している事だが、ミュージシャンはそのもがきのエントロピーが拡散的だ。エントロピーが拡散すれば、これはバカにならざるを得ない。同じ淫するなら、才能があった方がいいに決まっているが、才能があったらあったで、それなりに、常人には伝わらぬ屈託があるはずであり、なかったらなかったで、これまたそれなりの屈託があるに決まっている。この曲のすごいところは、才能如何に関わらず、聞く者をもってして、「愚かなりし我が心」と、万人をして感じさせうるメロディーラインを持っているところであろう。淫するがためにおこる屈託、もがきたくなくても、もがかざるを得ない日常。世の中から、自分も大人として見られなければならないという暗黙の枷もこの屈託に加わるだろう。もしこの世がこれだけの要素で構成されているならば、またこれまでも構成されていたならば、我々人間はあまりにもみじめっぽくしょぼくれた生き物であろうしあったろう。しかし我々には音楽があるのである。音楽をになう要素の一部として忘れてはならないもの、それは激しいネオテニー的な衝動だと思う。世の屈託、大人としての枷を取っ払ったもろい部分を前面に押し出しても安心できる空間。それは良い音楽を聴いている時なのではないだろうか。
某月某日
世の中では人々が目まぐるしく働いていて、僕の仲間達も目まぐるしく音楽の分野で活躍をしている。そんなこのことは今日に限ったことではないけれども、僕は活躍などまったくせずに、今日一日、あまり外にも出ず、掃除をし洗濯をしていた。のろのろと家事をするということは、気分転換以外の余計なことを考える時間を作るということでもある。余計な考えは大抵ネガティウ゛で、なんだか生まれてからこのかた、何の意味の無いことをずっとしでかして来たような気分となって、暗胆たる気持ちにいつも陥る。自己を肯定する何らかのよりどころというのも、所詮は妙な思いこみから始まっていることの方が多く、確固として前に進むだけの力強さに欠けているように思えてならない。かといって、混迷をきれいに取り去った社会というものが存在するかといえば、そこは人間のすみかでは無いであろう。北朝鮮にも混迷があるぐらいなのだから。暇にかまけて、「イブラヒムおじさんとコーランの花たち」という映画を見にいったが、まったく、がくっとくるように無意味な映画で、何の感動も感慨もわかない僕は、どこか精神的に異常なのだろうかと思ったほどだ。たぶん僕の感性がにぶっているのが悪いんだろう。少なくともフランス映画であるから、お涙ちょうだいもリキュールの味程度の抑制があるが、なんでこんな映画作る気になったのか、全然分からない内容だった。ハリウッド映画のドンパチもいやだが、こういう映画もいやだ。畢竟、気分転換に映画を見るという楽しさも奪われた気分である。僕の生活する環境のまわりで、特出して冴え渡っている何かを見つけること自体が、贅沢な欲望なのかもしれない。後はきのきいた居酒屋がどこにあるかというような情報を、近所に住む友人と交換するぐらいのことしかないのかもしれない。それはそれで良いことなのかもしれないが、酔えば酔ったで、後は全ていっしょこたである。地球の自転と時間の流れは、そんな僕の生活の中でも容赦なく、先へ先へと進んでい行き、これに逆らうことはできないし、たとえ生活自体が昼夜逆転だからといっても、過ぎ去るものは過ぎ去り、僕の意志とは関係なく明日はくる。すべてがお手上げだ。なす術もなし。きれいにした部屋等もいずれまたよごれる。意味を見いだすまでもなく営み自体は続くのである。ヨーロッパに行きたい。たぶんあそこは日本よりホコリの量が少ない。
某月某日
またしてもずっと日記を書かなかった。多忙だったという理由があるが、詳しくは、その多忙中に行動をともにしていたベーシスト、水谷浩章氏の日記に、その動向が詳しく書いてあるのでそちらを参照されたい。(リンクの欄に彼のWEB ADDRESSがあります。)こちらが音楽三昧で浮かれているうちに、地球上ではいろいろなことがおこっているようでして。なんとなく毎日いやな気分で過ごしているありさま。国内も国外の情勢もろくなもんじゃない。「人の世は 地獄のうえの花見かな」という僕の好きな川柳があるが、最近は花見さえも許してもいらえないということなのかもしれない。地獄の上に地獄があったら、死んでも意味がないじゃないか。この世が即地獄ならば、生きているかいがいしさも空回りだ。世界一強い国が、なんで戦車と機関銃で戦争するのだろうか。やはり人間はドンパチが好きなんだろうなあ。僕も含めて。人間であることがいやになる。同じ地球上で。双方皆親があり、兄弟があり、友人があり、そのことには変わりなかろう。こんな中学生の作文みたいな文章書いたって、大局は何もかわらないのは百も承知。だいたい、人前で演奏すること自体が、少なくとも上品な行いとはいえまい。そのことも承知のうえだ。だいたい、こんな日記書いて、不特定多数の人に読む場を提供していること自体上品とは言えない。このことも承知のうえだ。でもひどすぎるなあ。人間の所業。下手をしたら、人間は二本の足で糞とゲロを支えている動物以下の動物だと前の日記に書いた。それでもう下品さにおいては十分なはずなのに、それ以上の下品な行いを、キリスト生誕以前から営々と続けている我々はいったいどういう種族なのだ。いかんせん国益という立場に立てば、脱げないパンツもずり下ろすしかないのであろうが、もっとお互い、考えるべき人間の問題がたくさんあるんじゃないのか。もっと人類として、考えるべきことが山積しているはずだろう。勘違いしないでほしいんだけど、僕はただ単に戦争反対を叫ぶ者ではない。いざとなれば、撃たれたら撃ちかえす事もあるだろう人間の一人として、その自分自身を悲しみながら憤っているんだな。戦争の核心は擬制資本ではないのか。それともたがのはずれた本能の狂乱なのか。どちらにしても、僕が想像していた以上に、この世紀は暗黒だな。
某月某日
11月1日、午後8時より横浜にあるクラブ、「DOLPHY」にてGO THERE !の面々と演奏する。クラブ「DOLPHY」は、JR桜木町駅と、京急日ノ出町駅のあいだに位置する。正確に住所を記せば、宮川町というところにあるクラブである。この近辺、ぼくは横浜の住人でないので、あまりえらそうなことは言えないが、このままずっと、誰の手も入ることなく、ひっそりと、そしてそっととっておきたいなあと思わせる場所である。まずこのあたりは時がいまだ昭和の雰囲気であり、港町につきものの猥雑さがひしめきあっている。JR線をはさんで反対側の未来都市との差は、計測する思想も基準も持ち合わせないくらいの違いだ。いずれにせよ、ぼくにとって居心地のいい方は、なぜか日ノ出町駅、宮川町近辺であり、桜木町から宮川町へ歩くルートに立ち並ぶ、港町には必須のアイテムを道の両側に見ながらクラブに向かうこと自体が楽しい。必須のアイテムとは、ここにあえて記すこともないだろうが、全ての、と言っていいだろう、昭和ロマン歌謡曲の中の歌詞に出てくる名称が、ここにはあるのだ。バー、スナック、ソープランドにはほとほと見えない「トルコ」な風俗店の数々。スターバックスからはほど遠い喫茶店など。(ちなみにぼくはスターバックスが苦手である。なぜかって?タバコが吸えないからに決まってる)、ラブホテル、エプロンを着たおばさんがやっている一杯飲み屋、書きだしたらきりがない。また、かの伝説のジャズ喫茶「ちぐさ」や、「DOWN BEAT」などが、まだ顕然と存在しているのも、横浜という港町の特徴だ。そういった、一般にはネガティブに使われる言葉、しかしここではぼくにとっての褒め言葉である「猥雑」な一角に、クラブ「POLPHY」は、何気なくたたずんでいる。東京のジャズ喫茶という空間が全滅したのにもかかわらず。これも横浜という港町の持つ特徴なのだろうか。もともとジャズってこういう感じのあたりで演奏されていたんじゃないだろうか。ジャズの歴史の本を読んだ知識などで、SPEAK EASYと呼ばれた禁酒法時代のもぐりの酒場、そういったあたりで、黒人のミュージシャンがジャズを演奏していたということは知っている。しかし、それはあくまでも文字から入ってきた知識にすぎない。しかし、桜木町駅から川沿いにDOLPHYまでの道をたどれば、そんな本の知識なんか屁でもないような景観が広がっていて、ひじょうに小気味良い。どの都市にもガス抜きは必要であり、それは東京にも言える事ではないだろうか。町のつくりは全然違うのに、その道すがらを歩いていると、よく新橋に住んでいたおばあちゃんの家に遊びにいっていた頃の事を思い出す。そのあたりを歩いてまわった子供の頃のことだ。印刷工場のガチャンガチャンという音とともに、当時の新橋近辺の記憶が宮川町あたりとなぜか重なる。その記憶の中にあるものは、やはり、バーやスナック、喫茶店、町工場、袋小路にまたたく春雨の流れのようなネオンの明かり。みな昭和40年代の東京の風景だ。新橋に川は流れていなかった。しかし、当時と同じにおいが宮川町近辺にはある。当然、そして必然的に、そこで演奏される音楽は、東京の山の手にあるクラブで演奏するものと比べて、全然別もののバイブレーションを帯びてくるに違いない。また、そうでないとしたら、我々の演奏するものは、ジャズではなくなる。
某月某日
大切な仕事の合間を縫って10月だというのに台風ばかりが空にたれこめ脳内は泥濘のようになり頭の上には漬物石をのせたような背の縮まるような日々が続きいやな気圧の関係で思い付くこと考えること全て大切な仕事向きの内容でなくニコチンの量が倍アルコールの量も倍となり夜はさらに眠れずこのじとじとした大気を部屋に入れまいと閉じこもれば閉じこもるほどに悪循環さらに倍加し薄い呼吸をしているのがやっとで食欲もなく10月の爽快な秋を夢想する気力も失せたあの東京でも一番透明感のある秋の雰囲気を一日でも削がれるということは東京に住んでいるという事実自体の意味を遠ざけるまた、高飛びするだけの金も暇もなし時々どこかでとんかちを二回、三回たたくような音が聞こえるがこれは頭の上の漬物石のせいなのか頭の血管に欠陥があるのか幻聴か秋よ来い[MUSE;オフェーリアの化身」 ドラマー、オラシオの笑顔の中には、ミューズが宿っていた。このリズムの天才の、しかも繊細な彼の笑顔の中に。MUSEはギリシャ神話に出てくる神様の一人である。MUSICの語源であろう。ぼくなどは、たまにしかそのミューズに遭遇しないのだけれど、オラシオの笑顔の、その中の瞳の奥の、そのまた奥の魂全体に、ミューズが住みついていることが見て取れた。10月18日、スイートベイジルに於けるトリオ演奏の最初の音を聴いた時にである。陰茎に血液が集中するように、ぼくの魂の中のどこかしらに隠れていた、自分さえ気付かなかったミューズに、オラシオはその第一音で、そのミューズの頬がバラ色になるような息吹を吹き込んだ。”!!!!”こいつは化け物だ。そう、怪物。怪獣、人間じゃ無い。俺自身が気付かなかった俺の魂の中のミューズを叩き起こしやがった。しかも笑顔で。そのミューズは、有名なオフェ-リアの絵から抜け出してきたような妖精に見えた。例の、ジョン・エベレット・ミレイ作の有名な絵の中のオフェーリアだ。ハムレットの筋書き通り、狂っていて、小川に浮いているにもかかわらず、バラ色の頬をしている。絵の中のオフェ-リアは無表情で蒼白だが、ぼくの中のオフェーリアは、小川からすくと立ち上がり、唄をうたっている。そして、ぼくの魂の中にあるミューズ、すなわちそのオフェ-リアは、こちらがよだれをたらしそうになるような、ある意味ものすごく陰媚な、そして同時にものすごく清楚な微笑みを浮かべている。演奏が進むにつれて、彼女は、ぼくの魂の中で、信じられないようなセクシーな表情で、唇をつぼめたり、少しだらしなく開いたりしている。深紅の唇。演奏が盛り上がるにつれ、彼女は何かぼくに囁きかけてくる。かの夏目漱石が初めてこの絵を見た時の感想とはまた違った、何語かわからない、しかし、非常に切れ味の良い、そして響きの良いアクセントで何かぼくに語りかけてくる。もしそれが本物のオフェ-リアならば、シェークスピア時代の古い英語の筈だが、そのサウンドは英語ですらない。いずれにせよ、その言葉の韻の中に吸い込まれそうになる。身体が半分彼女の方に持っていかれそうになる。だが、ギリギリのところで、完全に吸い込まれはしない。何故かって答えは簡単だ。このオフェ-リアはオラシオがあやつっているのだ。何ということだ。あのごっつい顔のキューバ人が、俺の魂の中を良い意味で掻き乱している。あいつはブ-デゥ教の呪い師か何かなのか?オフェ-リアがぼくをセデュ-スしている。音楽が、オラシオのサウンドが、カルロスの野太いベースの音が、ミューズが、オフェ-リアが、同時にぼくの聴覚、ピアノのタッチ、アイデア、ソウル、魂、何でも良い、全部一時に襲ってくるのだ。それは死と直面するスリルにも似ている気がした。だから気持ちが良いんだ。よ-し死んでやる。オラシオよ、お前は天才だよ。だけど俺にだって矜持ってもんがあるんだよ。俺の魂の中に眠っていたミューズ、すなわちオフェ-リアを叩き起こし、俺の音楽的なある部分を開眼させたことは確かだ。だからって、そっちの誘惑だけで音楽を進行させるわけにはいかない。だってこれは俺のコンサートなんだ!あ、くそ、またオフェ-リアがぼくをモノスゴク誘惑してきた。オラシオよ、少し待ってくれ、俺にも準備ってもんが必用、、、、あ、今すげえ事が起きた。演奏中にだ。これは俺とお前がいっしょにやったもんだからな。お前のブーデゥ-教か何かシランが怪しい呪いの力だけじゃ無いんだぞ。しかし、うっ、またすげえ音楽的に言って大きな波が来た。喜んで溺れ死んで見せましょうぜ、オラシオさんよう。俺だって伊達にピアノを今まで弾いてきたわけじゃないんだ。俺が銀座のナイトクラブで悲しい気持ちで演奏していた時、おまえはゴンザロ・ルカルカバなんかと世界ツアーしてたんだろ。人それぞれだ。だけど今は、死なばもろとも。俺もお前の中のミューズと同じくらいピアノを弾くことが好きなんだよ。ほら、わかんだろ、そうそう、その通り、ドウドウドウ、少しゆるやかに行かない?何て言おうとしたらまた大きな津波が。オフェ-リアも、カルロスも、オアラシオのミューズも、ぼくの中のミューズも、そのサウンドの津波の中にどっぷりと沈み込んだ。ものすごい官能が全身をしびれさせる。オラシオよ、一瞬だったが合体したな。俺達。カルロスもさ。これが2曲目のトリオ演奏での感想だ。3曲目からはSTRINGSを交えての演奏だった。三曲目からの感想はって?「TOUCHES&VELVETS」を買って聴けばわかりますよ。『病的に病的な自分: 新譜「TOUCHES&VELVETS :QUIET DREAM」発売に寄せて。』10月21日に発売されるぼくの新しいCD、「TOUCHES&VELVETS :QUIET DREAM」の宣伝を、早くもプロデューサーである菊地成孔氏のSITEでやってもらっています。このSITEより有名だから無駄かとも思いますが、一応彼のSITEのアドレスをここに記すことにします。(http://park10.wakwak.com/~kikuchic/)そして以下のアドレスは、10月18日に演奏する JAZZ TODAY 2004の情報です。(http://www.ewe.co.jp/jazztoday2004/)勿論、TRIO PLUS STRINGSという構成です。この期におよんでは、ぼくも何か次回の新譜に関して書かざるを得なくなった気がします。以下の文章は、プロデューサーである菊地成孔氏、そしてEWEの全ての関係者への感謝の念と共に書いた、前口上です。新しい音楽を表現し、それを世に向けて発表することは、大変嬉しいことです。しかし同時に、今回は少し複雑な心境でもあります。今回のこのCDの製作、コンセプト、宣伝などに関して、我が友人でもあるプロデューサー、菊地成孔氏に全てを一任するつもりでいたからです。もちろんこういう文章を書くことも含めてです。実際に、演奏前から新しい音楽を創るにあたっての会合、最初のトリオ録音の進行の時も含めて,ぼくは菊地氏の言うことに一言も反論しませんでした。彼に全信頼をゆだねると決めて製作にはいったからです。ですから、ある意味で、この「TOUCHES&VELVETS」は菊地氏の夢が現実のものになったと言っても過言ではないでしょう。このような理由で、今この時点から、このCDのことを文章として、初めて自分の意志を通して語ることは、ひじょうに難しいのです。もちろんトリオ録音中においては、自分の「意思」無しでは音楽は創作できません。しかし、その意思さえも、菊地氏の鋭敏なる頭脳とセンスにあやつられていた感があります。ただでさえ、自分で自分の音楽のことを文章に書くことは、下手をすると、手前味噌になる嫌いがあり、逆に、あまりに日本的謙譲の美徳を振りまわすと、なぜ創ったんだと言うことにもなってしまう。うまく書けてもそれは短編の私小説的なものになるしかなく、うまく書けなければ、それはただの駄文と化してしまう。畢竟、この文章を書くにあたってただひとつ残る道、それはぼくがバカ正直になり、自分が普段考えていること、思っていることを文章でさらけ出すしかないと考えました。ですから、この先に記する内容は、ある人にとってはひじょうに不愉快なものになるかも知れません。何故このCDを気合いをこめて創り込んだか。答えは簡単明瞭です。我々の住んでいる環境、我々が日々目にするもの、耳で聞く音の実に八割以上はそれこさ汚く不愉快なものです。少なくとも僕にはそう感じられます。一歩ドアを開けておもてに出る。道のまん中に妙に間延びしたカタカナで「止マレ」などと書いてある。実に不愉快です。変な白線が路上、車と人間の合間を定めているようですが、何の為に白線が必用なのかわからない箇所が街には沢山あります。空を見上げると、電柱とその間にこんがらかったケーブルが、風景の中に、蜘蛛の巣みたいに張り付いている。駅へ行く。「おさがり下さい」「携帯電話の電源をきりなさい」「足下に御注意下さい」日本は母系社会だからこういう親切がまかり通っているのかも知れませんが、僕にとってはただの雑音です。見たくないものに対して、目は閉じられますが、耳は閉じられません。蛍光灯の使用量も、各場所であまりにも多すぎます。蛍光灯、これは既に害悪であり公害です。人間を明き盲にし、脳に色彩というセンスを伝えないようにしてしまいます。渋谷、新宿などはもう、本当は恐ろしくて近寄りたくもないのですが、CDを買ったり本を買ったり、仕事をする場所でもあるので、しかたないので出かけます。僕の知っている東京という都会は、もっとモダンで、未来への可能性を充分に含んだ豊かな都市であったはずです。しかし、この頃の東京は、何かがずれ、何かが決定的に欠落し、何もかも途方もなくうるさい場所に成り果てました。デューク・エリントン、ビリー・ストレイホーン、マイルス・デイヴィス、その他書ききれない、燦然と輝く彼らの音楽は、その彼らの住んでいた時代と、その街の一番クールなフィーリングを、音楽を通して我々に伝えています。時間を通り越し、時空を超えて。では今ミュージシャンとしてのぼくが、東京という場所に住んで、どんな音が創造できるのか。現実を見たら、ぼくにとっては絶望的です。無味乾燥な音楽が東京で盛んなのもそのせいでしょう。言ってみれば、無味乾燥な音楽こそ今の東京のヴァイブレ-ションを体現しているのかも知れません。僕には全く恐ろしいことです。しかし、ぼくには自分自身が理想とする東京が、確固としてイメージのなかにあります。少々アナクロニズム的なイメージですが、たとえば、両親と銀ブラした時の思い出。子供の頃、デパートの屋上から見た東京の風景。歌舞伎座近辺。夕暮れの東京タワーの上からの眺め。ぼくはこれらのイメージを土台とし、今の東京の音を創造します。誰もが自分が生まれ育ったところを愛したいと思う気持ちには変わりないでしょう。この時点で、菊地氏のイメージとぼくのものが合致したと感じられた瞬間、それは何度もくり返した会合の中での一瞬でしたが、ぼくは菊地氏の指示に全面的信頼をおくことに決めました。我々に今必要なもの、それは審美眼と文化、芸術です。音、味、匂い、色彩、服装のセンス、全てにおいて優美な、ロマンスを感じさせる微妙な何かが自然と生活の中に組み込まれていることが、我々には必要なのです。しかし今はこういった条件がひじょうに生活の中に乏しい。人間二人居れば、もうそこには濃い情の世界が生まれ出ます。またその反作用も人間ならではです。そこに、文化と芸術の意味が絡まってくるのではないでしょうか。これらの文化、芸術が我々の生活にすんなりと属していないとどうなるか。これは考えても恐ろしくおぞましいことですが、我々はゲロとクソをニ本足で支えている、動物以下の動物になってしまうということです。動物以下です。動物は、黙って我々の為に死んでくれて、食料と成リます。核爆弾も作りません。ぼくもピアノを弾かなければ、単なるゲロ袋です。そういう自分の存在も自分自身が許せない。では何ができるか。センスのある、フィーリングのある、すてきな音楽をピアノを通して奏でるしかないのです。まず人間として。そういう思いが、この「TOUCHES&VELVETS」には込められています。そして、この音こそが、東京で生まれ育ったぼくが、はじめてこの街にストレートに突きつけた音楽でもあリます。何の短絡も、自己とその意思の間に横たわる逡巡さえ無しに。これはプロデューサーの采配のおかげです。この場を借りて菊地氏には大いなる感謝の念を送りたい。音楽を始めてこの方、ここまで来るまでに考えぬいた事、いままでやってきた音楽、そこから生じるいろいろな紆余曲折。血だらけ火だるまの時もありましたが、いまやっとスタートラインに立った気がしています。誰が何と言おうと、このピアノの音は、東京に生まれ育った日本人の、南博のピアノの音です。
某月某日
三日続けて演奏の仕事をこなした。別段珍しいことではないけれども、いつもの三連チャンとはまた違った趣のある三日間であった。一日目が通常のクラブギグ。横浜JAZZ IS でサックスの井上淑彦氏のグループで演奏。そしてこの三日間の中日が、横浜ジャズプロムナード主催の、横浜ドルフィーというクラブでの演奏であった。ちょうど台風が関東に牙をむいていた時間帯にだ。幸い我々が演奏していた午後五時前後が一番ひどい状態だったようで、突風と雨はまぬがれたが、リハーサルのため一時半に横浜ドルフィーに到着すると、なんだか外の空気感が重くたれ込んでいるような気がした。しかし、雨風は以外にも静かであった。嵐のくる前触れなのか、なんだか世の中全体をも含めて、逆に大気が静寂に包まれているようで無気味であった。台風が助走をつけていたことは明らかである。前記のごとく僕は一番ひどい状況の最中に演奏をしていたわけだが、クラブに来てからなぜか体と心がざわざわし、いても立ってもいられないような落ち着きのなさが体の中を行ったり来たりしているような気分だった。これは本能的に何かがおきる前兆を予期していたのであろう。普段とは違ったテンションを張り巡らして、ピアノを弾きまくった。台風の前触れを察知したとはいえ、相乗効果というにはあまりにも過分なエナジーが体の中から吹き出し、自分でもびっくりしてしまった。三連チャンと記したが、実はその中日の夜十時から午前一時まで、井上淑彦氏をリーダーとして、ジャムセッションのホストをつとめるという仕事もあったので、日付けをなしに考えれば四連チャンである。午後三時半からの演奏後、体の中では、音楽を演奏するという概念が消失していた。これは長年演奏してきて、一日で、演奏は2回をこなすということが体に染み渡っているせいだろう。次がいくらジャムセッションとはいえ、体の状態や集中力を、音楽のどこの近辺にすり寄せたらいいのか皆目見当がつかなかった。しかし、また考え方を変えれば、貴重な体験となるはずだとも言えよう。実際、セッションの進行、音楽の中身は僕の思った通り貴重な経験となった。プロムナードに招待されてきた大勢のオランダ人と、一緒に演奏した。中に異常に体がでっかいピアニストがすごい演奏をするので、なんだこいつはと思って聴いていたら、どうもこの人は、オランダのジャズシーンではNo.1の、ミケル・ボルストラップという人らしい。欧州全土に、少なくとも一人ずつこういう奴がいるのかと思ったら気が遠くなってきたので、気が遠くなってきたということを理由にワインをがぶ飲みしてやった。こいつらにできないことを、俺は見つけなければならない。今から毎日ステーキ喰ったって、身長は伸びないであろう。かといって妙な浪花節は大嫌いだし、しっけた音を出すのもいやだ。たぶん答えは、オランダ人とか日本人とかそういったことを飛び抜けたところにあるはずである。僕の発想を裏打ちするが如く、ミケルとサックスの井上氏、ドラムの久米雅之氏が互角にわたりあった、打々発止のそれこさセッションは大変な見物だった。二人とも本当にすばらしかった。良いミュージシャンにカコマレタ僕は幸せ者だ。それでまあ、それやこれやで当初の午前1時セッション終了は案の定のびて、プロムナード実行委員がとってくれたホテルに帰ったのは午前2時過ぎとなり、ベッドの上に僕ものびてしまった。さて、三日目はパーティーの仕事であった。ベースデュオにてあるオシャレな輸入家具などを扱っている会社の展示場にて演奏。通常のクラブギグ、延長戦でこなしたジャムセッション、そしてパーティーでの演奏だ。すべてにおいて、演目も違えば、演奏自体の雰囲気も変えなければならず、同時に南博である自分が演奏しているということもアピールせねばならない。この変化をつけることは、そう大変なことではないが、演奏後の疲労感は普通のクラブギグを三日連続で演奏するよりやはり疲れる。ということで、明日はお休み。
某月某日
長らく日記を書かなかった。これほど暑い夏も珍しいもので、その中をくぐり抜けるようにして、いろいろな事をやり、いろいろな演奏をし、音楽を中心に夏が廻っていった。前の日記にも書いたように、7月から半月ほどコペンハーゲンに滞在。気温15度前後という世界に居り、帰国して降り立った鴬谷駅で、それこさウグイスの幻聴が聞こえてきそうな暑さに苛まれ、8月は新譜のジャケットの撮影のため訪れたNYも。気温26度前後という適温であり、帰ってきてまた身体に日本の夏の暑さと湿気がずしんときた。デンマークへ行って、NYに行って、逆にデンマーク人達を日本に呼び寄せ、日本ツアーをしたのであるから、書く事には事欠かないのだが、それらのネタは全て、EWEの発行する次号の「JAZZ TODAY」に記事として書いてしまった。これらの経緯に興味のある方は、「JAZZ TODAY 09号」を読んで下さい。確かにこの二つの事は、いろいろな演奏の間に挟まった夏の大行事であったが、ここでは、その影に少し隠れた、しかし大いに意味のあるすてきな仕事のことを書きたいと思う。NY帰国直後、しかも一番暑い盛りに、大久保のスタジオにて、水谷浩章(B)、芳垣安洋(DS)というメンバーで、一曲だけレコーディングをした。このメンバーでは初めてのトリオ録音である。ヴァイナルソユーズというレ-ヴェルからの依頼に賛同し演奏したものだ。コンピレ-ションアルバムである。まずは、ヴァイナルのプロデューサー、清宮陵一氏の意見をここに記したいと思う。ドメスティックジャズコンピレーション(仮)について。コンセプト「様々な局面で世界的に変革の時期を迎えているまさに今、日本で起きている事」これまで何度も大きな時代のうねりと戦ってきた「ジャズ」という音楽。2004年という時代の空気を「ジャズ」という切り口で長きに渡って伝えられるような盤を製作したいと思っておリます。ジャズとはかくあるべし、ということを無視するところに今のジャズがある。今回ご参加いただきたいと思った方は、そのボーダーラインを飛び越え、今までの枠を大きく広げてみせてくれるパワーがある。その枠を超えようとする姿に、私を含め音楽が好きな人間はみな惹かれるのだと思います。また、この作品はバンド全体と言うよりは”ミュージシャン個人に焦点を当てる”構成にしたいと思っておリます。日本のジャズの最も面白いところは、各音楽家それぞれ個人の強力な個性によってグループが支えられ、さらにそれがパラレルにリンクしとてつもなく強固な基盤を築いているところです。コンセプトの違う様々なバンドで演奏し、毎回見るたびに違った新鮮な衝撃を与えてくれる。音楽の現場として最も魅力的で、原始的で、本質の部分を持ち合わせている「ジャズ」をもっといろいろな人に、いろいろなカタチで知って欲しいと思っておリます。このCDをリリースするというひとつのスタートラインを機に、現場により足を運ばれるような、様々な活動を微力ながらさせて頂きたいと思っておリます。参加をお願いしている方々(50音順)大友良英 NEW JAZZ QUARTET勝井佑二 ROVO菊地成孔 DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN外山明+大儀見元PERCUSSION DUO不破大輔 渋さ知らズ水谷浩章+菊地雅章 BASS DUO芳垣安洋 VINCENT ATMICUS南 博 TRIO 清宮令陵一タイトルはまだ未定であり、ぼくのトリオが最後ということ以外曲順もいまだ未定。だが、発売は12月中旬を目指し、清宮氏は今、その総仕上げに奔走中だ。そうそうたる布陣である。上記のコンセプトについては、演奏後に説明を受けたものであるが、いずれにせよ、このようなコンセプトの仲間入りができることだけで嬉しい。しかし、レコーディング当日は、スタジオまでたどり着くこと事体で精一杯であった。粘り着く時差ぼけ、急激な気温の変化による体調不調。帰国後次の日にも演奏があり、その次の日がこのレコーディングで、しかも集合は午後1時。さすがのぼくも首筋がまっすぐにならないような状態で、腹時計は夜中を指しており、外界は、マレに見る炎天下。食欲なし。だが、一瞬そのスタジオのピアノに触れた瞬間、ぼくの体内で何かが起った。すばらしいスタインウエイがそこには用意されていたのだ。コリアン、チャイニーズのレストランを両側にかわるがわる見ながらたどり着いた大久保のスタジオには、純正ヨーロッパのサウンドのするピアノがあった。低音域はダブルベースを、中音域はチェロを想起させ、高音域から上は花々しいピアノの音に彩られたそのピアノは、コリアンとチャイニーズの行き交う道の裏にぽつねんと置かれていた。東京はこういうところが奥深い。とにかく、すばらしいサウンドに恵まれたその日のぼくは、時差ぼけだ何だ言ってられなくなってしまった。我がバンド、GO THEREで、いつも最後に演奏する「PRAISE SONG」という曲をトリオで演奏した。PRAISEとは、賛美するといったような意味だ。神への賛美という意義にも用いられる。ぼくはノンポリで、宗教政治に関してはフリーである。しかし最近の人類の動向を見ていると、もうロクなもんじゃない。「BOWLING FOR COLUMBINE」も見たし、「Fahrenheit911」も 見たし、「アホでマヌケなアメリカ白人」も読んだし、「アホでマヌケなマイケル・ムーア」も読んだ。正否はあえてコメントしないけれど、この地球上では恐ろしいことが起きていることは確かだ。僕らの生活に今必要なもの、それは審美眼と文化、芸術だと思う。音、味、匂い、色彩、服装のセンス、すべてにおいて優美な、ロマンスを感じさせる微妙な何かが自然と我々の生活に組み込まれていることだ。我々が街で見るもの、聴くものの七割は雑音であり、景観の観点から見ると、もう無茶苦茶な街だと思う。今の生活がいつまで地球環境的にもつか、ぼくは化学者ではないから詳しいことは知らない。しかし、これから東京はいい方向に変わって行って欲しい。その時点でぼくに何ができるか。そういう期待をかけて、ぼくができることを演奏した曲が「PRAISE SONG」です。発売を楽しみにまっていて下さい。
某月某日
KASPER TRANBERG SEXTET JAPAN TOUR FROM DENMARK さあ、今年もやってくるぞ。ユーラシア大陸の北端から、その名も轟く ヴァイキングの末裔達。しかし、昔の歴史がそうであっても、今現在のデンマークは人口550万人の小国で、面積はほぼ九州といっしょ。税金が52%科せられる変わりに、生まれてから死ぬまでのあらゆる公の機関はタダの国となった。人類の到達する最良なしくみを持った国家のひとつだと思う。今回日本に来て演奏するデンマーク人達は、昔の血を充分にその身体に受けとめたヴァイキング的気質と、ヨーロッパの中でも最も清潔に洗練された家具、ヤコブセンなど、機能美のみに終わらないセンスある空間で、剛胆にして繊細な環境にて生まれ育っています。彼らの音楽には、その両極がうまく組み合わさった、しかもヨ-ロッパ的品格が随時サウンドの中に垣間見れる音楽を演奏します。前記のごとく、演奏の内容は剛胆であり、同時にセンシーヴルではあるが、演奏が終わった後は、ただのヴァイキングに成り果てることが多い。昨年のツアーで、僕を含む6人でびっくり寿司にいったら、15万円飲み食いしやがった。ヒロシはおごってやるという条件であったが。友達思いは良いとして、伝票を見た僕は腰をぬかした。まあ、楽屋裏のねた話しはここまでとして。デンマークとジャズという組み合わせは、一般的にあまりマッチしない組み合わせではある。しかし、この21世紀の時代に於いて、こと芸術に関しては、人種、国境はもはや科学の力により止める術もないほど、世界は一体化している。その国々によって、すばらしいインプロヴァイザーが居り、気鋭の彼らはどんどんデンマークの外へ演奏の場所を広め、今回は、何故か日本人一人とデンマーク人五人のいう、圧倒的不均衡によって、新しい物語がはじまるわけです。この組み合わせ、コペンハーゲンに行ったって、早々見聞きできない。ものすごい事が、今月、日本各所で爆発するのです。こんな音楽、手前味噌ですが、なかなか聞けるもんじゃありません。さあ、来たれ音楽好きよ。さあ、来れ、予定調和に飽き飽きしたジャズファンよ。我々のふところは深いぞ。何でも呑み込んじゃうんだから。ビールのみならずね。そして、来れ若者よ。僕らの演奏時は、決して誰をも裏切らない。「KASPER TRANBERG SEXTET IAPAN TOUR FROM DENMARK」のフライアーを見たり渡されたりした全ての皆様へ。今日は、
某月某日
などと言っていられない。皆様申し訳ございません。演奏時間に関して間違いがありました。9月12日(日)のMOTION BLUEの入れ替え公演の時間は、PM5:30 &PM6:30ではなく、正確には、PM5:30&PM8:00の間違いです。本日8月25日以降、時間をあらためたフライアーをつくります。今日以降のフライアーには正しい時間が載っています。WEBのフライアーも正しい時間になおしました。http://www.shinya.comm.to/minami.htmlまた、MOTION BLUE のSCHEDEULEもチェックしてみて下さい。http://www.motionblue.co.jp/schedule/index.htmlどうかお間違いの無き様、御来場をお待ちしております。