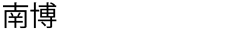某月某日
前回の日記には、自分の夢の事を描写してしまったが、聞く人によると、夢の描写は現実感の喪失につながるからよせと言われた。暖かいアドヴァイスは別にして、こん週末からの演奏の要を、今回は紹介することにする。この一文は、前の日記に書いたものと重複するのだが、日が迫ってきたと言うことで、あえて二重写しにした。これらは全てぼくが仕組んだ仕事なので、ぜひ大勢の人に聞きに来てもらいたいと思う。一:井上淑彦氏と初めて中目黒のクラブ楽屋に出演。ここのアジアンフードはかなりうまい。もちろん井上氏の演奏もうまい。初めての場所と言う設定も、ミュージシャンには演奏に火をつける要素でしかない。レッドチリペッパーとともに、井上氏のサックスの音を聞いて、皆で涅槃を散歩しましょう。こんなロケーションと演奏、身が二つあったら俺がお客で行きたいぐらいだ。中目黒近辺の人も、そうでない方もいざ楽屋へ。詳しくは楽屋http://www.rakuya.net/電脳フライアーhttp://www.shinya.comm.to/live.html二:ジプシー系ドイツ人のヴォーカリスト、MELANIE BONGと都内近辺にて短いツアー を企画した。知り合いの日本に住むドイツ人から紹介されたのだが、ブラジリアンのようなものも軽くうたいこなす、ちょっといい女である。(送られてきた写真を見ただけだけど。)声質がぼくの好みだったので、仕事をとってみた。詳しくは、MELANIE BONG http://www.melaniebong.de/ 電脳フライアーhttp://www.shinya.comm.to/minami.html以下彼女の経歴を簡単に紹介する。メラニー・ボング MELANIE BONG (VOCALIST, COMPOSER)ドイツに生まれる。現在はミュンヘン在住。彼女の父親はシンティ族というジプシであった。10代後半から歌いだし、「Melanie Bong Crew」という最初のバンドを結成する。学校を卒業の後、アメリカの有名なシンガー、シェ-ラ・ジョーダンに師事。 後、ドイツを中心に世界的に活躍の場を広める。(P)ウオルター・ラング(ドイツ),(B)デヴィッド・フリーゼン(USA)等を筆頭に、多くのミュージシャンと共演。彼女の最初のCD「SMILE」はモダンジャズ的なアプローチに満ちたもので、日本でも発売される。2001年、2枚目のCD「FANTASIA」は、彼女が作曲した曲が全編を構成し世界中で発売された。彼女のブラジル音楽への傾倒をはっきりと打ち出した内容のもので、作曲家としても認められる。ちょっとかたい文章だけれど、当日なにがハプニングするか分からない所が、今回の出色な部分で、いまから演奏者自身も楽しみでしょうがない。まず御来場を、そして、今月の南博は、大幅に予定調和の仕事がありません。いままでやってきた音楽も、この国の中では予定調和の部類に入らなかったと思うけれど、今回はさらにまた更にその部分から遠のく所存です。自分で考えても、今週末から来週にかけて贅沢な仕事させて頂く喜びでいっぱいです。
某月某日
今日は導入剤の助けを借りずに寝られると思い、坂口三千代著「クラクラ日記」を読んでいたら、本当に気付かぬまま眠ってしまった。しかし眠りは浅く、とんでもない悪夢を見てしまった。JRの駅だと思うが、それに似通った大きな駅に夢の中の自分は立っていて、その駅から仕事場へ、つまり演奏のために駅を出る。その演奏場所が凄まじくコンディションが悪く、共演者も初対面であり、高校時代けんかした奴にそっくりなベーシストなども居て、雰囲気も最悪。仕事が終わってやっと駅に戻ったら、見覚えのない表示と駅名だらけで、しかしなぜかここは東京の郊外、埼玉、千葉の方のような感なのである。とにかく電車に乗ると、そこには質の悪いサラリーマンの酔漢、どうしようもない、手のほどこしようもない高校生の不良グループなどが乗っている。誰かに帰りかたを聞くような雰囲気ではない。床には嘔吐された汚物が散乱し、次の駅で別の車両に移ることにする。とにかく今乗っている電車が自分の家の方に向いて走っていると言うことが知りたいのだがそれどころではない。気がつくと、前に乗っていた列車に貴重品、カバンなどを置き忘れていたことに気付き、また次の駅で、最初に乗った車両に乗り換える。カバンは床にぶちまけられた嘔吐物の上に、更にカバンの中身がぶちまけられていて、金品に変わるようなモノはみな無くなっている。スペアに使っている眼鏡も何ものかがふんずけたらしくガラス部分も粉々で、ぺッチャンコになっている。まわりを見渡すと、ものすごい視線が集まってきて、抗議するどころでない。今必要なのは、正しい家への帰り方である。次の駅でその電車は終点なんだか、全員おりることとなる。プラットフォームに降りてみると、非常に複雑な立体交差的線路が、頭上に展開されてい、その中のどれに乗ればいいか、皆目見当がつかない。これ以上家のある方角とは反対の電車には乗りたくない。プラットフォームにいる何人かのサラリーマンが急に駆け出す。ぼくも反射的について行くと、今まさに、ドアを閉めんばかりの別の電車が、出発する所であった。他のサラリーマン軍団といっしょに、ぼくもしゃにむにその電車に乗ってしまう。愚連隊のような奴等であふれていたさっきの車内より、こっちの車内の方がましだと思ったからだ。しかしこの電車が家の方向に走っていくものともかぎらない。車内にある路線図を見るが、この電車が今何線で、どこの駅に向かって走っているか、皆目見当がつかない。まわりの人に聞いても、なんだかはっきりした答えは出てこない。外の景色は見覚えも無し。その電車が止まった次の駅は、薄暗いながら、何らかのターミナルを要した巨大な駅で、ここでなら家の方に向かう電車がありそうな気がして飛び下りる。プラットフォームに駅員らしきものが居たので、まず、私はどこにいるのでしょうと話しかけると、あれを見なさいと赤旗を持った方の手で、薄暗い先を指し示す。そこはプラットフォームの先端部で、その先から、遊園地にあるような小型電車が、地中から何本も走り出してくるのが見える。利用客は、その小型電車の外側にへばりついたり、屋根につかまったり、振り落とされないように、必死な形相でつかまっている。しかし何人かの脱落者がぼくの目の前で振り落とされる。落とされると、電車とレールの間に引き込まれて血だるまとなって轢き飛ばされる。駅員はぼくに、あれに乗りなさいと言う。一旦次の電車が地中から出てくるのをプラットフォームから線路に降りて待つことにした。次の電車はすぐ来た、電車の側面に、沢山の人間が、必死の形相でつかまっている。しかし、大きな駅に到着するためなのか、その小型電車は速度を落とす。今がチャンスかと思い、まずその小型列車を走って追っかけて、最後尾の隙間に何とかしがみついた。何人もの脱落者がゴロゴロと線路際に血だるまになってころがってくる。最後尾なので、列車の両側を流れる強い風を避けることはできたが、何かの拍子にぼくも転げ落ちるかもしれないと思うと、生きた心地はしない。やっと次の駅についてみると、前の駅にも増して複雑な構造の駅に立ち降りたことに気付く。天蓋の向こうには、沢山の電車が走っており、ぼくはどこかの地下にいるようだと言うことがわかる。天蓋の向こうの電車に乗り変えるには、階段などなく、みな高熱でグニャヤ二ャまがった鉄柱をそれぞれの力量で、登ろうと必死になっている。ぼくも天蓋まで行けば、家の方に向かう電車があるような気がして、グニャグニャになって折り重なった鉄柱を手足を使いながらよじ登りはじめる。やたらと体力と気力を要するということが、登り始めてから分かった。地下の駅と天蓋の駅は相当な高さで離れてい、手を滑らせたら落っこちて死ぬだけである。鉄骨のジャングルジムと格闘しながら、やっと天蓋の駅に登りつめて頭を出すと、そこは、線路のまくら木のあいだであった。前方から電車がフルスピードでやってくる、、、、、、そこで夢から醒めた。午前二時頃である。寝覚めも悪く、気分も悪く、明け方までまんじりともせず過ごした。
某月某日
世はゴールデンウイークである。誰がこのような「ゴールデンウイーク」なる名前を命名したのだろうか。黄金週間。金色に輝く日々。むかし貨幣は、兌換紙幣といって金と交換することができたそうだ。いまは信用だけで成り立っているらしいが、そこから先の事は、経済オンチなので分からない。ただ、紙幣には日本銀行券と書いてあって、お金が欲しいなあとは思うが、券が欲しいなあとは思わない。いずれにせよ、この黄金週間のあいだ、この銀行券が労働者からサービス業、運搬業の方に流れ移るということは確かだ。だから命名者はサ-ヴィス業に関与している人達が考え出したのではないだろうか。ぼくの職業は、まあサ-ヴィス業と言えるかもしれないが、そう100%言えない部分もあり、この何日かは、ゴールドが頭の上を飛び交うのを、じっと家で眺めている。労働者は、決まった祝日しか休めない。我々は、仕事がなければ即その日が何曜日であろうと休みである。わざわざ人混みのなかに身を投じるのは、逆に我が特権をダイナシにしていることと同じであり、だから遠出など仕事以外しない。特に散財もしないし、行きつけの店は、それこさ休業していることが多いから、じっと鍵盤などを見つめている。どうしても解せない不思議なことは世の中に多々あるが、これだけ不況だ不況だと騒いでいて、どうして高速道路が渋滞したり、海外に遊びに行く人々で、成田空港がいっぱいになるのであろうか。ああいう所にいない人が、逼迫した生活をしていると言うことなのか。ぼくは留学という名目でアメリカに住んでいたことがあるが、海外とは、観光客には甘い口をきくが、いざ一旦住む者にはとてつもなく厳しい場所である。毎年ヨーロッパに行くが、それも仕事であり、時差ぼけのなかを何とかかいくぐり演奏をしたりしている。遊び、観光という目的で外国に行ったことがないので、よく分からないが、現地でも観光者はゴールドを落とすのだろう。本当に不況なのか。何をしていったい豊かというのかが良く分からぬ我が国は不思議な国家である。と言いつつ、このぼくも、ゴールデンウイークの初日だけ、普段とは違う行動をした。先日、生まれ育った世田谷の団地を、カメラとともに訪れたのだった。従姉妹が世田谷の役所に勤めていて、ぼくが物心つく前から小学校5年生まで住んでいた公団住宅が、再開発のためとり壊されるという話を彼から聞いたからだ。あまりむかしの事に固執するタイプではないが、なんというか、言葉の選び方のセンスが悪いのを承知で書くと、心の原風景みたいなものが無くなる前に、フィルムにおさめておこうと思ったのである。その団地は、新宿から京王線に乗って行く場所にある。懐かしいはずの駅前は、改札口が地下になっていたので、あまり懐かしさの感慨はわかなかった。遠足の時の集合場所であった駅前の広場も、なにやらどこでも見かける弁当屋などが商売をしており、なんだか土地を細分化してさらに細分化して、色々な商売を林立させるという、東京にありがちなごちゃごちゃ感が駅のまわりを支配していた。母親からいつも、渡る時は車に気を付けてといわれていた駅前の通りも、なんだか非常に狭く小さく見えた。子供のころには大通りに見えたのに。ぼくが生まれたのは1960年、ちょうど日本が高度成長期という時代をむかえた時だ。経済が上向きになるのに比例して、ぼくは育っていった。テレビ、洗濯機、掃除機が三種の神器などと言われていた時代で、ぼくはこの団地で、確かアポロが月に降り立ったのを白黒テレビで見ている。あの日だけ、特別のよふかしを許されたような記憶がある。駅から住んでいた団地への道をたどって行くと、よく野球をして遊んだりしていた広場がフェンスで囲まれているのを発見した。何か建物が立つのだろう。その場所には、当時の雰囲気は残っていないが、ぼくの心のなかに、当時夢中になってボ-ルを投げていた野球遊びの後の爽快さや、名前は忘れてしまったが、当時の近所の友達の面影がスっと頭をよぎった。その広場の横は団地の集会所で、保育園も兼ねていて、ぼくもそこに毎日かよっていた。当時のままの佇まいでその集会所はあった。太陽が真上にあって、ものすごく天気の良い日で、だからこそ光と影の差が激しく、カメラの絞りを設定するのに逆に難しいぐらいで、とにかくその集会所をフィルムにおさめた。集会所から住んでいた団地、5号館への道は変わりはてていた。流れていた小さなドブ川は埋め立てられてい、工事中のフェンスのようなものが、川沿いを囲っている。当時ドブ川の向こうには、とある化粧品の工場があり、なんだかわけのわかんないどろどろしたものが、排水口からそのドブ川に流れていた。ドブ川の上には、1メートルおきぐらいに、細いコンクリートの四角い棒のようなものが架かっていた。幅は30cmほどのもので、根性だめしとかいいながら、よく綱渡りの芸人よろしくドブ川の両端を行ったり来たりした。たまに足を滑らせ、ドブ川にはまる者が出る。ぼくも何度も落っこちた。下半身はどろどろとなる。どろどろをひきずって家に帰ると、母親はその場に立ちすくんだものだ。なんだか強力な科学物質とばい菌があの水分には含めれていたような気がするが、当時はなにが起きてもへいちゃらだった。ドブ川のみならず、広場として記憶にあるあらゆる場所が、すべて駐車場と化していた。5号館が目に入った。懐かしい。しかし4号館はもう無かった。恐ろしいほど巨大な公団住宅が5号館にのしかかるように建っていた。もう少し来るのが遅ければ、5号館、そう、ぼくの子供のころ寝起きしていた公団住宅は無くなっていたに違いない。5号館に近付く。雪の日、かまくらを作って遊んだ団地裏のスペースは、もう巨大公団の敷地にのみ込まれて無かった。じっと5号館を見た。こんな小さい建物の、こんな小さい横幅の、こんな長方形の建物に、俺は住んでいたのか。しかも24世帯ぐらいが同じ屋根の下に同居していたのだ。たしかぼくの部屋のとなりは、スペイン語の大学教授だった。真夏の夜、汗だくになりながら、その隣の家で、スペインに行っていたその教授の写した写真のスライドを見た覚えがある。あれが初めての、ぼくにとっては生の外国の風景だった。確かスライドは押入れのとびらか何かに写し出されていたのだと思う。近所の子供がぼくと同じくすし詰め状態でそのスライドを見ていた。映写機と人間の熱気でムンムンしていた。そんな悲喜こもごもが、この小さな横幅で行われていたのかと思うと、感無量だ。ここで皆生活し、排泄し、交接もし、本当に何度も書くが悲喜こもごもがあったのだ、この横幅で。下の階には御夫婦とも高校の先生をしていらっしゃったKさんだったか、名は忘れたが住んでいた。沢山の本があった。こんなに沢山の本が世の中に有るとは当時、子供だから思わなかったので驚いた記憶がある。そこのうちにはお嬢さんがおり、当時高校生ぐらいで、いつも受験勉強をしてた。その彼女の部屋にも、沢山の本があった。あれは今から考えると、女性の部屋に入った初体験であったのだ。彼女から、ぼくにも読めそうな本を借りたことを思い出した。この5号館を目前にすると、もう書ききれないほどの、朝の、昼の、夜の、夜中の、日々の、春夏秋冬の思い出が渦巻いてくる。一言で団地と言っても、色々な種類の人々が、狭い区画のなかで、様々に暮らしていたのだ。あたりまえの事だが、すごいことだとも言える。あの横幅で。気がついたらシャッターをきりまくっていた。これが最後だな。故郷のないぼくの故郷のような所が、姿を消すんだ。ぼくの住んでいた5号館の階段の前にくると、もうそこには誰も住んでいないことが分かった。皆どこかへ引っ越したか、新しくその地に建つ公団住宅に入りなおすかするのであろう。階段を上がり、以前住んでいた部屋の、鉄のドアの前までいった。ここでぼくが赤ん坊のころ、このドアの真ん前で、正月に写真を撮ったのだ。親父に抱かれて。写したのは母親だろう。こんなに小さい建物の中に家族四人が一時暮らしていたのか。4号館には、集会所で知り合ったN君が住んでいた。N君がピアノを習いに行くというので、ぼくもついていった。なぜだか分からないけど一緒についていった。それが全ての始まりである。N君は高校受験のためピアノを習うことをやめたが、ぼくだけ極道に入ってしまった。思えばその団地から、読売ランドの先にあるピアノの先生の家までかよっていたのである。駅前の当時大きく見えた道からバスに乗って成城学園駅まで行く。そして小田急線に乗り換えて先生の家までたどり着く。このレッスンには、N君の向いに住んでいたHチャンも参加するようになった。ぼくはN君,Hちゃんと比べて、格段に覚えが遅かった。みながどんどん赤マルをもらってハノンを上がりチェルニーだブルクミューラーだと進んで行くのに、ぼくは、不器用だったのと、頭がボーッとしていたのとが相乗効果となり、みんなにどんどん間をあけられてしまった。なぜピアノのレッスンが続いたかと言えば、習っていた先生が好きだったという理由だけである。でも弾けないものは弾けない。この建物の小さな横幅のそのまた小さな部屋に、カワイだったか、電気ピアノを買ってもらって練習していたのだ。スイッチを入れると赤いランプのつく、小型電気ピアノだった。近所の事を考えてか、その楽器はヴォリュ-ムが調節できたから、夜になっても弾いていた。外で友達がローラースケートで遊んでいるのを窓越しに見ながら。なんという狭い空間での、出来事の多さだろう。記憶とはすごいものだ。この記憶を呼び覚ます風景や建物は、遅かれ早かれこの世から消える。一階には、名は忘れたが、近所の子供をまとめるガキ大将が住んでいた。一階に部屋があったからか、ベランダの前に犬を飼っていた。はたして、当時の公団住宅で動物を飼って良いのか悪いのか、そんなことは今となっては分からないけれど、その犬の名前はなぜか覚えている。ロンちゃんといった。皆でロン、ロンと呼んでかわいがっていた。4号館の裏にある給水塔は、5時になると鐘の音をならす。もちろん録音されたものだと思うけれど、それが家に帰る合図の音だった。その鐘の音を無視して外で遊んでいると母親にしかられた。実際に、給水塔はまだ建っていた。当時そのあたりでは一番高い建物だったのだが、ぼくが見たその時は、巨大公団住宅の横で、ちょこッと建っているマッチ棒みたいに見えた。ぼくは写真を撮りまくる。全てを、少なくとも画像に残しておきたいという、この衝動はどこから来るのか。給水塔も撮った。あらゆる角度から。鐘の旋律は今も覚えている。ラソファソ、ドソラファ、ファラソド、ドソラファ。毎日放送されていたこの鐘の音にぼくは今、何らかの音楽的影響を受けているのだろうか。どうあれ、毎日聞いていたことは確かだ。キンコンカンコーンという音だった。思えば不思議な現象ともいえる。役所や会社のように管理された空間では無いのに、毎日5時になると鐘の音がする狭い空間とはなんだったのか。他の音の記憶をたどってみた。家にはクラシック名演集のような小さい盤のレコードがあった。母親がたまに聞いていた。お決まりのモーツアルトとかああいった類い。ぼくにはあまりピンとこなかったが、今から考えると、習っていたことは、いずれこのレコードの中の音を再現するための技術と音楽性であった。親父といっしょに風呂に入ると、親父は必ず軍歌を歌った。この方がぼくの耳に残っている。後はトランジスターラジオの音質の悪い音で聞く野球観戦の音。タイガースファンの親父は、タイガースがホームランなどで逆転すると、隣の四号館にまでこだまするような拍手を風呂場で放った。その音の記憶の方が、正直に言ってモーツアルトより上だ。他は、テレビの人気マンガ番組の主題歌のソノシートを何枚か持っていた。持っていったフィルムはあっという間に使い果たしてしまった。これらの写真は、他の人にとっては何の意味も成さないものであろう。だがぼくには、この画像一枚一枚に、数えきれない思い出と記憶、感情、感傷、時の移り変わりに対する思い、それらがいっしょこたになっているものである。真昼時、まったく人影がない団地のはざまで、ぼくは闖入者と呼ばれてもおかしくない状況にあった。空き巣ねらいとして、警官に誰何されても返答に困るような状況でもある。さすがにぼくが以前住んでいた団地のドアを開けるようなことは差し控えたが、階段を登り、いろんな角度からシャッターをきったりして、夢中であった。まわりに人が誰もいないということから来る恐怖も感じなかった。誰か昔の知り合いがひょっこり顔を出さないかな、なんて、なんとも現実離れしたことを夢想させるほど、その日は天気が良く、写真を撮るには絶好の天気であった。難をいえば、フィルムをもう少し持ってくれば良かったということだけであるが、ある意味いくら撮ってもきりがないから、フィルムの無くなった時を潮時として、また駅の方に向かって歩き出すことに決めたのだった。その前に、もう一度、ぼくが住んでいた部屋のベランダをあおぎ見た。やはり誰も住んでいない様子であり、物音ひとつしない。声に出して「アデュー」といってその場を離れた。駅まで来ると、こんどは、通っていた小学校の通学路や、その小学校にもいってみようかとふと思ったが、やめることにした。ゴールデンウイークの初日の日の、午前10時から12時過ぎまで、ぼくは、過去自分が居た場所をさまよっていたのであった。きりがない。もう充分だ、と自分に言い聞かせ、京王線に乗って帰ることにした。フィルム代、電車賃あわせて1000円前後で経験したタイムトンネルだった。少し感傷的になったりもしたが、心の芯の部分では、何か充実したものが感じられた。ぼくのゴールデンウイークはこれにて終わりである。