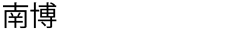某月某日
机の中を整理していたら、昔の恩師の写真がでてきた。元芸大ピアノ科名誉教授であり、日本のクラシック界の重鎮でもあり、ある意味昭和デカダンスを音楽で体現したピアニスト、作曲家の宅孝二氏の写真である。偉大なる人物であった。当時ぼくは19才で、通っていた音楽高校のピアノの先生に、ジャズを聴いていることが発覚し、それが元で喧嘩状態となり、学校をかろうじて卒業後、どうしたらジャズピアノが弾けるようになるのかと、そのことばかり考えていた。先行きの見えない、ひじょうに不安な心理状態で、今から考えると、本当に中ぶらりんな状態であった。音高から音大へという通常の道は断たれていた。そんなとき、とある親切な知人の紹介で、宅先生のマンションにレッスンに通い出したのは、世の中をやぶ睨みして、どうとでもなれという状態の時であった。当初の情報では、クラシックのみならず、ジャズもいける人だと言うことぐらいしか、ぼくは聞いていなかった。当時五反田に住んでいた宅先生のレッスン初日から、ぼくは色々なことに開眼し始めた。ピアノの演奏技術のみならず、宅先生の存在自体がぼくにとっては巨大であった。当時のぼくは、ただ単にはんちくなバカな若僧であり、とても宅先生自体に近付ける存在ではなかったと思える。が、しかし、宅先生は、ぼくを同等に扱ってくれたのであった。特に威張るのでもなく、先生の持ち味をそのままぼくの目前で、演奏で披露した。ぼくは宅先生が大好きになった。当時の宅先生とぼくの関係は、距離に例えれば地球を2週して追いかけても姿さえ見えないぐらいの差があったと思う。しかしなぜか、ぼくの当時の心情に通じ合う何かが、宅先生の中にもあった、先生も決して世の中をストレイトには見ていなかった。そこには底なしの優しさも混在しているのだが、宅先生の中には、野太い反骨精神のようなものがあって、それをぼくが嗅ぎ付けたのではなかろうか。宅先生の部屋には、楽譜とグランドピアノ、ハモンドオルガンがあったのみのような記憶がある。あとは可愛がっていた白い猫。何もできない、何も弾けない当地のぼくの後ろで、粋なオルガンで伴奏をつけてくれたり、南君、この曲はノン・シャラントに演奏するものなのだよ、そうねえ、この言葉に値する日本語はないねえエ。まあ、こいういう感じと言って弾きだすそのピアノの音の中には、19才のバカな若僧の耳にもわかる、何だかとてつもない本物の音が響いていた。それまで拮抗していた、音楽学校の授業やレッスン、その当時もっていたクラシック音楽の概念を、一発で粉々にするような音だった。と書くと、なにやら激しい爆発的印象を与えるが、決してそんな音ではない。優雅でエレガントで、ある意味退廃的でとてもカッコがよい音としか、文章では著せない。宅先生は50才を過ぎて、突然ジャズピアノに開眼し、芸大の職を追われてもヘイチャラで、若者に混じってジャズピアノを弾いていた。当時既に70を過ぎていたと思う。とんでもない巨星である。半年ばかり習ったきりだが、ぼくは、その時間の長さに関係なく多くの事を宅先生から学んだ。レッスンに通うということ自体が楽しみになるなんて、当時経験したことがなかった。色々な思い出がある。でもここには書きたくない。なぜだか、この日記には書きたくない。宅先生を尊敬するがゆえである。ひとつだけ披露すると。ある日、ぼくは宅先生のレッスンを受けるべく駅から先生のマンションに向かって歩いていた。駅からマンションまでは一本道であり、坂を上がる格好になる。ちょうど駅からマンションの中間点にさしかかった時、宅先生が前方から歩いてくるのが見えた。腕を組み、何かを真剣に考えている様子で、でかい黒のサングラスをかけ、ぼくが上がって来た坂を駅の方に向かって歩いてくる。すれ違う瞬間に、ぼくは声をかけ損ねた。何か声を書けてはいけないムードが先生の廻りに漂っていた。先生はぼくの事にも気付かず、すたすたと駅の方へと歩いていった。ぼくは宅先生のマンションのドアの前で1時間ほど立って待っていた。待っていることがなんだか嬉しかった。宅先生は本当にかっこいいなあと思った。なぜそう思ったかうまく文章では言い表せない。あの、何かを考えている姿こそが、ぼくにとっては今日のレッスンだったのだと思った。ノン・シャラントとは、フランス語で、気ままにとか、軽快にといった意である。それを演奏で教えてくれた宅先生が、ぜんぜんノン・シャラントではない時もあるのだということを先生が体現したことで、その日は充分満ち足りた気分であった。宅先生はヘビースモーカーで、レッスンが乗ってくると、自らピアノを弾きだして止まらず、灰が鍵盤にぱらぱらと落ちる。その姿の見事だったこと。後にぼくがピアノを弾くと、白鍵が灰色になっていたりした。19才の音高脱落者のぼくにとっては、見たことも聴いたことも想像したこともない存在が宅先生であり、神秘的な存在だった。宅先生に習っているという気持ちの張りがなかったら、あの当時ぼくはどうなってしまったのかと今だから思える。宅先生は大正末期から昭和の初めにかけてだと思うが、パリに留学しておられた。当時のパリに居たということ自体、音楽にかぎらず、あらゆる分野の最頂点を体感したはずであり、宅先生の演奏にも、それは聴き取れるものだった。もちろんぼくは戦前のパリなど行ったことがない。しかしなぜだか宅先生のピアノの音の中にはそういう要素がいっぱい詰まっていることが聴き取れた。音楽はすごいと思った。ある日、レッスンが終わってふと壁際を見ると、古いレコードが床にころがっている。よく見ると、昔の字体で近衛某指揮、東京帝国管弦學団演奏、ピアノ宅孝二、チャイコフスキー・ピアノコンチェルト日本初演なんて書いてある。これは少なくとも戦前の録音であり、ひじょうに貴重なものと思えたので、先生、これ貴重なもんじゃないんですか、大切にしまわないでいいんですかとぼくが問うと、宅先生は顎をさすりながらにやっとしただけだった。何だかとてつもない、ものすごい人にピアノを習ってるんだなあと思った。嬉しかった。半年ほど習った後、経緯は忘れたが、なぜだかぼくはキャバレーや、色々なところで演奏している状態となり、演奏の中で何かを発見するごとに、なるほど、これが宅先生の言っていたあれだ、これだと、レッスンの内実と現実がシンクロナイズしてきて、またまた嬉しくなってたまらず、もう少しうまくなったら宅先生のところに会いに行こう。また後ろでオルガンを弾いてもらおう。ぼくが少しうまくなったとこを見せてやろうと、もう少し、もう少し、と思っている矢先、宅先生は突然死んでしまった。その知らせを聴いた時、ぼくは本当に悲しかった。こんなに悲しいことってあるかと思った。なぜもっと早く宅先生に会いに行かなかったのか。ピットインの朝の部に出られるようになりました、ぐらい挨拶しに行ってしかるべきだろう。偲ぶ会のようなものが、宅先生のマンションで開かれるときいて、顔を出しに行った。宅先生は、レッスンの時、ぼくの演奏を非難もしなければ誉めもしなかった。そんなことはレッスンを受けている時はどうでもよかったのであった。その会合に参加した愛弟子の一人から、南君は時間をかければ良いピアニストになるよ、と宅先生が言っていたと言う話をきいた。眼球が落っこちそうになるぐらい涙がでてきて止まらなくなった。滝のように涙がでた。その一言が、間接的ではあるが、どんなに今までぼくを支えてきたことか。いまでも机の前に先生の写真を飾っている。誰が撮った写真かわからない。笑顔の、薄いサングラスをかけた宅先生が微笑んでいる写真で、後ろに、よく伴奏してくれたオルガンのレバーがうっすらと映っている。もう、20年以上前の話である。
某月某日
NHK教育いう番組で、R・ヘルフゴットというオーストラリア出身の天才ピアニストに関する番組を見た。何やら愛は病を癒すとかなんとかお決まりのタイトルがついていたが、画面上のヘルフゴッドの動作言動が、昔見たセロニアス・モンクのドキュメンタリーととても似ているように思えた。天才の脳みそはたぶん、一部がものすごく有能に働き、その他は子供前後で、下手すると自閉症ぎみで、そばに誰かが随時付き添って面倒を見ていないと何もできない人が多いのだろう。二人とも、音楽のジャンルは違うけれど、まったく同じ立ち振るまいと動向をしているようにぼくには見え、うらやましくもあり、複雑な心境でもあった。金の事も、諸事雑事にも気を取られず、ずっとピアノだけ弾いていて、まあ才能があるのだからまわりは放っとかないのだろうが、それにしても飢え死にもせずああやって活動をして、ある意味幸せそうにも見える。天才でないぼくが見ると、ああなってみたいなあと思いう強い願望の反面、自分で稼いだお小遣いで好きなものを買ったり酒を飲んだり、まったく意味のないクダラナイ遊びに耽ったりすることができる自分が、負け惜しみでなく、やはり捨てがたい自分の流儀であるとも思える。まあ、この二人と自分をくらべること自体、ノンセンスの極地であるが、彼らができないことを、微々たる事でも自分がやってみたいなあと思っているのだから致し方ない。とにかく、モンクのピアノ同様、ヘルフゴット氏の演奏にも、眼球が眼鏡を吹き飛ばし、3メートルぐらいぼよよ~んとなるぐらい興奮した。たまにはテレビを見るのも良いものである。
某月某日
クアトロでの演奏を終わり、しばらく演奏の仕事なし。かといって変な形で、しかも妙に毎日が忙しく、じっとしている暇はない。本当に何もやることがない状態ということがあり得るのだろうか。二日酔いで寝ている状態がそれに近いかもしれない。しかし水を飲んだりトイレに行ったりするので、やはり死んだ状態が、何もしていない、やろうにもやれない、動こうにも動けないということなのであろう。死のことに関しては、実はある時期頭がねじ切れるぐらい深く考え、悩み、抑鬱状態になったりした。いくつか読んだ哲学の本も、その著者自体が自殺したり狂い死んだしているのだから、お手上げである。新渡戸稲造著「武士道」はとても気に入った。切腹の事を書いた部分が面白かった。自殺がいけないことと考えられるようになったのは、明治以後のキリスト教の影響が強いのではないか。それまで侍は、自己に恥じる部分があれば、誰にも強制されること無く、自ら進んで腹を切った。これを自死と言う言葉に置き換えると、何となく自殺と言う言葉との違いとニュアンスが浮き彫りになる。一神教の無い国であるので、他国との死に対する概念もおのずと違うものであろうし、時代や文化によっても受け入れられる様は異なろう。まあ、いずれにしても、死ぬまで生きるということには変わりない。脳内にはどこか、今日中に必ず死ぬんじゃないかとか、明日には必ず死ぬんじゃないかといった、何の根拠もないが、しかし根源的な生の部分の恐怖心をぼんやりと忘れさせてくれる器官があるような気がする。そうでなければ日々身がもたぬ。それで、え~話が戻りますが、そうで無いと、明日死ぬのではとばかり考えていたら、将来の為になるような仕事や雑用は意味を無くし、高級和服を見に纏う旦那となりて、銀座の高級寿司やで思いっきり冷えた辛口の樽酒と雲丹や時価のさしみを破産するまで食べつくしてしまいそうだ。まあ、ある意味ケチな発想ではあるなあ。しかし大体人間なんてこんなもんじゃないだろうか。
某月某日
、と書いても、クアトロでの演奏は昨夜の出来事であり、あまり某日などと書いても神秘性はかもしだせない。良いピアノに良いエンジニア、良い共演者に良い客に囲まれて、時間オーヴァ-で演奏してしまったのだった。腕を組んで足下に視線を落としぐっとこらえて聴いている客や、ゆらゆらキャンドルライトのテーブルに座っているカップルなどに演奏し慣れていたぼくは、オールスタンディングというシチュエーションに、どう対処したものかと最初少し戸惑ったけれども、立ち見というのは、言ってみれば、自分が一番聴きたい場所に曲の演奏中ですら、自らの体を動かすことが可能な状態なので、何もこっちが心配することはあるまいと思い立ち、いつもどうり演奏したら、お客の集中力がグアーッとこちらに盛り上がってきたので、普段出さぬ技なども惜し気もなく披露し、演奏は好評だったようだ。楽屋で、次回作のピアノトリオの事で、菊地氏と少し話す。今回は前回の「CELESTIAL INSIDE」のように、曲によって彼のプロデュースした物をはさむのではなく、全面的100%菊地氏プロデュースによる作品となる。共演は、今を時めくオラシオ・エルネグロ・フェルナンデス(ds)カルリートス・デル・プエルト(B)等によるもので、もう録音は済んでいる。しかし菊地氏のクルクルと回転するすばしっこい頭脳には、この録音をもっと壮大なものにする計画があったのだった。このトリオにストリングスなどをかぶせると言うのが、その野望である。しかもハリウッドのスタジオ・ミュージシャンを使うというおまけつきだ。同時に、年末に発売予定だったぼくのトリオのCDが、来年春以降の発売となるということでもある。もうこちらの演奏は済んでいるので、後はeweの方々、菊地氏などにまかせて、様子を見るつもり。菊地氏自身のアルバムにも参加することになっており、この一年ひじょう有意義なものとなってきたような気がする。なんてね、気を抜いてると足すくわれるのが世の常だから、期待を胸に、しばらくじっとしていることとする。
某月某日
デンマーク人達が、今日帰国した。突風のようにやってきて、これまた突風のように去っていった。それほど今回のツアーの行程は長くもあり短くもあり、暇でもあり忙しくもありで、何だかわけのわからないものとなった。しかし、彼らは彼らなりに、東京に一週間の滞在中、彼らの感性が東京の街が持っている何かを感知したはずであり、ぼくはぼくで、彼らのアンサンブル能力の高さ、音楽自体の持つ厚みと奥行きを、改めて確認することができた。なんて書き出しはかっこいいのだが、そういう有意義な時間は瞬間的なものであり、残り時間の大多数は、一緒にゴクゴクとビールをかっ喰らっていたというところが事実である。さあ、明日10/16からは、EWE主催、BODY ERECTRICのコンサートが控えている。気分一新、渋谷クアトロの演奏順は、GO THERE, GOTH TRAD, TOKYO ZAWINUL BACH,VINCENT ATOMICSである。19:00開演。このオーダーだと、我々がまず、ツカミはOKとし、客をこちらに引きつけ、ステージをあたためるという意味においても、大役である。明日の演奏寸前まで何をやるか決めないということにしようと思っている。客筋を見てから曲を決めるということ。色々と楽しいことが起これば良いなあと今からやる気満々である。
某月某日
昨夜、デンマーク大使館で演奏し、後に、デンマーク人の好きな寿司屋にくり出して、飲むは騒ぐはの爆裂状態となり、あまりのものすごいビールの消費量に、店側もびっくりするやら嬉しいやらで、少なくとも彼らの胃袋は、日本の不景気に大いに貢献したことだけは間違いなし。翌日、EWE企画の映画「10ミニッツ・オールダー」イメージ・アルバム製作にデンマーク勢のキャスパー・トランバーグ(TR)トーステン・ホーク(AS)マース・ヒューネ(TR)を麻布のさるスタジオにつれてゆく。 菊地成孔氏、作曲アレンジ、テナー&アルトサックス、ハモンド B-3、セレスタ、 CD-J)大友良英氏(エレクトリック&アコースティック・ギター)菊地雅晃(エレクトリック&アコースティック・ベース、エレクトロニクス)藤井信雄(ドラム)南博(ピアノ)の面々が演奏したものの上に上記のデンマーク勢が、音をかぶせるという趣向。出来栄えとしては、ほんとに無茶苦茶so coolで、菊地氏はスタジオのブースでにたにた笑ってる。ぼくが聴いても、各々の音のクオリティーが、絶妙なるハーモニーを生み出し、ソロとなると、各自が菊地氏が編曲した音の上で、これまた絶妙なるソロをとった。なぜヨーロッパの演奏家の音は、ドドメ色の浪花節にならないのだろうと思わず菊地氏に話しかけると、それは彼らがヨーロッパ人だからでしょう、という簡潔な答えが返ってきて、まそうだわな、いずれにせよ、ぼくはこのデンマークのバンドの一員でいられることがひじょうに嬉しいことには変わり無い。この映画のイメージアルバムは、「10ミニッツ・オールダー」と「人生のメビウス」二本のオムニバス映画のイメージアルバムとして、EWEから12月発売予定である。映画と共に楽しんでいただければ本望です。
某月某日
ずいぶん前の日記に書いたことと思うが、だいたい海外から秋のコンサートを準備する場合、だいたい3月ごろから行動を起こさねばならない。しか四に入ってから皆さんご存じのとおり、イラク戦争、SARS等どちらもどういう形でいつまでに終焉の日を迎えるやも知れず、テロやわけのわからない伝染病に我がデンマーク人の仲間を、危険な状況に近付けないため、今年は彼らとのツアーは一旦休憩ということにするはずだった。しかし今回は先方からら東京の仕事を振られたので、リーダーのキャスパーはデンマーク、主催者側のデザイン会社は日本にいるデンマーク人、というパーティー形式の仕事が飛び込んできた。その影で楽器調達その他采配を振るわざるを得なくなったのがこの俺。このデンマークパーティーギグに関しての詳しい情報のやり取りが、e-mailにより各自にサーキュレートされるという、今まで以上に複雑な作業に着手しなければならぬはめとなってしまった。あれよあれよという間に時は過ぎ、大切ないくつかの事項を決められない段階で、デンマーク勢6人が成田にやってきた。半分はホテル、半分は我が家に滞在という、最初にイメージしたリッチなバジェットの元に行われる企画ものではないことがだんだん露見してくる。彼らと共に、来日したその日の夜にデンマーク大使館にて演奏。デザイン業界の方々、在日デンマーク人のお偉方に向かって大使館の中庭で演奏す。皆を興奮のるつぼにお誘いしたのはいうまでもない。2年前東京で録音した「KASPER TRANBERG MORTIMER HOUSE」http://www.ewe.co.jp/artists/detail.php?id=32の内容を、更に一新するサウンドと曲が揃っていた。デンマーク大使も演奏をひじょうに気に入って下さり、一緒に写真まで撮ってしまった。これから体育の日まで、彼らの面倒を見るのである。自分でオーガナイズしたツアーでない分、戸惑うこと多し。しかし、これからの活動において、最重要人物達に演奏を披露できたことは、将来決して無駄にはならないであろう。文化そのものと、音楽そのものを愛することを知る人々である
某月某日
前回に書いたデンマーク勢の襲来に加え、菊地成孔氏とのヴェルトリッチ、ゴダ-ルなどの映画に対するイメージアルバムの仕事がからんできた。これにも、ちょうど良い機会なのでデンマーク勢もぶち込んで何かするつもり。これはスタジオでの密室状態の演奏で、他のデンマーク勢の演奏も、デンマーク大使館内でのコンサートなど、一般の人が入れないこれまた密室状態の演奏状況となり、今回はあまり一般の方々には演奏を披露できないのが現状である。すみません。なにしろ今回のスポンサーがデンマークのデザイン会社で、僕自身がツアーを組んでいるわけではないので。しかし、前記のイメージアルバムには、EWEもかかわっているので、将来的に何か発展があると見て間違いはない。とにかく前に書いたように雑用がおてんこ盛りの状態で、しかも来週末は横浜ジャズプロムナードなどもあり、休む暇なし。(デンマーク側は総勢6人、二人我が家に逗留し、他はホテルに滞在。)デンマーク人にかぎらず、友人の普段気付かなかった、自分には当たり前な日本の諸事情、事柄に対しての、彼らなりの鋭い指摘などあり、良い意味で神経が刺激を受け、同居することはまんざらやぶさかでない。脳内の大掃除を彼らと共にするつもり。まだ決定せぬ案件など有り焦る心持ちではあるが、彼らの来日が待ち遠しいことに変わりはない。どうなることやら。
某月某日
突然デンマークから大勢の仲間が来日することとなり、雑事がおてんこ盛りとなってしまった。今回は僕の仕切りで呼んだわけではなく、さるデンマークのデザイン会社のイヴェントのための来日ということである。しかし、日本で演奏する楽器等のレンタル及びその運搬は、自然と僕の役回りとなり、自分で企画してないからこその齟齬がいたるところに生じ、海を越えてのe-mailで、キャスパーとああでもないこうでもないと、お互い第二外国語の英語をあやつって、何とかこの仕事のスムーズなる流れをつくり出すのに、いま四苦八苦している状態。何をかくそう、僕はデンマーク人によるセプテットのただ一人の日本人ピアニストである。興味のある方は、このWEBのCD欄をご覧あれ。このバンド結成以後、毎年デンマークのセプテットを日本に呼ぶことを自分の内なる課題としてきた。この日記の読者も御存じのとおり、2002年10月に、EWEから「MORTIMER HOUSE」EWCD0047 ewe recordsを発売している。しかし、今年前半、何やら不穏な空気が世界をおおっていた。SARS、イラク戦争、だいたい秋口のツアーは、3月頃から行動を起こさないと、形に成らない。その時期に、何時終わるやも知れぬ疫病とテロに、我がデンマークの友を巻き込んではならないと判断し、今年はツアーなど計画せず、おとなしく秋口には栗でも食っていようかと思っていた矢先の、先方からの急なオファーである。イラクの戦争は、内紛を抜かせば、まあ気にしなくても良いかという状態で、SARSも、今のところおさまっている。こんなことなら、最初から、件のデザイン会社と結託してもっと大きな何かができたのになあとお思う反面、彼らが来日するまでの準備に追われる僕自身、やはり何と言えば良いか、今年も栗なんか食って京番茶すすってる暇じゃないよと言うどこからかのお達しなのであろう。実際演奏のメインがデザイン会社のパーティーの仕事であるので、過去通常演奏してきたし新宿ピットイン等などでは演奏しません。デンマーク大使館の庭とか、そういった内輪の仕事ばかりですが、なんとか一度だけでも、ふつうの日本人にこのサウンドを聞かせたく思い、期間ギリギリまで奮闘中といったところです。何か新しい動きがあれば、DM等でお知らせを出します。また、この日記を呼んで興味を持った方は、是非こちらにメールを下さい。詳しい情報を届けます。ツアー中何日か空いている日があるので、急遽どこかでゲリラ的に演奏するかもしれないなんとも微妙な状況です。まだKASPER TRANBERG SEPTET(KASPER TRANBERG :CORNETJAKOB DINESEN :TENORSAXOPHONE MADS HYHNE :TROMBONEHIROSHI MINAMI :PIANO NILS DAVIDSEN :BASSANDERS MOGENSEN :DDRUMS)を聴いたことの無い方、これはもう、言ってみれば我々の北欧というプレコンセプションを根底からぶっ壊すようなバンドなのです。北欧と言えばECMですが、もちろんこの手のサウンドも踏襲し、そこにえも言われぬモダンな音楽に対するアプローチと、日本人の感覚では得られない空間の扱いのうまさ。ロック的なフィーリング。しかし全体的には非常にアコウスティックなアンサンブルで聞き手を圧倒する。こんなバンドなんです。今回、一部かぎられた場所でしか演奏できないのが大変残念ですが、いずれまた、皆様の前に、彼らの音楽を表現する機会が訪れると思います。いずれにせよ、この日記の欄と、NEWSの欄、お時間のある時にチェックしてみて下さい。デンマーク大使館以外の仕事も、彼らの滞在中あるやもしれません。