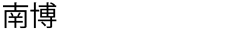某月某日
散歩と読書がわが脳みそをかろうじて惑星直列的大惨事から守ってくれている。情ない話であるが、この二つの人生のアイテムは、ほかの暇つぶし、趣味に比べ安価である。良書は精神の地図と言え、千円で釣りがくる。しかも、生きているうちに、世界の良書をすべて読破する事は不可能だ。ということで、飽きもこない。東京という場所は、店鋪のみならず、その土地にあるビルごとある日消えて無くなるので、ある意味散歩も飽きがこない。ひいきの店が突然消滅することはショックではあるが。地震、天災、空襲もないのに、建物がこつ然と消えて無くなるのは、なにやらこっけいだ。手品をみている感じである。同じ道筋を散歩していると、そういった空き地がポツポツと目につき、しかも驚くほど早く新しい建物ができあがる。景観もへったくれもあったものではない。新しいビルを眺めながら、ハーと最上階を見上げ、また歩き出す。本日も音楽ネタなしの味もそっけもない日記となってしまった。仕事がないんだからしかたがない。
某月某日
音楽とはあまり関係のない日記をだらだらと書いてきたので、3月に入ってから、我が音楽生活を真面目に書き記す文章をと考えてはいたが、なにしろこの月は、稀にみる演奏の回数が少ない月となり、今年後半に準備しているツアーやその他の雑事は通常どおりこなしているものの、演奏に附随する花々しいレポートなど書けない状態である。この回の日記も、前回に続き下らぬ挿話に終止しそうであるから、我ながらナサケナシ。いくら雑用その他があるとはいっても、日がな一日家に籠っていると、自ら鬱な気分を発酵醸造していることとなるので、夕方近くになると、強制的に小銭を持っておもてに出る。何やら風強く、薄ら寒く、目的も無くおもてに出た我が身を、ぴーぷーと風があおる。ボストン時代のマイナス20度に耐えたこの顔面、と思いつつふらふらと街を散策。禁治産者である。寒いので、自然脳内は暖かい快楽を求む。妙なレジャー施設や、お台場にできた大温泉ビルに比する快楽が我が住まいから徒歩30分のところにある。その名も○×△湯。都内も深く掘り下げれば温泉が出るらしい。温泉の事は詳しくはないけれども、サウナ、露天風呂完備で、帰り道はタクシー基本料金の距離でもある。行きは徒歩、帰りは湯冷め防止の意味でタクシーで帰るとして、まずは番台に料金を払う。タオルその他はすべて完備した場所だ。ロッカーにて眼鏡をはずすので、湯煙の幽玄な空間が、輪をかけてぼんやりして見え、まことに好都合。他人のあそこをがちょんともろに見るにがにがしさを味わわずともすむというメリットまである。体を洗ったのち、湯舟にて体をあたため、サウナ、露天風呂、湯舟という順番でもうろうとしてくるまでこれら巡回し、髪をかわかした後、下のフロアーにてビールを呑んでタクシーをつかまえる。せこいんだけど、なにげに王様気分で帰宅。冷蔵庫の食材で簡単な料理。本日はふろふき大根とシシャモ。自前の味噌だれを大根に塗りながら一日の後半を終了。こんなことしていて良いんだか悪いんだか。
某月某日
ぼくの数少ないファンの方からときどきメールが来る。嬉しい限りだ。その中でいちばん多い質問は、最近の愛聴盤はなにかというものだ。これはかなり答えるに難しい質問で、一挙一投足には回答できない。最近は、そのいわゆる愛聴盤として、音楽自体を聞けなくなってきているというのも、即答できないひとつの理由となってしまった。新しい、しかも興味深い新譜を買って聞く場合、ぼくの耳はどうしても分析的になってしまい、なあるほど、こんなことやッてらあ、すげエ、こんな技もあったのか、こんないい音でとれるスタジオとそのエンジニアはいったいどういう人なのだろう、等々、つまり、音楽自体をリラックスして聞くことができない。悲しい習性である。まだジャズを聞きはじめて日の浅い頃の、わくわくとして、聞きはじめたら心がドカ~ンと破裂しそうな、あの心の動きは近来あまり感じない。これは新しいCDを聞く時のみならず、音楽を聞く機会ごとに感じる最近の正直な感想だ。ということで、愛聴盤というものは、最近さらに特定できなくなってしまった。しかし、強いていえば、毎回聞いていて飽きのこないものがひとつある。それはCDではなく、ラジオ番組なのだった。その名もNHKラジオの「ラジオ深夜便」だ。夜中に譜面を書いたり、作業をしている時、この番組が、もっともぼくの脳内を静かな状態にしてくれる。こんなことを書くと、もうこの俺も、どこかの田舎の隠居おじいさんみたいだが、事実なのでしかたがない。バイリンガルの女の子が、威勢よくしゃべるほかのFM番組も、料理をつくっている間など聞くことはあるが、黙々と単純作業をくり返さなければならない深夜などは、やはりラジオ深夜便にかぎる。その単純作業中に、刺激的なCDなど聞いてしまうと、耳と神経がそちらに吸い寄せられてしまい、いかに単純な作業とは言え、仕事そのものに集中できなくなってしまうのだ。ラジオ深夜便は、ああ、まだこの国はなんとか、クレージーな人間ばかりで構成されているわけではないんだなと安心させてくれるという、別の安堵感もぼくにもたらしてくれる。「リクエストの時間がやってまいりました。本日のお葉書は、○○県××郡字△村にお住まいの、農業、×山◇太郎さんからのお便りです。寒くなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。本日は妻の誕生日です。結婚前、二人でよく行ったダンスホールでの日々を思い出したく、タンゴの名曲、ラ・クンパルシータをお願いします。妻と二人で楽しく番組を聞いております。」てなぐあいだ。平成の世に昭和の息吹が深夜に流れていると、子供のころ、少し夜更しを許された日々を思い出した気分になれる。たぶんこれは精神的退行なのだろうけれど、精神的安寧にはもってこいの番組ではある。
某月某日
前々回の日記にて、蕎麦屋のことを話題にしたら、各方面から大絶賛を受け、(うそです)なるほど、食い物の話題ならば、反応があるのだなと学んで、またここに食の話題について書くことにする。ミュージシャンのくせに、音楽のことに触れない日記など書くべきでないかもしれない。いずれにせよ、音楽のことは次回にゆずるとする。ディテールが面白ければ、この日記のコンセプトとは相反さない。食についていえば、今回の新しいCD「CELESTIAL INSIDE」に三曲の楽曲を提供した菊地成孔氏には、及びもつかない。いつだったか何年か前、デンマークで演奏するついでに、ちょうどその時期パリで演奏する仕事があった菊地氏をたずねたことがある。彼は毎晩のように、ぼくを、調べつくし選びつくした、そして値段も妥当なレストランにつれていってくれた。見も知らぬ料理が眼前を通り過ぎ、見事なる注文の順序によって、はたはた感心するヴァランスのよさで、毎回の食事を堪能できた。残念ながら、それらのメニューの名称、成り立ち、レストランの名前、それらはすべて記憶にない。これは本当の食いしん坊でない査証である。パリのはずれにあるヴェトナム料理屋にも、同じ時演奏の仕事でパリに来ていた水谷氏と食いにいった。これも水谷情報がもとで、僕はついていっただけである。実をいえば、91’年の冬から夏近く、6ヵ月にわたり、ぼくはパリを放浪していたことがある。事情を書くと長く成るので割愛するが、その当時、住んでいたアパートには同居人もいたりして、(この件の詳しいことは原稿料が発生するところでも書けない)毎日色々な事情でにっちもさっちもいかなくて、金もなくて、寒くて、フランス語もほとんど分からなくて、住んでいた部屋の窓はワレテいて、暖房器具がぶっ壊れてて、という、住環境へレンケラー状態であったから、レストランに行くなんて、とてもじゃないがそう頻繁にはできなかった。だから、パリの道筋には、記憶と経験で探りを入れることができたけれども、その道筋にあるレストランの扉をあけるには、我が同胞の助けが必要だったというわけだ。91’年パリ彷徨生活の食生活は、なんだかわけが分からない。まず朝はクロワッサン二個。あと小ぶりのどんぶりみたいな容器にカフェオレ。昼は食わぬ。夜はといえば、角の安カフェで安ワインをガブと飲み、胃をごまかしてからアパートに帰り、パテとフランスパン。パテとは、鴨かなんかのペーストで、そこいらの食料品やで安く売っているもの。外側にゼリーみたいのがかぶさっていて、これをあの長いフランスパンにぬったくって食らいつくと、その場の飢えはおさまってくる。まあ、同居人に、日本食をつくってやるとわけの分からぬことを言って金をふんだくり、パリにあるチャイナタウンにもよく行った。日本食などつくれるはずもない。材料があっても器具がない。向こうの人にとっちゃア日本も中国も区別はねエだろうてえんで、ずいぶんインチキなものをつくっちゃ食わせた。こっちは醤油の味さえすればよかったんだから。チャイナタウンに行くと、なぜだか、タイやヴェトナムに輸出されたであろう出前一丁など売っている。文字があのクルクルピョコンだから東南アジア用とわかった。胡麻ダレもちゃんと付いていた。これを大量に買込んで、オイスターソース、鶏ガラだし、醤油にてあらゆる種類の野菜を混ぜてバッと火にかけて、金の余裕のある時はちょっと肉などのっけて、はいようパーコー麺などと嘘八百ついて、同居人に食わせていた。もちろん俺も食った。窓の外は、フランス風アパートの並みいる甍と、その屋根から無数にはえてる煙突と煙り。夜なのになぜか薄明るい空に、なんだか妙に低い位置にある大きな雲が、カゼに乗ってあらぬ方向からあらぬ方向へと流れていて、その景色をみながら食する、タイ仕様の出前一丁は、ミスマッチな味だった。同居人はうまく騙されてくれて、「ボン、ボン」言いながら食っていた。パリに行ったのには理由があって、まあ、理由って言ったって、ぼくは哲学者ではないから、誰かにツッコミを入れられたら、さしたる根拠も開陳できない。ひとつ言えることは、ぼくはパリに住んでやろうと思っていたのだった。無謀である。フランス語なんか分からないのに、フランス人の友達が数人アメリカでできたから行ってしまった。ぼくの脳みその中には、この衝動に加えて、ヘンリー・ミラーの「北回帰線」「南回帰線」、数々のフランス映画、エディット・ピアフの歌、その他諸々の憧れがごちゃごちゃしていて、英語さえ分かればなんとかなるジャンなんて思っていたのだった。真性のバカである。実際、行ってみたら、誰も英語を喋ろうとせん。ヘンリー・ミラーを筆頭に、ぼくの知っているパリのことを、パリに住んでいるフランス人はあまり知らない。いま考えると当たり前だけどね。ぼくだって毎日東京タワーには登らないんだから。まあ、そういった理由に加えて、パリに到着してその直後、なんだか湾岸戦争がはじまりやがって、パリの街も暗い雰囲気になってしまった。ある日、小銭を持って今日は久々に外食だ、なんて街を歩いていたら人っ子一人おもてに居ないなんてこともあった。後で事情を聞くと、テレビニュースで外出は控えるようにと言っていたのだそうだ。劇場、メインのメトロの駅、デパートなどに、テロリストが爆弾をしかけたという情報が当局に入ったからだそうな。フランス語の分からない真性バカのぼくは、さすがパリの夜景は絶賛に値する。金がなくとも環境からえられる文化は値千金、なんて気分で人気の居ない路地をうろうろしていたんだから。まあ、それで、メインの華やかなところは歩くんだけど、懐具合を考えると、だんだん場末まで寒い冬のパリをとぼとぼ歩いて、変にチンケなカフェなんだかレストランだか分からないような店に入るわけだ。店の前の看板の文字は読めないけど、数字は分かるから値段は察しがつく。そういう店にかぎって白人のフランス人はあまり居ない。皆ヒゲ濃い系のアラブ、アルジェリア系の人々で、まあ、それなりに親切な人達だったからいいんだけど、安いメニューの王様は、クスクスという、とうもろこしの粉を蒸してツブツブにした、地中海沿岸地域の主食と、なんだか酸っぱいサラダが定番。安くてうまくて、凍えた体にふ~っと栄養が行き渡るあの瞬間がたまらなかった。クスクスはあまり味付けがされていない。横に添えてあるサラだの酸味をまぜて、卓上の塩、コショウでいただく。まあこんなのは、グルメもへったくれもない。一般のフランス人はこないような店である。やたらエネルギーを持て余したのっぽのアラブ系青年が、店の中にあるピンボールをだんだんと叩きなながら真剣に遊んでおったり、カウンターの奥のオーナーであろう乃木将軍みたいなヒゲをはやした首の太い親父は、店の天井の角を、視線の定まらない漆黒のメンタマでボッと見ているような空間。他のテーブル席には、ぼく以外にもうひとりぐらいしか客が居なくて、それが、すっぽりと中東風ネッカチーフを頭から首まで巻き付けた、異様に目が大きくてきれいなアルジェリアかどこかの美人だったりする。どう注文したのか、ぼくとは違うまそうなものを食べていたりする。それはナンだと問うてみると、フランス語も分からないのに、なんだか、アルジェリア語でナンチャラという料理の名を言った。ふ~ん、値段も安いし、おっし、オーダー追加して太っ腹ジャポネになってやろうって勢いで、同じものを追加注文しようとしたが、あの時はたしかやめた。食後の酒代しかなかったから。ふだんクロワッサンとパテと出前一丁の毎日に比べ、ぼくの中では、このアルジェリア系レストランでのものが、星三つなのだった。まあ、月一回ぐらいだったけどね。後年、日本に帰ってきてみたら、何やら高級なパン屋が増えており、クロワッサンなども簡単に手に入るようになった。しかし、毎朝寒い冬のパリの路上を、てくてく歩いて買いに行ったあのクロワッサンと同じ味に、まだ出会えないでいる。戦争前夜の状況とか、沈んだパリの街並も、相乗効果があったのだろうけれど、それにしても、あのクロワッサンのしっぽのところのカリッとした食感が、日本にはないような気がするんだがなあ。あの味、もう一度味わいたい。バターの香りがほんのりとするのだが、べとついた感じはしない。あの朝の食感、もういちどシルヴプレ。
某月某日
TOWER RECORDがつくっているMUSEEという雑誌において、僕のインタヴューを載せることとなった。インタヴューも、その聞く側によって、こちらの主張が同じでも、記事自体は変化するものだ。今までにも、様々な人に、様々な国と場所で、あらゆる状況を含め、インタヴューを受けてきた。その際たるものは、91’年、日本でグリーンカードを取得するべくアメリカ大使館でのインタヴューであろう。グリーンカードは抽選で当たった。当たったのだから、当たった日から市役所などに出向きさえすれば、あのパウチッコ作りのカードが、その場で即給付されると思っていた。当たった当初は舞い上がり、当時住んでいたボストンのワル仲間と飲めや歌えの「青い招待状」取得ばんざいパーティーなどやらかした。カード取得に様々な技を駆使してくれた、移民専門の弁護士の送ってきた注意事項を読んでるやつなど、その場には一人もいないで、後日よくよく見ると、永住権を得るには、かなり面倒な手続きが必要である事がだんだん分かってくるというテイタラク。条件の中には、アメリカ大使館でのインタヴューが含まれていた。一旦日本に帰り、指定された病院にての身体検査を受ける。健康診断の後が、本命のアメリカ大使館でのインタヴューという事である。このインタヴューは、ライターの人がアーティストなどに行うものと内容は大違い。要するに、「面接」という日本語を当てはめた方が分かりやすいかもしれない。健康診断をパスして行ったアメリカ大使館、この「面接」の事は一生忘れないだろう。その当時の僕は、日本に帰る気などさらさら無く、なんとかアメリカに永住してやろうという思っていた。その面接は、アメリカ大使館内の窓口にておこなわれた。「アメリカが好きか?」「アメリカの音楽芸術を尊敬していて、それで長期滞在望むのだな。」「あなたの友人、両親、または親戚、それらの中に、過去におけるナチ、およびネオナチの活動に参加し、また、サボタージュ、スパイ、人種差別等の行動を計画、実行したものはいるか」などが主な質問だったような記憶がある。特に最後の質問は、アメリカに入国の際、飛行機の機内で配られるカードの裏に書いてあることと、大使館での質問内容を、混同しているかもしれない。グリーンカードの申請をしたのは、たしか92’年頃だったので記憶が曖昧だ。しかし、やはり同じようなことを聞かれたような気がしないでもない。親戚にナチがいないのかという質問だが、例えばぼくの親父が、ゲシュタポの将校の格好をして、新宿の呑み屋で、ナチ風の長めのブーツを、横の空いた席にひっかけて、「すんません、ヒレ酒熱いのもういっぱい」という図を瞬間的に想像できない。もしそのような場にぼくが居合わせたとしたら、ああ、もう南家はお終いだ、とその場で気絶するだろう。いずれにせよ、このインタヴューは、ぼくの人生の中でも、最も緊張する瞬間であったことには変わりない。最近受けたインタヴューで、身体的にも肉体的にも極度に緊張してしまったのは、去年の冬、デンマーク各地を我がGO THEREのメンバー、そしてピアニストの板橋文夫氏とツアーした時に受けたものである。コペンハーゲン到着後、その日の夜、ジャズのラジオ番組に、板橋氏とぼくという二人のピアニストだけでゲスト出演してほしいと、このツアーを組んでくれたデンマークジャズ協会の人にお願いされた。ジャズ協会が作成し、わざわざ日本まで送ってきてくれた綿密なスケジュールには、件のラジオ番組出演という欄はない。急遽決まったのであろう。到着直後のぼくの気分としては、まず着替えてシャワーを浴びて、ホテルの一回にあるバーカウンターでビールでもかっ食らって、時差ぼけを吹き飛ばしたかったところだが、かの地においては、まな板の鯉になるしかない。板橋氏と共に、目をしばしばさせながら、ホテルから車で15分ほどの放送局へ送り込まれた。建物の中には入った途端に、グオアーという感じで眠気が襲ってきた。第一次jet lag奇襲攻撃のはじまりだ。番組を収録するスタジオ内が、程よく暖気されていたというのも裏目に出た。ホテルのロビーで、慌ただしく荷物をほどいてフロントに預け、すぐさま放送局へ行く体制を整えている時、皆のすきをついて、ビールを盗み飲みしてしまっていたのだった。スタジオの暖気と、時差ぼけの疲れた体に染み渡るビールによって、急に脳みそ自体がモツ鍋になったような眠気である。かろうじて、この小さい細長の目を真ん丸くして、笑顔をつくり、番組のDJの人と挨拶。生番組らしく、間抜けな解答、質問の後に生じる音無の空間、これらをしない、つくらない状態で、心身共にシャープでなければならない。しかし、実際のこのぼくときたら、机に突っ伏して寝てしまいそう寸前という状態であった。番組がはじまり、まず板橋氏、HIRIOSHI MINAMI GO THEREの新譜が番組のオープニングとして使われた。DJ氏は、たくみにデンマーク語と英語を使い分け、デンマーク語の時はリスナーに向かって、英語の時は、我々に向かってと、さすがにプロの采配。こちらに対する質問も、ひじょうに洗練された、しかもリスナーという第三者が電波の向こうで聞いているという状況を包括した、見事なもので、こちらとしても、質問内容はもちろんの事、リスナーに対しても、呼び掛けになるべく答えなけれればならなくなった。しかし、その時まさに、そして最悪なことに、その時のぼくの「時差ぼけ」は、「爺さんぼけ」に近い状態になっており、とにかくDJから発せられる質問に、間をあけずに対応するのが精一杯。加えて、こういう場所で英語を喋るのは何年ぶりかといったおまけまでついて、さらに、先輩である板橋氏の言ったことを補足しなければならないのだった。まあ、リスナーの方としても、御苦労さんにも極東からわざわざデンマークまで来て番組に出て、なんだかしんないけど一生懸命しゃべっている日本から来たミュージシャンがいらあ、ぐらいに思ってくれれば、オンの字だった。国文学者で、イギリスに関してのエッセーなどを書いていらっしゃる林望氏は、インタヴューの極意というものは、寡黙でいることだとなにかの対談で言っておられた。ぼくの場合、爺さんぼけが高じて寡黙にならざるをえなかった。意図的に寡黙になるのと、寡黙にならざるをえないということ、この二つのコンテクストは表裏一体ではあるが、意味合いは全然異なる。ゲシュタポの格好をした親父が頭の中に出現したり、、お互い第二外国語で、しかも間を空けてはいけない生放送で、雄弁になれというのが、ぼくには土台無理な話なのだった。ぼくのインタヴューが載る次回MUSEEは、3月末入稿予定である。ここでのぼくは、はたして寡黙であったか、寡黙にならざるをえなかったのか、それは記事を見てのお楽しみということにしよう。