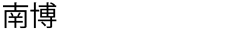某月某日
ものすごく暑い日々が続いている。子供の頃に過ごした夏の日々の中には、これも日によってだがどこか清涼とした空気と雰囲気があったような気がする。最近の夏にはそれをあまり感じなくなったのは気のせいだろうか。実際気温も年々少しずつ上がっているような気がする。これも気のせいだろうか。いくら知力があり、人間として完成されていても、天候に関して、自然の力に向かって行くには、ただただ体力がものをいうということだろうか。何か特別な技能、知恵をもっていても、暑さでからだが動かなかったら何もできない。先週のレコーディングに続いて、今週はこの暑さの中を毎日色々なところへ行って演奏した。レコーディングでの疲れを少し体に残したまま炎天下を歩き回り昼は打ち合わせにリハーサル、夜は演奏という日々を過ごした。昨夜は小岩のKOCHIという店で井上淑彦とデュオ。めったに行かないダウンタウンサイドの東京。いい感じの商店街が駅前に開けていて、お茶やさんや、精肉店、メロンソーダとかまだでてきそうな喫茶店などが軒を列ねている。元々こういう風景の中で生まれ育ってきたのではなかったかという感慨が沸き起った。現代はすぐにこういう商店街を駅ビルなどに改築してしまい、どこへ行ってもなんだか全て同じに見えてしまうようになって、何となく寂しい感じがする。そんな横丁の一角にKOCHIはあり、何だか地方のクラブにツアーで来ているような錯覚におそわれた。カウンターに座ると体がすっぽりとその場所におさまった。つまり居心地が良かった。こういう場所が近所にあったら即ボトルを入れてしまうだろうなあ。マスターのM氏も程よくそして押し付けがましくなく、はじめてその店を訪れた僕をもてなしてくれた。お客さんの息づかいが感じられるような空間で井上氏と演奏。井上氏は僕が学生の頃からのアイドルである。サックスの音、特にソプラノの音は僕が日本でいちばん好きな音だ。その井上氏と一緒に演奏をはじめて一年半ほど経つ。通常は水谷浩章(B)田鹿雅裕(DS)を加えたクアルテットでの活動が主だが、この日の演奏は初のデュオである。光栄な上にちょっと興奮してしまった。しかも暑さで頭はある意味で柔らか~くなっていて、その柔らか~い頭の中に井上氏のサックスの音が、浸透してきた。とても気分が良かった。カウンターのお客さん達も喜んでくれた。不思議な、そして心地よい時間を過ごし小岩をあとにした。ちょっと小さな真夏の夜の夢のような夜だった。
某月某日
HIROSHI MINAMI QUARTETでのレコーディングが終了した。メンバーは御存じ、水谷浩章、芳垣安洋、竹野昌邦である。一日でほぼ全8曲の演奏のOKテイクを録音するというまれにみる快挙、加えてミキシングもスムーズに進み、発売は11月初旬となる模様。一般の僕の演奏に対するレコグニション、特に評論家達の僕に対する評価は、日本でヨーロッパ的なアプローチをするピアニストという事になっている。今回はそういう先入観を払拭するべく曲を揃え、コンセプトによってはごりごりと弾いた。もちろん美しい音で弾くというこころみは変わらないけれども。録音前の一週間は葛藤の連続だった。どこまで曲の中のリズムその他決めてかかり、どこの範疇までをミュージシャンのその場のアイデアに頼るか、その両者の程度のバランスをうまく保つのが難しいのだ。これはもうすでにアレンジされた、そして作曲された曲をいかに膨らますかという段階での話だが、実は譜面にかきようのないこのバランスこそが一般の演奏、そして今回の録音のような状況にいちばん大切なところなのだ。あまり全てを決めてしまうと、共演者のできる事を逆に殺してしまうし、逆に自由を与え過ぎると、バンドとしてのマトマリ感が薄れてしまう。またこのバランスを逆に考え過ぎてもいけない。考え過ぎる事で、自分の作曲した曲やそのメロディーに対して、演奏することへのワクワク感が薄れてしまったりする。加えて、そのレコーディングの日の我々の体調、気分、その他諸々の要因が加味され、まあある意味で、いくらきっちり決めてかかったとしても、ギャンブル性の高いことで、そのギャンブル性が高ければ高いほど、うまく行けば音楽事体が面白くなるし、うまく行かなければ全てが崩壊するといった性質をもっている。しかし、このメンバーで活動してはや4年ほどが経ち、この間あらゆる条件で演奏し、ツアーをし、何が起こってもお互いの中に揺るぎない信用が音楽を支えているという事にはかわりない。レコーディングの四日間は、梅雨明け前の稀に見る猛暑の日々で、スタジオの中に入ると、逆にエアコンがギンギンにきいており、演奏後の汗がすぐにすっと冷たくなるような条件で、一日7時間ほど演奏した。通常のクラブでの演奏の三倍強のエネルギーを午後3時頃から放出する事となる。ピアノはスタインウエイだった。本庄まなみちゃんのようにノーブルな楽器。ドレミと弾くだけで倍音が空気中に細かい金の粉を吹き上げるように舞い上がる。至福の状態。ふだん天童よしみみたいなピアノばっかり弾いているので、たまらない気分だ。今回の録音に於いて、特筆すべきはレコーディングエンジニアのH氏である。かれは前回の2枚のトリオのCDのレコーディングの際にも僕の音をとってくれた人だ。僕の抽象的しかも基本的に機械オンチから来るわけの分からない要求に、気前良く、そして迅速に答えてくれる。仕事のできるとはこういう人のしている事だなあと、かれの背中を見ながら思ってしまう。演奏が午後8時を過ぎると、腹がへってくる。店屋物の注文となり小休止する。カツ丼の上を食べた。カツ丼というのは本当にごちそうだなあと思う。カツと卵、しょうゆの味にみりん、その下に飯。スタジオいう閉塞した空間でこういった店屋物を食べるのも一興。冷たいペットボトルでお茶を飲んで録音再開。夜もふけて12時近くなり自然と終了。ミキシング、マスタリング共々順調に進み、発売は、11月9日の予定。こう御期待。
某月某日
これから来る梅雨の季節に向けて、少しばかり気合いを入れていた。この日記にも書いてきたように、ぼくの体は湿気に弱い。体のみならず気分的にもいい影響を受けない。これから一ヵ月間じくじくと過ごすにあたり、少しばかりのきばりを持ってのぞもうと思っていた。しかしこの頃は、予想に反して晴天の日が多く、なんとも拍子抜けする。しかし今日のお昼は、晴天とはいえ、何やら太陽の光線が大気に乱反射して空間がぎざぎざのものにまみれているようだった。昔の人が持っていた極楽という概念は、暑くも寒くもなく、飢えを感じる必要のない場所だったそうだ。その筋から行けば、現代の生活はこの世に居てすでに天国を実現していると言えよう。あんまり湿気だなんだぼやいているのも、昔の人にしかられそうではある。よい音楽を造らなければ。岡本太郎著「今日の芸術」によると、「美しいときれいは違う。」と書いてあった。かねがねぼくはきれいな音楽を演奏したいと考えてきたが、岡本氏に言わせると、きれいというのはつまらなくもあるそうだ。ぼくも美しい音楽をこれからめざそう。あまりにも工夫のないナマな証言である事は自分でも良く分かっている。しかし、お天気のせいで気分がぼうっとしやすい日々の中で、これぐらい自分の中にダイレクトに響く言葉を念頭に置いておかないと、自分の中心がきが付かない内にずれてしまうような気もする。
某月某日
ピアノを教えた。生徒の人数の多いときは、半日以上教える場所にこもらざるをえない。現実に戻って外に出てみると夜になっている。自炊を放棄して久しい。所詮洗濯から掃除、それらの家事と演奏作曲、それに加えてメシの煮炊きを全てまかなうことは不可能である。結果これらの人類の永遠の営みから自炊という要素が消えはてた。何だか小気味良い。ザマアミロという感じ。自分に対してそう言いたくなる。都市部に住んでいるおかげで全て深夜でも外食でまかなう。飽きる飽きない、旨い不味いでくうのでは無い。生活の流れとして食事する。美食家には憧れるが、あまり食い物に神経質になるのもかえって面倒だ。大体一人でメシを喰う時は本を読みながら食べる。だから味など良く分からない。それでちょうど良い感じ。好きな食いものは生うに、そばである。しかしあまりコダワリは無い。こだわるエネルギーと時間が面倒だ。遅い夜メシの後、最終の地下鉄に乗って青山ブックセンターへ。中島義道著「私の嫌いな10の言葉」「ウイーン愛憎」その他を購入。中島氏は今を時めく哲学者である。非常に面白い本をかくひと。疲れた時も読書に限る。鬱陶しいことを忘れるには、文面が頭に入らずとも、ただただ活字を追っていれば、よけいなことを考える脳のキャパシティは、少なくともすみの方に追いやられる。六本木の街も変わった。ぼくが大学生のころは、年令も大人と子供の合間で中途半端ということもあっただろうが、六本木は大人の場所だった。もっと落ち着いた、そして良い意味で危険な感じの場所だった。実際当時は入り口で門前払いをくわされた場所もある。この場所に受け入れられるような大人になりたいと常々思っていた。六本木界隈は今でも好きな場所ではあるが、今はあまり当時感じた危険な面白みが無いような気がする。まあしかし、かといってぼく自身、東京以外住たいと思う都市は無いのだが。思えば寂しく、そして自由な身の上である。生まれ育ちは東京で、小学校高学年の時川崎市に引っ越し、大学生活を終えてまた都内に居を移した。後アメリカに住み、また東京に帰ってきた。自分が生まれ育った世田ヶ谷の団地も、何れは取り壊しとなり、マンションなどがその跡地に建てられ、昔を思い出すものは何れは無くなってしまうであろう。今両親が住む川崎の家も、典型的東京郊外の住宅街であり、別段地域に密着した生活では無い。ぼくが実家に帰っても友人その他特に親しいものが周りに住んでいるわけでもない。世田ヶ谷の生まれ育った団地にはそこはかとない郷愁を感じるが、川崎の方には何も感じない。故郷がない。帰る場所が定かでない。ミュージシャンなので組織に属しているわけでもなく、何かに対する帰属意識は皆無。寂しいようで実はどうでもない。というかどうでも良い。家に居たってツアー中だと思えばいい。死ぬまでツアーに出ていると思えばいい。住処とはたまたま他のツアーより時間的に長くいる場所と思えばいい。へっへへへ、ざまあみろ。
某月某日
本日、横浜エアジンで自分のクアルテットにて演奏。じつは7月に竹野邦昌(SAX)芳垣安洋(DS)水谷浩章(B),このメンバーで7月にレコーディングの日が決定している。発売は前回トリオのCDを出したEWEからだ。新曲その他を模索しつつ演奏は充実したものだった。今日の結果を鑑みてまた更に新しい曲を書いてレコーディングに望む所存だ。エアジンで演奏の後、とある仕事関係の人と会って酒を飲む。色々チャンポンして酩酊した。最近酩酊するまで飲んだことが無いので、自分自身の千鳥足に戸惑いつつ、何とか住まいまでたどり着いた。自己反省と共に就寝。
某月某日
当時僕がピアノを弾いていた銀座のRという店は,その界隈でも一番料金が高く,女の子の質もダントツに高いことで有名であった。客筋もテレビ雑誌で有名な方々が毎晩のようにやって来て,かなり華やかな活気を呈していた。僕はそこで,ピカピカひかる黒塗りのグランドピアノで,カントリーアンドウエスタンからナットキングコールまで,バンマスの気が向くままくり出されるメロディーにその場で伴奏をつけ,必死の思いで生きていた。金をためて外国へ留学してやろうと内心たくらんでいた。月頭に成ると,バンマスのスーツの内ポケットからキャッシュでギャラが支払われた。給料というものは,本当の意味で我慢料だということを,その頃悟った。バイトではけっして味わえないことだった。グランドピアノの上には,大きな白い花瓶がのっており,そこには,名も知らぬ,色々な種類の花が,天井に向けて扇状にいけてあり,その花達がスポットライトに照らし出されていた。鍵盤から顔を上げると,いつもその花達が目に入った。何故か分からないが,何だかとても哀しかった。RのホステスでT子という女の子がいた。キレイどころが集まっていたRでも目立つ子だった。目が大きくて,一見お嬢さん風のいでたちをしていた。T子のファンも多く,彼女のまわりはいつも華やかだった。一見ホステス風で無くても,少し酒が入り,テーブルの客共々盛り上がってくると,彼女の言動はやはりザギンのステホスそのものに変身した。彼女は他のホステスよりも,テーブルからテーブルへ,クルクルと動き回り,彼女は他のホステスよりも,僕が曲を弾き終わると拍手をした。「センセ-,ピアノうまいんだ-,あたし子供の頃ちょっと習ってたんだけど,チェルニ-の練習曲ぐらいでめげちゃってー。続けとけばよかったな-。」素の顔でそういう彼女と,客と対応している時のホステス然としている彼女とのギャップが,さらに彼女を魅力的にしていた。とにかく,どこかちょっと,他のホステスとは風情が違っていた。銀座界隈でピアノを弾く時,一つだけ守らなければならないことがあると,バンマスに諭されたことがある。銀座を初めてまだ日も浅い頃だ。つまり,お店の女の子とのおつき合いは厳禁。ウエイターとホステスがデキルというのはよくある話だが,ばれれば銀座界隈から所払い。店も当然クビ。女の子がその筋の方と懇意であればただでは済まない。「ミナミちゃん,悪いことはイワネエ,遊ぶんだったら金もって,どっかほかんとこでやってくれよな。」冗談をいってるような表情でバンマスにいわれた。でもその目はまじだった。掛け持ちの仕事というのは,実際時間との戦いだ。8時29分に,例えばナイトクラブAから飛び出す。8時30分にはナイトクラブBのピアノの前に座っていなくてはならない。また,8時59分にBを飛び出して,9時きっかりにAに戻るのだ。それを8時から御前1時まで,月曜日から金曜日まで続けていた。小便するひまも無かった。Rは日航ホテル横のビルにあり,エレベーターが運よく1階に止まっていればそれに駆け込んで二階にあがる。エレベーターがどこか上の階に行って使えない時は,横の階段をかけのぼる。エレベーターがまっている時の方が少なかった。エレベーターを使うのは,お客さんや我々ミュージシャンだけでは無い。Rから客が帰る時,何人かのホステスが必ずビルの1階の踊り場までお見送りをしていた。皆で嬌声を上げ,手をふって,「またきてねー!」とやるためだ。ある日僕は,いつものごとく小走りでRに向かっていた。走りながらユニフォームを着替えることもしばしばあった。Rのあるビルの前まで来ると,運よくエレベーターが1階に止まっており,ドアが開いていて,中には誰も居なかった。エレベーターの中に滑り込み,ネクタイの曲がり工合を直しつつ2階のぼたんを押した。フ-,今回は階段を駆け上がらずにすむ。ドアがしまり始める。すると向こうから人陰が手を降りながら近づいて来るのが見えた。T子だった。「せんせー,まってー。」反射的にドアを開けてまっていると,彼女が滑り込んで来た。ドアがしまる。エレベーターの青みがかった蛍光灯の明りに,変に上気した彼女の顔が浮かんでいた。女の人のこんな表情を見るのは,生まれて初めてだった。じっと目を見つめられた。いい気持ちだった。実際並んで立ってみると,店の中で見るより彼女は小柄だった。エレベーターの中には鏡がはってあり,そこに彼女と僕の姿が写っていた。小柄とは言え,今まできづかなかったが,彼女のスタイルは抜群にいい。ちらっとその鏡に目をやると,彼女のムチャクチャ形のいい足が,もう少しで僕の体を挟みそうだった。周りの空気が濃密になったような錯覚を起こした。彼女と二人っきりに成るのはもちろん,これが初めてだ。彼女は,少し唇を押しつぶしたような表情で,上目ずかいにじっと僕の目を覗き込む。「せんせー,わたしいつも,センセ-のピアノすてきだと思ってたんだ-。」すっと手が伸びて,ユニフォームであるダブルのスーツの胸ポケットに紙片を滑り込ませる。その手つきたるや,どんなマジシャンでもかなわない、あっという間の出来ごとだった。実際全ての事があっという間の出来ごとだった。たかだかエレベーターが1階から2階まで上がる間の瞬間である。しかし驚くべきことは,ドアが開く頃,彼女は僕と向き合っていなかった。ちゃんと店の方に顔を向けていて,ドアが開くや否や,彼女は店の中に,実際見事な身のこなしで滑り込んで行った。ドアを開けて待っていた僕のエレベーターに滑り込んで来た時の同じリズム感がそこには有った。エレベーターを出た2階の踊り場には,バンマスと同僚のべーシストが,出番を待って立っていた。死ぬほどドキッとした。今有ったことを表情で悟られまいと思い,思わず視線をそらせた。彼らは店の中の,チェンジのピアノの人の方を見ている。助かったかな?店の中からは,気の抜けたピアノのアルページオが,我々のいる階段近くの踊り場まで流れてくる。否応なく,毎晩聞いている音だ。「アノウ,まだ時間かかりそうですか?」「あいつヨウ,何時だと思ってンだよ,とうに時間過ぎてるだろう,急いで来たこっちの身にもなれよなあ」「あのバンマス」「なんだよ?」「小便してきていいっすか」「すぐ戻ってこいよ」トイレに駆け込んだ僕は,中に誰も居ないことを確かめてから,胸ポケットの紙片をそっと取り出す。リ-ジェントのロゴが入ったメモ用紙に,「こんど電話してね。T子」と走り書きがしてあり,下に電話番号が書いてあった。エレベーター横でバンマスを見た時より,もっとドキッとした。しかもそのドキッとした感じは,もっと体の芯から来る,何やら甘ったるい,どうしようも無くけだるい要素も含んでいる。急いでその紙片を,胸ポケットでは無く,スーツの内ポケットの奥の方に捩じ込んだ。急に銀座の,Rの,変にごてごてしたトイレのシャンデリアが,ものすごく高級で明るい,何というか全てが幸福で明るく,活気に満ちて見えた。鼻歌が出そうに成るのを押さえつつ,ピアノを弾くべくトイレを出た。10年以上前の話。
某月某日
前日アルフィーでの演奏が思いのほかハードであったのか今日は午前中何もできず、良くいえば、ひたすら体事体が体を休める方向に向かっている、悪くいえば、はなはだ怠惰で無気力な状態となり、無為に過ごす時間が意識の中をすり抜けてゆくような昼の時間だった。今年の冬から岡本太郎の著作に心酔している。彼の画業もさることながら、その著作に優れたものがあまりにも多い。青林工芸舎、「太郎に訊け」、これは、岡本氏が生前月刊プレーボーイの読者の悩み相談コーナーを集大成したものだが、投稿の質問の内容が稚拙であっても、全身でぶつかって答えている岡本氏に桁外れな好感が持てる一冊だ。この本以外にも、光文社文庫の「今日の芸術」、みすず書房から出ている一連の著作集、彼の秘書を永年つとめた養女である岡本敏子氏の本、どれをとっても今のぼくが探しているある一種の、ぼくの活動における根元的な問題や悩みを救う指針に満ちあふれている。これらの岡本氏の発言にいつも共通する信念、瞬間瞬間爆発し、岐路にたったらより危険でリスクの多い方を選ぶといった生きざま、その他全てがぼくの今の位置を鼓舞し、反省せしめ、勇気づけている。その筋からすると、今日の午前中のぼくの有り様は、目も当てられない怠惰なもので、岡本氏の著作を読んだものの片隅にもおけないひどい時間のすごいし方だった。午後から精神的肉体的に復活し、フィジカルなエクササイズと共に作曲する。瞬間瞬間に本当の意味で挑戦していれば、良い曲を書くのもあながち不可能では無いはずと信じて楽器に対峙するのだが、いかんせん岡本太郎の著作にあるようなスパッとした展開はなかなか無い。ぼくは岡本太郎のような全人格的天才では無いことを差し引いても何かが足りないのかも知れない。この部分は読書でもおぎなえないことは充分承知だ。しかしだからといって全てを停止すれわけにもゆくまい。演奏の仕事も、ティーチングも無い雨の一日だったが、色々と全てやりおえて、以上のような感慨が残る一日だった。
某月某日
六本木アルフィーでトリオの演奏。朝から雨がふっている。気圧のせいか頭の中も重く、日常の些事をこなすのさえ、いつもより時間がかかる。以前日記にも書いたが、どうもぼくは天候気温季節その他に影響されやすい。皮膚が湿気にてきめんに弱い。昨年3日間ながらタイのバンコックで演奏の仕事をした時、日本の気温と現地の気温の格差とその湿気でどうかしてしまうかと思った。バンコックそのものは妙に魅惑的な場所だったが。空港を降り立つと、花の芯と埃、果物が熟した時に放つ香り、そして若干のゴミの匂いがないまぜになったような臭気が空気の中に満ちていた。そしてその空気の質量事体の中に、多分の水分が感じられ、3日間その中で過ごした。確実に頭の中のシャープな部分をとろかす気体が常時からだのまわりに有るといった感じ。しかしその頭の中のシャープな部分は、常々不安とか、心配、憂いなどを感じる部分であるらしく、滞在中妙に脳天気に過ごすことができた。皮膚の状態はよく無かったが、意外と居心地は良かったわけだ。さて東京で、妙に気圧の高い日で雨がふっていても、ビジターで無いから何とかこの環境に順応し、日々過ごさなければ成らない。しかし今日という一日は、タイに居た時のように、頭のシャープな部分も鈍らず、しかも頭は重く、皮膚にも不快感がある。アルフィーに行くと、すでにべーシストの安カ川、ドラマーの外山共に揃ってカウンターの角でだるそうにしていた。同じ気分だそうだ。カウンターの端にある窓から東京の夜景を覗いてみると、赤くライトアップされた東京タワーの上半分が、雲とも蒸気ともつかぬ妙なタレコメ物体に覆われていた。建物の中から見れば変に美しい光景だが、あのタレコメ物体は東京全体を覆っているわけだから、こっちの頭が重くなるのも無理からぬ事体だろう。頭も重く、東京タワーも半分身をかくすような天候にもかかわらず、演奏はなんともクールに乾いた印象を残すもので、久しぶりに集まったにもかかわらず、お互いのバランスも良くとれた面白いものとなった。安カ川、外山共さすがの演奏。全て終了し、六本木の街路に出てみると、ビシャビシャビシャと雨がふっている。雨の東京って嫌いじゃないんだが。タクシーの柄とか色が妙に艶かしく、しかもくっきり見えて、ネオンも雨の蒸気でにじんだりして、それはそれで、普段見なれた東京の光景が別の様相を呈する。でも今日は、なぜだかそういうことを楽しむ余裕が頭の中に無い感じ。床がぬるぬるした地下鉄に乗っておとなしく帰った。
某月某日
何も無い日、つまりピアノを教えたり、演奏に出かけたり、業界の人とあって打ち合わせをしたりということの無い日。朝ゆっくり起きて朝飯をわざと抜きつつ読書。夏目漱石の「草枕」をじっくり読む。以前何度か読んだ筋に新しい発見あり。目の焦点が合ってきたところで読書終了。実はこの本、ピアニストのグレン・グールドの愛読書だったのだ。「草枕変奏曲」横田庄一郎著、朔北社に詳しく書いてある。この本を読んで再び草枕を読み返してみようと思い立った。この物語の冒頭の文章にすごく愛着を感じている。漱石、グールドともに生い立ちが似ているという。精神的に弱った時にこの草枕の冒頭の文章を読むと勇気づけられる。連休明けでやっと近所の食べ物やも通常営業となった。いつもの定食やで魚定食にしらすおろしの昼飯を取り、家に取って返して5時間ほど練習。最近作曲に関して、その方にぼくの頭脳が向かない。なぜだか分からない。ただひたすらフィジカルな練習の後、有機酸素を取り込むためのエクササイズの運動。気がついたら10時を過ぎている。今日の行動半径は家から半径500メートル以内。それでも充実した一日は過ごせるのさ。北朝鮮から正男が来ってぼくの求めているものには変わり無い。ゆっくりワインを飲んで寝ることとしよう。
某月某日
連休前現金をおろすのを忘れ、しかも自炊を放棄して久しく、冷蔵庫には何も入っていない。しかもしかもいつも行くレストラン、定食や、パン屋の部類も軒並みシャッターを閉めており、しかもしかもしかも連休中とあってぼくの住む澁谷近辺にはゾロゾロゾロと大勢の人が歩いている。カップル、家族連れ、良く分からない奴、普段静かな地域なので辟易とする。夜メシは吉野やの牛丼だった。蛍光灯の下で牛丼を喰っていると、映画館の真ん前の席で、しかもフルヴォリュームで、「釣りバカ日記」を無理矢理見せられているような気分になる。現金もないくせにふらっとパチンコやにはいる。4000円投入して箱四つの20000円の勝利。ざまあみろ。ギャンブルはやめて久しいけれど、連休だから良かろうと思ったのが吉と出た。換金の後お気に入りのカフェに行ってワインを一杯。後小一時間散歩。散歩中ひらめいた。連休だから当たる台が空いている確立が高いのではないか。二駅先のエリアまできていた。駅前のパチンコやに再びはいる。知らない場所の知らないパチンコや。1000円札投入し2分もたたないうちにあたった。閉店まで打って19000円勝った。再びざまあみろ。乱杭歯のババアがじゃらじゃら玉がでている俺の台を覗き込んでいた。おかげで現金が手に入り、連休を何とか過ごすだけの貯えができた。泡銭とは良く言ったもので、こういう金は絶対手元に残らない。10年ほど前、銀座のナイトクラブでピアノを弾いていた時、一曲弾くごとによくチップを頂いた。一晩5万ぐらいになる夜もあった。バブル全盛の御時世だったのだ。そんな金はせっせとパチンコの注ぎ込んだ。何だか貯蓄したり有意義に使うのが馬鹿らしく思える金だった。しかしそういう時に限ってパチンコでも大当たりをとってしまい、また手元にまとまった現金が残るようなことが何度かあった。アメリカに留学以後、こちらに帰ってきてから久しくパチンンコなどやらなかったのに。今日はそんなことを思い出す妙な連休の一日だった。
某月某日
他の天体にいるような一日だった。灰色の空。春なんだかなんなんだか分からない気温。気がふさぐ日々が続いていて、家にいる間中、ジョビンのボサノヴァをかけっぱなしにして過ごしてきたのに、今日の雲行きには、ジョビンも対抗できない。どんよりなんていう言葉さえあてはまらないような憂鬱さ。レッド・ガーランドのスローブルースのような一日。ブルースがボサに勝った日。あまりいただけない。こういう日はこもって作曲をする。外に出たって、何をしたって、気がふさぐことはまぬがれまい。以前は政治のことにも目を光らせていたが、最近はどうでもよくなってきた。ぼくは自分の行く末と、音楽のことだけが、今はいちばん重要だ。この考えに恥じることはない。今日はインター・FMのジャズ番組のゲストとしてしゃべった。広尾と霞町(今は西麻布という地名だ。でもぼくにとっては霞町なのだ。)の間にあるビルの18階にあるスタジオにいった。曇り空の下にある東京の街が眼下に広がっていた。何だか全てがくすんでいて、でもぼくの好きな街並には変わりなかった。でもその街並の中には、ヴォサもブルースも存在しない。やたら無機的に見えて、しかもぼく自身にはいちばん親近感が持てる場所なのだ。春の日の、変わった気温の日にでもぴたっとはまるサウンドはないだろうか。デザインや、壁の色や高さ、姿形が全く違った建物がまったく平和な雰囲気の中に並んでいる東京の景色。形や色を覆い隠す夜の景色が、東京には似合っている気がする。
某月某日
本日、新宿ピットインで演奏。自分のトリオ、安カ川大樹、外山明というメンツ。当日の午後まで、リラックスして演奏する為の練習、曲作りをぎりぎりまで続ける。ものすごく良いメロディーの断片ばかりがてもとにあり、しかしその前後ができない。今日は今までの曲で演奏することを決め、急いで準備をして家を飛び出したら、渋谷駅にてCDを鞄に入れ忘れたことにきづく。今日はCD発売記念ライブである。ピットインに少し遅れる旨連絡を入れ恵比須方面にひきかえす。おかげでピットインに到着したのは7時をまわっていた。ピアノの調律が良い。吉兆だ。ドミソの和音の良いバランスの倍音の上に、アイデアを乗せられることがぼくの喜びで、弘法筆を選ばずの境地にぼくはまだいない。いっかい調律の無茶苦茶なピアノで、キース・ジャレットのスタンダードトリオを聴いてみたいものだ。どうなるんだろう。最近演奏前によけいなことを考える癖がついてしまって、今日ピットインの楽屋でも、ああでもないこうでもないと考え込んでしまった。よけいなことを考えても、演奏する内容に大差はないと分かりつつ考えてしまうというのは、要するに無駄なことが好きなんだろう。偉大なプレイヤー達、ジャズ、クラシックのジャンルを問わず、皆ものすごいことをいう。曰く音楽は人生を謳歌するもの、音楽のヴァイブレーションが世界に伝わる云々、、、。はやくぼくもそんなことを真顔で言えるようになりたいものだ。だが反面、ぼくはたとえそういう音楽を実際演奏できるようになったとしても、恥ずかしくてそんなこと人前で言えないと思う。まあ、ミュージシャン一般ある意味一種の誇大妄想的発想が必要なのかもしれないけれど。当たり前の事だが、演奏が終わるとひじょうに疲れる。演奏後も元気なやつは逆にある意味信用ならないかもしれないが。演奏を見にきてくれた友人と中目黒の居酒屋で軽く食事をする。店内には有線だろう、ビバップのサックスが流れていた。ぼくは対外的にジャズピアニストとなっているけれど、こういう演奏と比べたら、ぼくのやってることはジャズでも何でもないんじゃないかと、またよけいなことを考えてしまった。
某月某日
私生活が悲しくとも、仕事はちゃんとしなければならない。横浜に結婚式の演奏によばれて行き、演奏した。新郎新婦の両親にいたく感謝された。待ち時間中横浜湾に面した式場の大きな窓から海を見たりした。とある飲み屋で知り合った人に頼まれての演奏だから、その新郎意外知り合いはいない。出席者は皆各々に着飾って楽しそうだ。それを式場の角からながめつつ、海の方にも目をやる。タグボートなどが行き来している。だんだん暗くなってゆき、満月がのぼり始める。宴酣、新郎新婦の友人達が余興を披露したり、歌を歌ったりする合間にピアノを弾く。窓の外には満月が窓のまんなかに浮かんでいる。式も終わり、バスで桜木町の駅に向かい、そのまま家に帰ったら近所の友人が彼女をつれて遊びに来た。白ワインを三人で飲んだあと、中目黒の夜桜を見に行く。なぜだかぼくだけ一人で、他の人たちはみなだれかと一緒のような気がしてきた。でも独りぼっちってわけでもない。友達の彼女とバカ話しをしながら、目黒川沿いを歩く。さっきの満月がいろんな方向から見えかくれする。満月は無表情なようでいて案外優しい雰囲気を持っているのかなあと、ほろ酔いかげんで月を見ながら歩いていたらつまずいた。友達の彼女が笑った。ちょっと寂しくて、ちょっと変化にとんだ春の一日だった。
某月某日
最近個人的に悩むことが多く、精神的な行き詰まりが激しい。詳しく書くと、なにかと問題になるので避けるけれども、要するにぼくはフリーランスのミュージシャンであり、世間一般でいうところの安定も、大方の人が幸せだと思う規範での心の安寧も、仕事をする上での最終目標にはなりえない。仕事に付きまとう色々な要素、権力、財力、名声、等などの事柄は、ミュージシャンにとってある程度のものであって、それが最終目標にはなりにくい。なぜなら音楽そのものがいちばん大切な事柄だから。しかしそこで火を吹くような反応を見せるのが、身直にいる女性達である。ガールフレンド、彼女、愛人、女友達、なんだって良いのだが、要するに、ぼくに対してかっこ良くいて欲しいと彼女らはいつも望んでいるのだと思う。そして、ぼくが音楽を大切にするのと同等のレヴェルで、彼女ら自身も自分達を大切にして欲しいと思っている。そして、そういう女性達を愛おしくかわいいなと思う反面、そんなことできるはずねえだろという矛盾のうえで、うまくことを運ばなければならない。しかしいったい、うまく事をはこぶってどうすればいいんだ?女性の方が男性より強い。断言してしまうぼくがもし世間知らずの幼稚な男と規定されるならば、少なくとも、このぼくにとって、女性達ははるかにぼくよりも強く逞しく、そして魅力的な存在なのだと言い換えてもいい。戦争の行く末に言い表される降参という、国家、政治概念をベースに表明される言葉がある。そして政治上のこの意味とは違ったスタンスで、ぼくはあらゆる女性達に対して降参している。まず白旗をひらひらさせながら、デートでも、おつき合いでも、インターコースにおいても、ぼくにとっては降参という状態からすべてが始まる。決して卑屈になっているわけではない。況んや降参してかかるということ事体、これはぼくが男性として良い意味でプライドを持っているからこそできることなのだ、と信じている。最近悲しいことが連続して起こり、それが女性との関係に起因していて、悲しく鬱状態になっている。しかしその鬱状態を優しく包むように慰めてくれるのも、ぼくが両手をあげていつもマイッタといっている同じく女性そのものなのである。降参してしまえば、過去の経験などあてにならない。手練手管をしりぬいた大人の男のアドヴァイスも場合によっては参考にならず、有効ではない。とにかく今は、悲しみと希望のはざまを気分的に行ったり来たりしていて、どうにもやるせない。まあどうせ、嬉しいことも悲しいことも永遠には続かない。そう考えることが、せめてもの救いだ。
某月某日
小岩のキャバレー,Hでピアノを弾いていた。19才の頃だ。バンドの楽屋の横に廃虚のような空間があり,そこにはフィリピン人のホステスが,ウレタンが爆裂しているようなマットレスの上に寝起きしていた。楽屋には裏口があり,裏口の鉄の扉は,換気の為かいつも開けっ放しだった。そこからJRの線路が見えた。たくさんの人を乗せた電車が行き来しているのが見えた。この世の果てのような風景だった。全ての風景は退色していたが,少なくとも,その楽屋の中だけは,僕も含めて若いかけ出しのミュージシャンがおり,皆それぞれ何とかして楽器をうまく演奏できるように成り,この場所から抜け出そうと四苦八苦していた。その息吹と向上心だけが,その場の空間を明るくしていた。ある者は安物のヘッドホンでスティーブ・ガッドのコピーにいそしみ,ギターのヤツは休み時間さえ惜しんで練習に余念がなかった。ピアノの僕としては,手元に楽器がないので,アレンジの本を読んだり,実際譜面を書くなどしていた。実際そのふりでも,少なくともしていないと,バンマスとポーカーをするはめに成り,ただでさえ安いギャラから負け分を差し引かれたりした。その頃は日替わりで演歌歌手がやってきた。名も知らぬレコード会社の,名もしらひとたちばかり。その晩も,いつもの時間にいつもどおり,歌手が楽屋にやってきた。ハナブサ何とかという名前で,出し物はヌード演歌だった。本番中は結っているのだろう長い髪を,ザンバラガミのようにたらし,薄暗いネオンに長年照らされてきたその顔は,しかし妙に花々しく,いきいきとしていた。明るいところで見たら40代,暗いところで見たら20代といった風貌。本番前の素っピンの顔は,妙に親戚のおばさんのようにも見える。この人ホントに脱ぐのだろうか。しかも歌いながら。彼女は,独特の物腰で我々バンドに譜面をわたす。「ハイ,ギターさん,ハイ,ピアノさん,ハイ,ドラムさん,」もう数えきれないほど同じ事を,全国のキャバレーでやってきたのであろう、その動きは何か,優美さをも感じさせるものがあった。「ハイ,最初の曲ね,テンポはこんな調子で。う~らーみっこな~しで~,わかれましょ~~~よ~」。その譜面がまた,宝島の地図のように,茶色く変色しており,巻物のように長い。ところどころ破けた箇所にはってあるセロハンテープも,茶色く変色している。譜面台に乗り切らないほど長いその譜面には,やたら多くの繰り返し記号,ダルセーニョなどが書いてあり,つまり譜面の最後まで行って突然ド頭やまんなんかに戻らなければならない。初見で弾くには,見失いやすい要素がいっぱいだ。しかも長年同じ譜面を色々なところで使ってきたとみえて,変な書き込みがいっぱいあって,何がなんだか分からない箇所がいっぱいある。しかし,次々に譜面を渡しながらテンポ設定をするヌード演歌嬢に,質問する余地はない。いつものオープニングの演奏の後,彼女が登場する。彼女の踊る位置は,僕の弾いているピアノのすぐ横だ。1曲目のテンポを,ドラマーが慎重にスティックを叩いて我々に知らせる。イントロを演奏し,テーマに入り,音楽は譜面のジャングルの中を進んで行く。罠がいっぱい。ただでさえ薄ぐらい,しかも赤だの青だのと変わる照明のした,我々は譜面に目をこらす。べーシストが間違ったところへ行っても,我々リズム隊はそっちについて行くしかない。しかし,歌い手にもついて行かなければならない。突然のピアノの間奏。ソロではなく書き譜。譜面が古くて読めない箇所がある。ああ,だめだ,間違える。「いかの~あぶったの~あればいいいー」ふと目を上げると,目の前に半裸の女性がケツをふって踊っていた。年若い僕の目にさえ,冴えない裸体だった。ケツの肉も,でこぼこして弛んでいた。しかし不思議に,僕の目はそこから離れられなくなく成ってしまった。と言っても2~3秒の事ではあるが。しかし演奏中の2~3秒は,譜面の上ではとてつもなく長い。どこをやってるのか分からなく成ってしまった。ヌード演歌嬢は,ストリッパーが必ず持っている,あのじゃらじゃらのヒモみたいなものを,股間に挟んで,それを手で上下させ,演歌を歌いながら悶えている。ちょうどそのじゃらじゃらを股間から外す時,彼女はパッとバンドがわに顔を向け,客側にそのたるんだケツを向ける。下にはもう何もはいていない。扇情的にするため,客をじらすため,肝心の部分を見せる事を,最後に持って行くテクニックである。しかし彼女から一番近いところにいるピアノの僕の真横では,彼女のオケケと女性自身がゆらゆらとしていた。そう、一番良く見える位置にある状態となる。年増だろうがなんだろうが,下半身さらけだした女性が,腰をふっていれば,譜面から目が離れても致し方ない。どこを演奏してるんだか分からなくなった。その時僕は19才で,おんなのことも,お金の事も,仕事の事も,音楽の事も,何も知らなかった。なにもかも分かっちゃいなかった。只々一生懸命だった。だがその時は,自分が今ステージの上で何をやっているのかが良く分からなくなってもいた。俺はいったい何やッてんだ?19才の僕の横にヌード演歌のハナブサナンタラが踊っていて,僕の目の前で彼女のオケケがぐるぐると円を描いていた。ただひとつ言える事は,二人はステージの上におり,立場は平等だという事だ。問題は,その時の僕は,彼女の仕事の邪魔をしている,つまりちゃんと伴奏していないという事だった。下町の,この世の果ての,薄暗い場所で,僕は全然なっていない演奏をしていた。オケケの横で,僕はピアノをひいていた。10年以上前の話。
某月某日
19才の頃,新宿の喫茶店でアルバイトをしていた。何だかその頃は,自分の生の行程がはっきりしない,薄ぼんやりした日々だった。というのも,退学に近いかたちで音楽高校を追い出され,やりたいピアノの道への確固たる道筋が見えていなかったからだ。そういうことに関してアドバイスをしてくれるものも身近にいなくて,ただただピアノのレッスンを受けている毎日だった。逆に言えば,もしその当時僕の心がとんがっており,先鋭であったなら,ある面で狂ってしまっていたかもしれなかった。高校を放校同前で卒業し,僕には何も残っていなかった。本能的にと言うか,自衛の為,僕の頭は薄ぼんやりしていたのかもしれない。しかしその薄ぼんやりとした感覚の中には,えも言われぬやるせなさと怒りが同居していた。その持って行きようのない哀しさを言い表すことは難しいが,呼吸をするごとにその悲しみ事体が、この体から少しずつ抜けて行ってくれたらどんなに楽になるだろうと思うような,重たい感覚だった。どうにもこうにもならない気分の毎日ではあったが,レッスンの月謝の足しにと,アルバイトを始めた。僕はその喫茶店で,全ての事をやらなければ成らなかった。店内の掃除,コーヒーを入れたりサンドイッチを調理したり,もちろん飲み物等をトレイにのせてお客の方まで運ぶことまで。アルバイトは僕のほか女の子数人で,店長,その他の男の従業員は,ある大手デパートの正社員であった。喫茶店はそのデパートによって経営されていた。皆一様に蝶ネクタイに白いシャツで,前掛けのようなものを腰に巻き,かぎりなく惰性の,それもいつおわるやも知れない無為な空間でみな無表情に働いていた。全ての仕事を覚え終わると,そのあとに来るものは,その惰性と無限時間の中で,どうやってお互いがそのことを忘れることができるかという,本当に下らないが大切なことに腐心するようになる。正社員の男達は皆高卒で,20才前後でちいさな子供と奥さんを養っているような者もおり,しかし高校時代は相当の不良であったものが大半であったから,大人なんだか子供なんだかよく分からない人達で,つきあいかたに苦労した。Yという男がいた。顔つきが丸太を思わせる何かヌボーッとした印象の男で,体型自体も頑丈そうだが雰囲気はないといった人物だった。ある日,僕がトイレの掃除をしているとき,Yがいきなりトイレのドアを空けて僕をにらんだことが有る。掃除をしている僕を見ると,表情もかえずにバタンとドアを閉めた。事実上トイレの中は密室状態になる。前のバイトの人間が,よく掃除をするふりをして中でさぼっていたのだそうだ。次の休憩時間にかれと控え室でいっしょになった時,Yはそう説明した。疑われたことが少しおもしろくなかった。しかしYには,そういう状態をウイットにとんだ会話でその場の空気を変えるような機知が備わってはいなかった。彼は急にぬっと右腕を僕の方に差し出した。手の甲を見ろという。覗き込むと,何か黒いシミのようなものが,皮膚の内側にあった。高校時代,死ね!と言う叫び声とともに授業中同級生に刺されたのだそうだ。その時に無意識にかばった右手の甲に,まだそのきずが残っていると言うわけだ。Yはその時反撃に出て,授業中であるにもかかわらず,その襲ってきた男をぼこぼこにしたそうだ。その時から彼は,僕がおとなしく話しを聞くことができるものだと知ると,休憩時間になると決まって,高校時代の武勇伝を僕に語るようになった。それは耳を被いたくなるようなリンチの模様などで,決してこころよい話ではなかったから,僕の休憩時間はいつも気の重いものとなった。しかし逆に,それらの物語の中の被害者に,新たに僕自身が加わることは絶対避けたかったので,おとなしくはなしを聞いていた。厨房でいつもサンドイッチやパフェなどをつくっていたNと言う男は,一見おとなしそうな何とはなしの二枚目で,店長にも客にも愛想が良く,髪型やたちふるまいもこざっぱりしていた。ある日,ランチタイムが終わって,一気に客が引けた後,夕方になるまで一人も客がこないという日があった。その喫茶店はビルの一階にあり,りに面していたので,午後に西日が直接窓越しに店内を照らすことになる。そういう午後の時間に,客が一人も居ない時間が長いと,誰一人として本当の意味での勤労意欲などないにもかかわず,これはこれで殺気だった雰囲気となってくる。その日Nは,暇そうにしている他の従業員から離れ,ひとり厨房で熱心になにか調理していた。客の居ないあいだに,何か新しいメニューでも創作しているのかなと思っていると,Nが僕の方を見て二コッと笑った。気味の悪い笑い方だった。こざっぱりとしたNには似合わない,ある種の残酷さをも感じさせる笑い方だった。その大きな瞳は血走っていた。その目は,おい,ちょっとこっちに来てみろよ。いいもの見せてやるぜと言わんばかりだったので,僕は厨房の中にはいっていった。調理台の上の皿の上には,今まで見たこともないようなサラダが乗っていた。レタス,トマト,きゅうりなどがきれいにレイアウトされていた。僕が何か言おうとすると,Nはそのサラダの中のきゅうりとトマトを手に取って僕に見せた。それは,包丁やぺティーナイフで細かく形作られた,男性器と女性器だった。トマトやサラダが新鮮で水に濡れているからこそ,とてもグロテスクに見えた。そしてそれはとてもよくできていた。Nはその血走った目で僕を見つめながらきゅうりとトマトを両手に持って,性交を暗示する動きを続けた。気持ち悪かった。しばらくしてから,やっとひとり客が店内にはいってきた時,彼はそのセックスサラダの部品でミニサラダを作り,客に出した。何だかやるせなかった。キャバレーでピアノを弾く仕事が舞い込むまで,19才の僕は,その喫茶店で半年ばかりアルバイトをしていた。何か全てが薄ぼんやりとしていて,何か全てがはっきりしない日々だった。
某月某日
ピアノを長時間教えたら疲れきった。自分で料理する気力もなかったので、近くの居酒屋にいった。前に来たことのある店で、焼酎のボトルをキープしていることを自分でも忘れていた。店員が俺のことを覚えていてそのボトルをテーブルに運んだ。軽くビールでも飲んですまそうと思っていたのに、ボトルの焼酎をお湯割りでのみだしたら止まらなくなった。何だか、なにもかも面白くなかった。日本のこととか政治とか、音楽の状況とか、全てクダラナク思えた。一体全体この国はどうなってンだ。クダラネエ。自分の音楽のことを考えた。いさかい、離婚、失恋、戦争、核兵器、憎しみ、税金、あらゆる種類の病気、等など、いきているうちは、苦しいことの方が楽しいことより多い。だからこそ一瞬でも良いからきれいな音楽を、きれいなピアノの音を、たとえ客がいなくたって演奏することが、その瞬間、その演奏している場所を有意義にできるのではないか。そういうふうに考えること、そういうふうに考えられることが、ただ一つの俺の救い、そんな夜だった。
某月某日
「ひばりジャズを歌う・ナットキングコールを偲んで 28CA-2671 コロンビア」は僕の密かなる愛聴盤だ。音楽を仕事としてやっていると、どうしても聞く耳の中に他のジャンルやプレーヤーと比較するという、ある意味ではよこしまな、しかしある意味では必要不可欠なイライラした神経がどうしても混ざってしまう。中学生のころビートルズを聞いたように、ただただ何かの音楽を心酔して聞き通すということができなくなって久しくもある。けれども、この美空ひばりナットキングコールを歌うを聞いていると、珍しいことにそういう音楽のことばかり考えているからこその功罪から逃れることができるのだ。こういう不思議な力が美空ひばりの歌の中には込められているのだろう。そして、ある意味でおはずかしい話かもしれないが、本家アメリカのジャズヴォーカリストのCDを聴くよりも、美空ひばりの歌声の方により安らぎと親近感を感じるのだ。ジャズには二面性があり、ひとつは文明の力的要素をもっていることと思う。誰にも学びうる約束ごとを了解しあえばそこに参加できる側面と、その環境や歴史に生まれ育たないと理解に苦しむ文化的側面。外国のことが好きになった大方のミュージシャンが一度は思い悩むそういった理屈を、美空ひばりは軽々と一蹴して、自分の持ち味、自分の歌心、自分のテイストで、軽々とスタンダードナンバーを歌っている。そこには、実は私はジャズ歌手だったのだというてらいも無く、お仕事で歌っているというなげやりさ加減も無く、しかも良い意味で本当に日本人的な歌でもある。これはすごいことだ。僕の育った昭和という時代の雰囲気も加味されて、非常に聞きやすい。音楽によって喚起される情景がひじょうに身近なのもてつだって、一曲めのスターダストからほっとした気分になれるのだ。まるで子供のころ、団地に住んでいたのだが、白黒テレビの前で、着物姿の親父とエプロンをしてカーディガンを着た母親と一緒に晩ごはんを食べているようなやすらぎをこの歌声はとどけてくれる。僕も、まあもちろんのこと、美空ひばりと自分を比較するような乱暴なことはつつしむけれど、このCDにあるような雰囲気を自分の音楽の中に残すことは忘れたく無い。それは、美空ひばりが表現した音楽が、僕にとって本当に身近かなものだからである。
某月某日
季節が艶かしくなってきた。陽光が強さをまし、庭のツバキも咲き始める。しかしなぜか気分は重くなるばかりで、気分的に春には明るさを感じない。何かざわざわとした、妙なけだるさを感じるばかりで、だからこそ明るい日射しがすこし鬱陶しい。今年はツアーに行くことが仕事の上で少ない。演奏に行くクラブなども、ぼくが住む恵比須近辺から半径30キロ以内である。突然デンマークにツアーに行くことになったりするので、その振幅は激しい。しかし最近は行動半径の範疇でいえばおっとりしたものである。その気分に春の季節がのっかってきたのである。春という語感には、発芽、入学など正月とは違う日本独自の心機一転の雰囲気が込められている。しかしこれらの事象は前向きなもので、ぼくにしてみれば、頭のぼやけ、集中力の欠除感、けだるさ、なまあくび、などなど、僕は春という季節の良いところを受け取れない体質に生まれついているみたいだ。どうあれ桜はきれいに咲いてほしいな。
某月某日
きれいな音楽を演奏したい。最近とみにそう思うようになった。きれいといっても漠然とした印象しか与えないだろうが、激しくテンポの早い曲であろうが、どういう状況だろうが、ピアノを弾くかぎり、きれいな音で演奏したい。きれいという範疇も、そのときの時代や文化に影響されるものであるし、ひとそれぞれきれいだと思う範疇も違ってあたりまえだろう。僕は僕がきれいだと思うことを実現する。ある人にとってそれが女々しく写ったり力強さに欠けていたりすることもあるだろうが、ピアノという楽器を、僕しか出せないきれいなおとで弾けば、少なくとも価値は認められるだろう。
某月某日
風の強い一日だった。窓から外を眺めていると、木々の梢がいい感じにしなっている。瞬間的にボストンにすんでいた頃の記憶がよみがえった。寒い寒い冬の一日、風の強い日は強烈なる晴天で、雲ひとつない紺碧の空、夜になれば冷たくそして魅惑的な夜空。それらの記憶がわいてきた。はじめてボストンに行ったのは1988年のクリスマスの日であった。留学する為だ。NY に数日滞在の後、アムトラックという電車に乗って夜ボストン駅についた。電車をおりると目の前に高層ビルが四つぐらい建っていた。ついに来たなあという感慨はあった。しかし同時にやたらと寂しく見えた。NYの摩天楼と無意識に比べたのではなく、もとより僕が生まれ育った東京と比較したのでもない。どう言ったものか、今まで行ったことのある地球上の最北端を大きく上回る地球上の北側にいることによって、体が敏感に反応したような寂びしさだった。駅を出て、荷物が多かったからタクシーに乗った。住まいはもう既に留学していた友人に探してもらっていたのだが、まず自分が日本ですべてに終止符を打って行くことになった学校の姿がいち早く見たかった。運転手に学校の住所をつげた。ボストン駅のすぐ裏手がチャイナタウンの入り口で、なぜか向こうの裏路地の街灯は病的なオレンジ色をしている。その灯りのしたにレンガでできた建物の壁とゴミの缶などが照らされていて、またよけいに寂しくなってきた。なんだか総てががさがさと刺々しくて、妙にだだっ広くて、道も東京のそれに比べるとでこぼこで、タクシーのエンジンの音さえ、僕には快適でなかった。チャイナタウンを抜けた夜の街並は、洗練されているように見えて何か不自然であり、その雰囲気には何か真に暗い要素が混じっていた。街灯の明るさをいっているのではなく、自分の気持ちがすっと引いて閉じてしまうような冷たさだ。ここに住むのかあ。その当時の僕としては、外気の冷たさも半端なものではなかった。タクシーが学校の前に止まった。むちゃくちゃ寒かった。学校の横にハイウエーが走っており、その上には橋がかかっていて、その橋の上に車の往来の風圧でゴミが舞っていた。総てがかさかさに乾燥している感じだった。学校の前に荷物と一緒に降り立った。見上げるととてもきれいな星が、雲ひとつない夜空に輝いていた。その夜空も、日本では見たことのないような不思議な青みかかった暗い色で、そこにちかちかちかと星がたくさん輝いていた。あとで知るのだが、ものすごい晴天の日は、風も強くそういう日は格段に寒い。僕のボストン一日目はそういう寒い日だったのだろう。不思議とそうして学校を見上げても、なんの感慨もわかなかった。ずっと銀座のクラブでピアノを弾いて金を溜め、やっとここまで来たのに。当時を思い出せば、そこまで、つまりボストンまで辿り付くのが精一杯だったのかも知れない。夢にまで見たその学校は少し古くなった単なる建物にすぎなかった。学校の前にあるマサチューセッツ・アヴェニューも単なる道で、学校の向いにあるカフェは、僕が行きなれた銀座のものに比べると、やたらチンケに見えた。地上のものはさておき、それらを覆う大きな空とその中にある星々が僕に元気をくれているように思えた。ずっと立っていると本当に凍えるので、大きな荷物を抱えて道を横切り、そのチンケなカフェに入った。汚い身なりの多分学生だろう、色々な人種のやつらがコーヒーを飲んだり、ぼーっとしてたりしていた。セルフサーヴィスのコーヒーをテーブルに運んで飲んだ。ものすごくまずかった。苦いだけだった。なるほど、これからこの味になれろという事だなと思った。しかしその暖かい飲み物は、凍えた体に染みとおり、少し指先の感覚も戻ってきた。当面の住まいとして、先に留学していた友人が、寝泊まりする場所を探してくれていた。まずそこに転がり込み、改めて自分のアパートを探すという算段だ。住所を頼りにめぼしをつけてカフェを出た。尋常ではない寒さ。横丁をスーツケースをごろごろ言わせながら歩いた。窓から見るそれらアパート郡の建物には、薄暗い電球の灯りが点っていた。でも何故か、建物の中があったかそうには見えなかった。何だかどこもかしこもすごく寂しそうに見えた。転がり込む先は、同じ日本人の留学生が住んでいるということだった。やっと辿り着いてドアを開けてもらうと、中はなぜだか、大学生時代よく泊りに行った友だちのアパートみたいな匂いがした。どこにいるんだ俺は。それから約1年ぐらいしてから、やっとアメリカもボストンの街事体も好きになった。しかしあのクリスマスの最初の日に感じた寂しさは向こう1年ずっと感じ続けたものだった。すごいクリスマスの一日だった。
某月某日
実にいやな一日で、なぜかといえば全ての事が頭の中ではっきりしない感じがしたからだ。気温はまだ冬であるにもかかわらず、小春日和にぼうっとしたような気分に成ることが多く、気温が春めいていればまだ対処の方法があるのであろうが、気温は冬。脳みそだけ春の予感に妙な反応を示していて体全体がやりきれない感じ。体調が悪いだの、病名のはっきりした病気でもないからこそ困ってしまう。どういうふうに困ってしまうかというと、何かをしている途中、ふっとその動きがとまり、体に向かって発せられるべき命令、普段ならよどみなく考えられる細かな動きなどが突然とまってしまうのである。そう、そのとまってぼうっとしてしまっている状態のときには、止まってしまっているという自覚もなく、普段なら簡単にこなせる日常の細かなことに、ものすごく時間をくっていることにあとから気付く。幸い僕には花粉症の症状はまだない。しかし四季の移り変わりに関して、僕の体は非常に敏感で、普通の人が普通に過ごせる時期を普通に過ごすことができない。特に春先は一番苦手な季節であって、幼稚園児の頃からダメである。血液や筋肉が、ヌルっとした綿のような感じに成り、書いたように脳みそは停止状態に突然おちいり、呼吸する空気の質感が妙に重ったるく艶かしくなってくるにしたがってこれらの症状は体の中で肥大して、体の真ん中の軸のようなものもふらふらするような感じになってくる。いちばんこれらの症状が顕著なのは5月で、5月は僕の誕生月で、だから僕の誕生日を祝ってくれた人たち、幼稚園の頃から今までにかけて、皆僕の浮かないようすを見て、あれ、こいつはあまり嬉しくないのかなという顔をする。せっかく僕の誕生日を祝いに集まってくれた数多の友人親戚達に、いつもすまないなあと思うのだけれど、こればかりは体の軸がふにゃふにゃしてしまっているのでどうしようもない。Spring has come.
某月某日
よくなぜジャズピアノを始めたのかという質問を受ける。日記を書くにあたってこれからは、webを見てよ、と言えるように、ここにその経緯を書き記す事としよう。僕は音楽高校に通っていた。ピアノ科だった。御多分にもれず、ベートーベンのソナタだのドビュッシー、ラヴェルなどを練習しては、先生のレッスンを受けていた。今考えても、クラシックを演奏するという事に対して、何か根本的な根拠があったわけではない。子供の頃から習い始めたピアノという楽器は、元々どうしてかクラシックから始まるものであり、僕もそういうものだと根本的なところに疑問をもたずに音楽高校までいってしまったのだ。だからといって別に満たされてはいないと感じていたわけでも無い。要するに、あまり深いところで音楽のことを考える機会が無かったといえるかも知れない。ある日、作曲科の友人から、シンフォニーのレコードと一緒にジャズのレコードを借りた。「みなみ、こういうのも聞いてみろよ」みたいなのりだったと思う。中学時代からビートルズが大好きで、その他のブリティッシュロックのレコードも聞いてはいたが、なぜかロックのバンドを組むとか、キーボードをやるとか、そういう発想は僕の頭には無かった。きっと爆発させなければいけない何かを、その当時僕は体の中にもっていなかったか、そういう危険なものが体の中にあること事体に気付かなかったかのどちらかだ。家に帰ってレコードを聞き始めた。リムスキー・コルサコフの「シエラザード」などを聞いたことを覚えている。なぜかそれらクラシックに混ざっていたジャズのレコードは最後に聴こうと思っていた。それがキースジャレットの「FACING YOU」だった。大袈裟な表現を抜きにしても、最初の一音めを聞いた時、僕はこういうピアノが弾きたいのだ、と強烈に思った。目の前が真っ白になった。今までいい音楽をたくさん聞いてきたが、あの時の衝撃をこえることはない。英語でいうところのORACLE,天啓だった。東京郊外の、典型的な住宅地の、オヤジがローンで建てた一軒家の、いわゆる典型的な子供用勉強部屋で、キースの深遠なピアノサウンドが鳴り響いた。今考えても、場所と音楽の質を比べたら、ものすごいミスマッチである。そして、どうしようもないステレオセットからその音は出てきた。スピーカーなんて、空き箱みたいな代物だったし、アンプだってプレイヤーだって、かろうじて最低限その役割をはたすようなものだった。しかしそこから出てきた音に、僕の脳みそはギリリとずれたのだ。今まで感じたことも、見たこともない世界が、ピアノの音によって僕の目の前にくりひろげられていた。今まで感じたことのない世界であることは本能的に理解しているにも関わらず、ものすごく自分にとって身近な世界であるようにも思えた。そこには、頭の上から大きな爆弾が落ちてきて、僕の頭の真上に当たって炸裂したかのような感覚と同時に、心の奥底から、なんともいえぬ静謐な、穏やかな心持ちも共存するような感覚が、僕の体の中にできあがりつつあった。キースの演奏が進むにつれ、その感覚は確固としたものになり、理屈抜きで、俺もこういうう演奏をやるのだという確信に変わった。後日、作曲家の友人にレコードをかえすとき、ぼくがいかにキース・ジャレットの演奏に感銘をうけたかを、色々な例をあげながら伝えた。そしてこう聞いたのだ。「この人の演奏している曲の楽譜はどこにいったら手に入るのかなあ。」作曲家の友人はものすごく人をバカにしたような目で僕をみていった。「みなみくん、これは即興演奏なんだよ。だから楽譜はないと思うよ。」そのとき僕はまた別種のショックをうけた。実はそのキースの演奏が即興演奏であるということを僕は理解していなかったのだ。また別の意味で脳みそがギリリとずれたのが分かった。今から20年以上前の話である。しかしあのときから今まで、自分の演奏の中に、あの衝撃をどこかで追い求めているのである。
某月某日
アレンジ及び作曲のアイデアと言うものは、突然どこからか脳の深い部分と体の真ん中あたりに浮かんでくる。否、浮かんでくるという言葉も駄当ではないかも知れない。スッと入り込んでくるのだ。それがどこかなどと考えている暇はない。とにかくそのアイデアを捕まえて譜面にするなりメモを書くなりして、何とかこの世のものとして現実化することに神経を割かなければならない。ボサノヴァの創始者、僕の尊敬するアントニオ・カルロス・ジョビンの自叙伝によると、かれはある瞬間、完全な形で、つまりもう出来上がった完全なヴァランスのメロディーがすっと頭に浮かぶと書いている。これは凄いことだ。僕は天才ではないから、ピアノのある部屋に引き蘢り、飛び上がったり、頭を振ったり、とにかく少しずつ絞り出す事しかできない。では絞り出せばいつもいいものが出てくるのかと言えばそうではない。後で見たら、なんだこれと言うものが大方である。いまだこのかた完璧なメロディーのシェープが、頭に浮かんだこともない。しかし、何かがすっと頭に浮かんでくるというその構造事体は変わらないようだ。今回のCDの中でも一番アレンジしてみたかった曲はフランシス・レイの「男と女」であった。そう、ムードオーケストラなどがよく演奏しているあのシャバダバダでお馴染みのあのメロディーを、何とか僕のものにしたかったのである。うまく説明できないが、この曲がずっと僕を呼んでいるという感覚がいつもあった。何か引っ掛かっていたのだ。今までこれを演奏したり発表したりする機会がなく、その為永年引っ掛かっていたにもかかわらず手を出さなかった。しかし今回、曲の「お呼びに」素直に対峙することにした。メロディーに特徴があり、調性に変化があった方がある面アレンジしやすい。しかしこの曲は、メロディーが打点のようにできている。ブリッジ、つまりいわゆるサビの部分はいかにもシャンソンの作曲家であるフランシス・レイらしい流麗なもので、逆に手が入れにくい。このまま演奏してしまえば、出だしとブリッジを含めおきまりのものとなってしまう。さてここらへんから、僕はピアノの部屋で飛び上がったり、頭を振ったり、じっと白目になったりしてときを過ごしはじめる。今回のこの曲に対するアイデアのおでましを、色々なコードワーク、テンポの変化その他を試し弾きをしながらじっとまった。何日も何日も何の変化も訪れなかった。経験上ギブアップの瞬間が近づいている事を悟り始めた。あまりにも最初のアイデアの発見に時間がかかり過ぎると、アイデアがすっとはいってくる門が閉じてしまうのである。何故だか分からない。しかしこの曲にはなぜか特別な思い入れがあった。この曲が僕を呼んでいるという感覚も死んではいなかった。門が閉じようが何が起ころうが対峙することを止めなかった。最初のメロディーは打点である。これは僕が大学時代まなんでいたクラシックの打楽器の譜面そのものである。そう、打楽器の楽譜と思えば、、、、、フランシス・レイ→パリ→フランス→ピレネー山脈→バスク人→ボレロ→ラヴェル、これらの言葉が脳内をかけめぐった速度は、それまでの沈滞と相反して非常に早かった。脳内に高速の光が見えた。ボレロだ!!こうして、「男と女」は、ボレロのリズムで、ソロパートはスパニッシュ風のアレンジで演奏することとなった。まあ、することになったと断言する根拠は何かと言われれば何もない。このように、アレンジをするにあたり、基本的アイデアのみつけかたを文章にしてみると、御覧の通り、すべてがとても馬鹿げていることが良く分かる。最初の動機には何の脈絡もなく、意味もない。まあこう言ってしまえば、演奏することにさえ意味はないのかも知れないけれど。いずれにせよアレンジしている当人、僕の事だが、別に人類を幸福にするある種の発明をしたのではないにもかかわらず、興奮し、喜びの為飛び上がり、天下をとったような心持ちでいるのである。今回のCDにはいっている「男と女」をアレンジするにあたり、こういったいきさつと言うか、行程があった。本当に馬鹿げているのか、意味がないか、それとも何かしら意味があるのか、演奏なりCDを聞いた人に感想を聞いてみたいなと思っている。
某月某日
来る2月21日に新しいトリオのCDが発売される。タイトルは「SONGS」。メンバーはドラムに外山明(DS)安カ川大樹(B)。前回より更にきれいな音楽をつくり大勢の人に聞いてもらいたいと思った。演奏において、盛り上がる事は非常に大切な要素であるが、それだけを目的にしたものや、難しいところだが、俺のやりたい事はこれで、分からないやつは分からないでいいというスタンスのものはつくりたくなかった。CDのライナー、曲の解説を含めて自分で筆をとった。本当は、あまり説明的文章を載せたくはなかった。ある面演奏を聞いてもらえれば、わかってもらえるはずと信じたいし、また聞き手のイメージを逆に限定したくなかったからである。しかし、そういう意味を含めて、CDを出すということ事体を補足する文章は書けると思った。そしていい意味で内容を補足しうる文章がかけたと思っている。ジャズクラブにおいて、クオリティーの高いピアノにめぐりあうことは稀だ。調律はまあまあ合っていても、アクションその他に悲しいかな充分でないものが多い。いわんや調律の狂ったピアノを、なんとかベストな状態で演奏しなければならないことが常である。スタジオで録音するということは、普段弾けないような良いクオリティーのピアノで存分に自分のイメージしているサウンドを現実化できるというメリットがある。普段僕の演奏をクラブに聞きに来てくれる人々さえ聞いたことのないような音がCDでは実現可能なのだ。嬉しくも悲しい現実ではある。今回の録音において、外山、安カ川両氏は、僕の音楽やアレンジに対し絶大なる協力を惜しまなかった。その二人の勢いを借りてか、音楽の内容は僕が最初にイメージしていた以上のものとなった。僕の職業は対外的にジャズピアニストとなっているが、実際今回のCDに於いて、いわゆるジャズのスインギーなリズムをもって演奏している曲はごくわずかである。三人のイメージと僕の曲やアレンジに対し、真に必要なアプローチが表出した結果そういうものがきてしまった。これでいいと思っている。そしてとにかくこういうものを世の中に出すことがとても嬉しい。特にジャズファンをふくめ普通の人がこのCDの音楽を楽しく聞いてくれたら本望だと思っている。
某月某日
深夜に,密やかに,BILL EVANS の「WALTZ FOR DEBBY」を聞いた。やっと ミュージシャンのDIARYらしきものがこの日記の欄に書ける夜となった。幾度 と なく聞いたこのCD,レコード盤の頃から聞いているこの音楽。かれのイメー ジは, 当にピアノという楽器が表現できるキャパシティーを優に超えてい て,実際, かれの頭の中にある音を表現できる楽器は元々存在しなかったのかも しれない そこまでの気分にさせるようなサウンド。出てくる音,ハーモニー,アイデアの 数々, ピアノという楽器がかれのイメージを全て受け止められないかのごとく,そ う,全て がギリギリのセンで,そして全ての行いが最高にリラックスしている空気。 盛り上がることをよしとするありがちなものではなく,人類を見限った美の ミューズ が,私も見るメが無かったと雲の上からちらっとマンハッタン島の片隅で行わ れる 一連の演奏に頬の片方だけを緩ますような演奏。戦争,いさかい,離婚劇, 失業, 憎しみ,嫉妬,美と対極にあるこの世の中のよく見る光景。それらがない交 ぜになっ てグシャグシャになった浮き世の辛さ。そんな世界に,僕が生まれる少し 前に, ほんの一瞬だけ,サア-っと,あっという間だけ,それら浮き世の常をほん の一瞬浄 化するような音楽が実際この世で奏でられていたことに,僕はとても嬉しさを感 じる。 妙な表現だけれど,嬉しさを感じる。そして僕も,かれのやろうとしていた事 の末端 の末端に少なくとも位置している事を,本当に嬉しさを感じる。
某月某日
銀座のナイトクラブでピアノを弾き初めて1年ちょっとたったころの話だ。ちょうど仕事にもなれ始め,毎日のルーティーンにそこはかとないけだるさを感じ始めた頃でもあった。いつもの時間に店に行く。ホステスさん達,バーテンダー,ウエイター,みな所定の位置で客入り前の雑談に講じている。ぼくもピアノの前に座ってタバコなどふかしていた。突然店の中がざわめいたと思って反射的に入り口の方を振り返ると,そこにママが立っていた。ものすごくはでな着物を着ている。鶴が三羽,飛翔している図柄の,ものすごく高そうな和服だ。店のママは,陶然としたなかに突き刺すようなプライドの視線を満遍なく店の中に送り込んでからゆっくりと,「オハヨ」と言った。なぜか誰も返事をしない。やっと店のマネージャーが反応する。「ママ,キレイだねえその着物,最高だわ。いくらしたのよ。」マネージャーは,客に対するような笑顔でママに言う。絶妙の間合いをあけてママが答える。「400万。」ぽつりと言う。この値段を聞いてぼくが一番のけぞった。それだけあれば,今すぐにでもアメリカに留学できるのに。400万が鶴に化けたか。マネージャーがまた何か言おうとした瞬間,えも言われぬ空気が急に店の中に流れ始めた。チイママが店に入ってきたのだ。二人の視線がバッチリとあう。あの目つき,ぼくは一生忘れない。恐かった。「あら,着物新調したんですか。」「そう,400万,どうこれ,いいでしょ。」文字にすると普通の会話だが,二人の言葉の端はしには,筆舌につくしがたい,逆の意味のニュアンス,嫉妬とねたみが一緒になって煮凝りになってしまったような,何か瘤のようなものが,空気中に散乱していた。その日の前半,ママは客の絶賛をあびながら上機嫌だった。ぼくの弾いているピアノの横のテーブルに座り,客との話も着物のせいで弾むのか,笑い声がどっと上がる。まあいつもどうり,ピアノの演奏を聞いてる奴なんかいない。そこでとんでもないことが起こった。新入りのウエイターが水割りを載せたコースターを持ってやってきた。演奏しながら何となく目の端でその場を見ていたら,そのウエイター,水割りグラスの一つをママの着物の上にこぼしてしまった。外野の俺でさえ,演奏が止まりそうになった。ママのいるテーブルが突然静かになり,ウエーターは小さい声で謝りまくる。何度も何度も頭を下げ,表情は消え入らんばかり。「いいのよいいのよ,この着物やすもんなんだから,気にしないで。なんてことないの。」ママは見事な作り笑いを顔に浮かべて,その笑顔をテーブルの客の方にも向ける。その場は収まり,何ごともなかった様に再び談笑がはじまった。その当時ぼくは掛け持ちと言って,30分ずつ,2件の店を行ったり来たりしていた。つまりたとえば,8時から8時半までクラブAで演奏し,8時半から9時までクラブBで演奏する。これを午前1時まで毎日やっていた。一晩で倍稼いでいたのだ。二つの店はユニフォームが違い,ぼくは短い時間の中,交代する時に,各々の店の非常階段あたりで,上着とネクタイを着替えていた。その日も8時29分まで演奏し,チェンジのピアノの人が来るや否や非常階段に駆け込んだ。そこにはママとさっきのウエイターがいた。目の端に二人を捉えつつ,ぼくは上着を脱ぎ始めた。突然,「パシーン!パシー!」という音が非常階段に鳴り響いた。何ごとかと思って振り返ると,ママがウエイターの前に仁王立ちとなり,ウエイターにビンタを食らわせていた。「あんたねえ,この着物イッタイいくらすると思ってンのよ,400万よ,400万!あんたが2~3年働いたって買えやしない代物なのよ。」「パシーン,パシー!!」ぼくはといえば,その場でどうふるまって良いか分からず,とにかく着替えようとするのだが,上着のボタンをかけ違え,ネクタイの結び目はうまくほどけず,次の場所の時間は迫るはで,ほとほと困った。ママはと言えば,あの銀座のママ独特の髪型,軍艦の舳先みたいな頭を振り乱して怒り狂っている。ほつれ毛が額やうなじに垂れ下がり,安物のSM雑誌の逆さ吊写真みたいだった。顔は,阿修羅のようである。ママがぼくの方まで睨みだした,ヤバいと思って,上着を手に非常階段の踊り場を飛び出た。一週間ほどたったある夜,今度はチイママが500万の着物を着てみせにやって来た。また誰か水割りをこぼさないか,心配でしょうがなかった。10年以上前の話。
某月某日
二枚目のトリオのレコーディングが終了した。録音したのが9月末であり,マスタリン グを終えたのが10月末であった。レコーディング,マスタリング共,お世話になった のは,東銀座にある音響ハウスというスタジオである。新しい音楽を生み出した喜びは 確かな手ごたえと共にあるにはある。しかしマスタリングの過程において,何度も自分 の演奏を聞かなければならず,それなりに疲弊する。 ある意味でとても楽しい時間ではあるのだが。マスタリングを終り,ふらりと東銀座の 路上に出ると,近くに知り合いが教えてくれたすし屋があることに気がついた。ぶらぶ らと記憶をたどりながら,そのすし屋の暖簾をくぐる。銀座のまんなかの喧噪を離れた あたりにあるそのすし屋は,家族単位でやっている場所独特の雰囲気があり,カウンタ ーの奥に据付けられたテレビからは,夕方のニュースが流れていた。 ちらし寿司と熱燗をたのんでカウンターに座った。ひとくち酒を飲んだら,もうそれで 頭がぼーっとしてきてしまった。こういう状態になりたくてこういう場所に来たのだっ たが,あまりにも酒による反応がはやい。まだCDそのものは出来上がっていないけれ ど,一段落ついたという安堵が酒のまわりを早くしたのかもしれない。すし屋の大将と あたりさわりのない話をしながら,ちらしをつまみつつちびちび飲んだ。何だかとって も嬉しかった。
某月某日
デンマーク人のコルネット奏者,キャスパートランバーグを招いてのツアーが今日終っ た。無事すべてを終えて,成田行きのリムジンにかれを押し込み,家に帰ってきた。 おはずかしい話だが,経費削減の為,彼は僕のアパートに寄宿していた。一番の盟友の 去ったあとの部屋は,散らかり放題であり,目もあてられない状況であった。 猛烈な量の洗濯物と,部屋の掃除を同時にこなしていたら,スーッと虚脱感におそわれ た。体の奥底からくる,根元的な虚脱感。体の疲れもその虚脱感を助長してはいる が,もっと体の奥底からくるなんとも言えない孤独感と虚しさ。ツアーも無事おわ り,評判もよく,何一つとして思い悩むことはないのだけれど,何かしら地面の底に 吸い込まれるような気分の重みが,掃除洗濯をすこしづつすこしづつ妨げる。アメ リカから帰国してこの方,年に一度海外からミュージシャンを呼んでツアーをすること が恒例となっている。 そして毎年,このツアーが終る直後に,同質の虚脱感におそわれる。満足感や何かしら をやり遂げたという充実感も,実はこの虚しい気持ちにもふくまれてはいるのだが。 定住という言葉があるけれども,それも時間の問題で,永遠に同じところに住み着くこ とはできない。地面の上に立っているという時点で,べつに演奏旅行というスタンスで なくても,僕はツアー中なのかもしれない。不快な話かもしれないけれども,死時に そのツアーも終る。別に交通機関を使って住み慣れた土地や街をはなれ,どこかに演奏 に行くということだけがツアーではないような気がしている。遠くの国から来た友人を 送りだして,ふとこのようなことを考えてしまった。冒月某日やっと今日は雨がふった。このところの暑さは常規を逸しているように思う。 台風でも何でも良いから,あの強い太陽光線をしばしの間曇らせていて ほしい。 汗をかき疲れたような皮膚感覚も,ホッと一息ついているようだ。毛穴とい う毛穴が 何やら弛緩しているような今日の朝。その弛緩した毛穴ににじり寄るような, そして 長い間聞いていなかったような錯覚を起こさせる雨の音。直射日光にあぶら れ続けた 頭皮と頭蓋骨も,やわやわとした湿気はあるにせよ,芯の部分から熱が引い て行くよ うである。僕の仕事はいつも人々が仕事を終えてから始まるのが常だ。というこ とで, 日中カンカンデリの中を汗水たらして何かするという事はめったに ない。 しかしそれでも,こうやって久しぶりに雨の日を迎えてみると,体の芯から 今迄の 熱気が少しづつ冷えて行くような感覚をおぼえる。夏の暑さは,今迄の僕の 体験と 記憶によると,時間的な解放感を意味していた。空が高く,着るものも軽く, 木々に 反射するストレートな太陽光線は,その生命力をダイレクトに浮きぼりして, 目に眩 しい。これらが僕の,今迄の夏という時期に関する印象なのだが,今年の夏は どうも暑すぎて,その特有の解放感もあまり感じない。太陽光線さえ,ギラギラ感を通り越し, 照りかえる木々の葉を見ると,生命力もヘッタクレもなく,何かジリジリと焦がさ れて いるようにも見える。気のせいだろうか。
某月某日
逡巡,そして忘我。この言葉の 意味する中間には,脳細胞と意識の入る隙間, 中間部分が普通あるものだが,演奏後,つまりピアノを弾いた後の 夜の時間 には,その中間部分が欠けるのが常だ。疲労と覚醒のカクテル。神 経と筋肉 の弛緩と緊張。この二つの要素が更に脳細胞と意識の隙間に入り込 む。意識 できる領域とできない領域,普通人はこのボーダーラインのありか た,また コントロールのしかたを心得ていると錯覚している。まあ,何が錯 覚かとい う事をさておき。しかし意識できる領域とそうでない部分のコント ロールな ど,本当は何人も可能な事ではないのだ。ただその事が不可能であ るという ことが日常生活ではわからないだけだ。人を逆の意味で狂わないよ うにして いる事柄,社会通念,常識,経済観念,お金のこと,各々の人生の 意味とそ の価値。それらのことが実はいかにもろい事か。オナニーする空 海,ハンバ ーガーを食べるマルクス,杖をつくカール・ルイス,自閉症の古館 一郎,観 念の世界では,色々な事が起こりうる。現実として認識している事 とこれら 観念の中の変な想像物,実はこれみなイコールなのである。イデオ ロギーに 酩酊する事,隣近所と仲良くしなければと思うしおらしい気持ち, 両親に対 して親孝行をしなければと思う,何かしらの罪悪感を伴った思い, 電車の中 ではからずも肩をぶつけてきた汚い身なりのオヤジに対するそこは かとない 殺意。これらのこまごまとした事象も全部ひっくるめて,意識と か,精神と いうものはことのほかもろい。ツアーにでて演奏の後行き着く先 は,なんの 味もそっけもないビジネスホテルが常である。得てしてあのような 空間が人 間の何か一番大切な部分,言葉や文章では言い表せない何か特別な 部分をい ちばんダメにする場所だ。なぜだか良くわからない。しかしもっと 飛躍して ,別の言葉でいえば,人生の,我々が生きている空間事体が,実は ビジネス ホテルのようなものなのかも知れない。味もそっけもない。しかし 冷暖房は 整い,プライヴァシーは少なくとも保たれる。冷蔵庫をあければ飲 み物は手 に入る。しかし何かが足りないのである。今いちばん大切な事は, さいはて の土地から来た吟遊詩人のいう事を聞く事である。この地球上にさ いはての 地がまだのこっていればの話だが。
某月某日
生まれ育ちは東京だった。いまも東京に住んでいる。宇宙から地球 を眺める と,東京一帯の関東平野が,いちばんキラキラと輝いて見える。 NHKで少し 前偶然そのての番組を見た。宇宙から地球を見ていちばん明るい所 に住んで いる。生まれ育っている。我々は生まれる時,自分の国籍,人種を 選ぶ事が できない。気がついたら日本人であった。しかも地球でいちばん明 るい所に いる。父親は京都の繁華街の出身で,母親は新橋で育った。子供の 頃から夏 休みの時期を迎えると,新橋か京都に行く事となった。高校2年の 夏休みに ,同級生で福岡から来ている級友がおり,かれの実家に遊びにいっ た。滞在 中に彼の家の法事が重なり,級友の家族と共に久留米の郊外のお寺 について いった。法事の後そのお寺に泊まる事となった。裏庭に面した広い 日本間の 障子をあけると,目の前が一面水田であり,遠くにローカル線が寂 し気な汽 笛をならしつつ走っていた。夜になった。一面の水田や,真の意味 での真っ 暗な空間を見たのはその時が初めてだった。とても恐かった。思い 出したようにローカル線が水田のはるか向こうを走り抜ける時があ る。ディ ーゼル車の灯が淡く水田を照らす。逆にその灯がまわりの暗闇を引 き立 たせるようで,更に寂しい気分になった。級友が,夜中に僕を散歩 に誘 った。複雑な心境で辞退したが聞き入れられず,彼と一緒に寺の外 に踏 み出した。目の前に真の暗闇が広がっていた。足が一歩も前に出な かっ た。自分が踏むべき地面が見えなかったからだ。僕の聴覚,皮膚感 覚の 次元まで,鈴虫の声が僕の体をふるわせていた。その聞いた事もな いよ うな虫の声にも平衡感覚を奪われたのだと思う。その時初めて真の 暗闇 というものを体験した。いまでも真の暗闇は苦手である。高校2年 で体験 した本当の暗さというものに,僕は衝撃を受けた。しかしあれから とい うもの,僕はいつも街にいる。キャンプにも行かず,スキーのよう な趣味 もない。 ツアーで地方に行く時も,だいたいがその地方の繁華街の宿で一泊 する。 暗闇とは長い間縁がない。何で今日はこんな事を突然書いたのだろ う。 冒月某日疲労感がある。精神的にでなく肉体的にである。これはあ る意味で喜ばしい 事で,夜になれば眠れるという事を意味する。頭だけが疲れている と,長い 車の運転の後に起こるフラッシュバックにも似て,寝床 の中で身悶えする事 となる。今日のこの疲労感は吉兆だ。鏡に写る自分の姿を見ると, 年相応の 自分の姿が,いかにも即物的に鏡の中にあるが,実はその自分の中 身の部分は 鏡にはうつらない。笑われるかも知れないが,幼稚園にかよってい た頃,ほの かに好きだった先生のことや,それらの記憶など鏡に写る筈もな い。 写るのは疲労した顔だけである。 ただ疲れて,ぼんやりした眼がこちらを見据えているだけだ。人間 の中身 に関して,古今東西の詩人や作家, あらゆる表現手段を持つ芸術家がその根底を,我々はなぜ生きるの かと いう問いと共に掘り下げてきた。答えはまだ見つかっていないよう である。 疲労した鏡の中の自分の顔と,その顔の内部にある少年の気分,こ れらも もしかしたら,その問いの一部かも知れない。冒月某日寝る前に, 貨幣というものについて考え出したら目が冴えてしまった。 お馴染みの一万円札をよく見たら日本銀行券と書いてある。私自 身, 経済とか,世間一般のことに対して,ものすごく疎い。生まれてこ の方 株券証券のたぐいは見たことも手にとったことも無い。株券などに 比べ 紙幣というものとの付き合いは長い。私自身の知識として,紙幣と いう ものは,もともと兌換紙幣といって金と交換できるものであったと いう ことだ。しかし今は信用のみで成り立っているそうである。いった いこ の日本という国の中には何枚の一万円札が存在するのであろう。 人のはなしによると造幣局が札を剃り,それを日本銀行が各大手銀 行に 配るそうである。ほんとか嘘かわからないが。働かずしてお金が支 給さ れるシステムがあるとはしらなかった。その配る枚数を誰がどのよ うに して,どういう基準で決めるのであろうか。そして今話題にしてい る紙 幣というものと我々がある意味で交換している,昼飯代とか,雑貨 とかと いうものの価値がある程度の振幅でもって落ち着いているのはなぜ なのか。 つまり色々なものの値段とその価値のバランスを保っている根元的 な基準 は一体どこにあるのか。それを誰が決めるのか。誰かが決めたとし て,た とえばそれが政治家でもいいのだが,その決めた基準の不偏的要素 は,い ったい誰が保証するのか。この世を創造した何がしかの存在,形而 上的な 何か,神様がその基準を決めたというなら納得するしか無い。あな たは今 ここに生きている。その存在事体私に因っている。その私が貨幣と 云う物 も同時にクリエートした。だから無条件で我が創造物にしたがわな ければ ならない,というのなら,事実そうなら,貨幣というものを理解す るのは 非常に楽なような気がする。しかし実際神様とか,何か絶対普遍的 な存在 が貨幣をつくりだしたのでは無さそうだから,自分自身,貨幣とつ きあい 理解する上で,現世的な何らかの基準が必要となってくる。その基 準は一体 どこにどう置けばいいのだろう。誰もが貧乏したく無いように,私 自身貧乏 したくは無い。良い仕事をして沢山お金がもらえれば非常に嬉し い。しかし そういう次元からもっとマクロに貨幣というものを考える場合の発 想のより どころ,それは一体どこにあるのだろう。冒月某日三日間だけのツ アーに行ってきた。長野,富山,そして三っ日めが帰りの日。 昔は旅というと歩くしかなかったという。司馬遼太郎の本を読む と,幕末の 志士はみなよく歩く。京都から江戸へ,毎日駈けた人もあるとい う。歩くと いうことは,徐々にまわりの環境の変化に体をならす事ができたで あろう。 つまり江戸から一歩一歩はなれるごと,ゆっくり景色など見なが ら,自分が 住んでいる所から徐々に離れていくということを本当に体感できた のであろ うはずである。しかし,現代はミュージシャンのツアーの移動時に 限らず, 車や列車などによって素早く移動するのである。飛行機などは, いってみれ ば,超低速のタイムマシーンの感がある。ドアをあければそこは別 世界だか ら。くるまでの移動でさえ,超々低速のタイムマシーンの感が少し 残る。 今回の移動は,水谷のワゴン車である。我々HIROSHI MINAMI QUARTET の面々,竹野,水谷,芳垣,新宿ピットインで演奏している我々の 雰囲気とか ヴァイブレーションのようなものを,そのワゴン車は,ある種の密 閉状態 で移動させる箱でもある。歩いて旅をしていた時代にはない人間の 真空パック を,なるたけ新鮮度を保って,パッとその地方地方に表出させる。 それと同時 に,というか日を追うごとに,ツアーに出るといつも感じるそこは かとない悲 しみのような感覚,倦怠とか,見知らぬ人に出会ったり,そういう 人に対して 演奏する喜びなど,様々な思いが,その密閉状態の車内に,日を追 うごとに蓄 積して行く。 辛いのに嬉しい。キツイのに気持ちいい。こういった相反する強烈 な感覚の粒 子のようなものも,車内にふわりふわり浮かんでは消える。よく知ってい たつもり だったサイドマン達の新しい側面を見ておかしかったり意外だった りする。 ワゴン車の外の風景は徐々に変わってゆく。外には密閉状態にはない, 少なくと も今はそうでない人達の生活とかその人達の住む家とかがゆっくり と窓の外を流れさる。またまたこれがもの悲しく見える。なぜだろ うか。演奏するごとに,我 々は新しい環境,つまり音響の異なった場所に自分の耳と体を合わせるこ とが要 求される。ピアニストである自分は,新しく出会う新しい楽器と仲良くしな ければ ならない。同じ場所で同じメンバーが演奏しても二度と同じ時演奏はないのだ から, 特に初めての場所での演奏というものは,ある種の,多分ギャンブル以上 のスリル と危険が存在する。ルーレットに花札をぶちまけるような,滅茶苦茶なギャン ブル。 しかもそこでは,聞いている人々に対して,一度は大穴のような,ストレートフ ラッ シュのような,大三元のような,確立の低いあがりのようなものをお目にかけ なけれ ばならない。そのまわりが,ワゴン車で運んできた新宿の空気とか雰囲気で包 まれて いれば申し分ない。ツアーに限らず,ピアノのイスに座るまでのプロセスが, どうし ようも無く長い。そう,何と長い時間がかかることか。そして演奏は,ものすご く短 い一瞬一瞬の積み重ねで成り立っている。普段の意識の時間感覚では無い一瞬の 膨大 な羅列。気がつけば車中にあり,密閉状態の箱の中でもといた所の空気と共に, その 空気とは全く違う場所を移動している。20?0年,月面のクラブ,「BLUE MOON」 で,80才の自分が,MOON RIVERを弾いている時が来るだろうか。冒月某日月夜 の夜に,ひとり歩く。見なれた通りや風景が,全く違って見える夜がある。 散歩というものは,全くお金のかからない,いたってシンプルな, そしてある 意味で有意義な時間潰しである。しかし自分が夜な夜な歩いている 姿を客観的 に考えてみると,これは実は散歩で無く徘徊という言葉に近いかも 知れない。 東京の街は迷路のようでもある。ニューヨーク,ボストン,パリ, ウイーン, 僕の好きなこれらの街のつくり,共通点はひとつ,夜歩きに適して いることで ある。今僕が住んでいる街東京は,夜歩きに適しているとも適して いないとも 言える。アメリカやヨーロッパの街とは全然違うのである。アジア には,北京 に1週間程演奏で滞在したことを除いて行ったことが無いから決し て断言でき ないが,東京のような迷路感覚は存在しないような気がする。この 場所にに生 まれ育っていてさえ迷路のように感じるということは,何か目に見 えない秘密 のようなものがこの街には隠されているような気がする。東洋でも アメリカで もヨーロッパでも無い東京のにおい。その臭いがかもし出す路地裏 の寂し気な 電柱。いきなり表出するお洒落なブティックの真横にある汚いラー メン屋。 交通標識と,下びた色合いの立て看板と,電柱にぶら下がる幾重に も絡まった 電線と,それら諸々が重なりあってどうにもこうにもグチャグチャな景 観の奥に ある東京らしさ。どう差し引いて考えても,ヨーロッパやアメリカの大 都市と比 べると,見劣りしてしてしまう所のほうが残念ながら多い。外国には負けな い美 感というものが確固としてあるはずなのに,古いものを大切にしないで どんどん わけのわからない建物をつくってしまう節操の無さそのものが東京を表面 上は見 劣りするものに作り替えてしまっている。しかし夜に,いってみれば徘徊し てい る最中に,これら諸々のゴタゴタグシャグシャのその奥に,東京という 街にしか 持ち得ない美感と透明感を感じる瞬間がある。その瞬間が訪れる条件にはま ずその 季節とその時期に見合った空気感があって,その空気の重さとか軽さの度合 いが, この街の透明感を存続させているおもな条件であると思う。生まれ育った東 京の街。 小さい頃お婆ちゃんの家から見ていた東京タワー。ちょうどタワーに日が点 る頃, 新橋のお婆ちゃんの家の前の路上で見上げていた東京タワー。今考えると あの瞬間 に,東京のスピリッツのようなものが僕の体の中に入ってしまったのかも知 れない。 そのスピリッツのようなもの,感じ方を土台に夜の東京を徘徊している と,景観が ムチャクチャでも,外国の都市と見劣りしても,やっぱりこの場所が好 きだなと 思えてしまうのである。トウキョウ・バンザイ !!!!!!某月 某日元来機械オンチである。ものすごくオンチである。と言いつつ こういう場所に 日記を書いているのもおかしいが,ここへこうやって文章を綴って いるという ことは,僕にとっては大進歩で,少し前の自分では考えられなかっ た姿だ。 何ごとにも得手不得手はあるが,それを決定付けるのは,機械に限らづその 事柄 に向かう時,もうすでに体の方がその事柄を受け入れる用意があるかな いかが重 要であろう。たとえその事柄に大して初めてであっても,いままで身近に あった とか,頭の回路がその事柄に近いとか。家にある家電の類い,音楽活動 をする上 でどうしても必要なステレオや録音器材,それと照明機具,これらの物 から生え ているコードの類いが,いつもホコリだらけになる。しかも,アダプター と言う 種類のもの,あれはなぜ全部大きさや電圧が違っているのか。アダプター 類をま とめてビニール袋に入れて保管しておくと,なぜかいつもこんがって そのままの状態で捨ててしまったりする。家電を含めた全ての説明書の類いが読め ない。字面は読める。しかしなぜだかいつも意味とその内容が頭に入らな い。いく ら読み返してもダメである。先日掃除機に内蔵するゴミ袋の取り付け方が分か らず, 非常に困った。ゴミ袋の取り付け方は図解までされているのに,袋の上下が 最後ま で理解できずに難儀した。引っ越しなどの際,コードを抜いたステレオセッ トを配 線しなおすのも僕にとっては大変な作業で,いつもスピーカーから音が出る まで, あらゆる穴にピンを突っ込んでは抜きをくり返す。羅列したらきりが ない。体の 中に,機械というものの受入先が見つからない。よくお年寄りの人で,ラ ジカセの 操作が分からない人など見かけるが,あれはきっと僕の未来の姿な のだろう。 近未来の僕の晩年には,機械類はもっと複雑化しているに決まっていて, 機械操作 が不得手だということだけで,ラジカセがいじれない以上の不便と不平等 な扱いを 招き,準市民のような位置に転がり落ちて,そうなれば,停電の時一人酒 を飲んで 気炎をあげるしかないか。
某月某日
東雲という言葉,語感と共に好きな日 本語のひとつである。自分が内証的になる時間。 意識と無意識のはざま,脳味噌が認知する行いの数々,理解,学習,視覚に よって見 える物を判断すること,その見えたものの名称を言語によって言い表すこと,挙 げて 行けばきりがない。しかしその行いの根幹は霧の向こうに包まれている。頭が ぼーっ としている状態とはまた違う,自分の脳の底の部分を探せないもどかしさ。晴 れ渡っ た空のした,美しい草原に身をおいても,100%の忘我と幸福にそう簡単に人間 は, というか少なくとも僕は身を措くことができないような気がしている。脳の 底が 見えないから。脳の根底部がわからない,計り知れない,意識できないとい う状態を フルに活用できるのは,演奏している時だけである。後はどうしても,全て人 間の行 いを悲観的にみてしまう。脳の底の部分なんか感じない人と,底の部分が見え ている と勘違いしている人と,僕のように底の部分が良く分からない人しかこの世 にいない はずだから。どれもろくなもんじゃないような気がする。小学校の1年の最 初の 授業から,僕の頭は,この底の部分を探すという意味のない戦いをくり返し てきた。 僕はなぜこの教室にいなければ成らないのか,この教科書は一体誰が書いた のか, その問いはいつも,脳の底の方に消えて行き,底の方からは答えが帰ってこなかっ た。 科目によっては僕の興味をひく題材が授業で扱われることもあった。非常に 興味を ひくこと,それは考えることが面白いこと,その題材から感じるものが心地よい とい うのが条件だ。それで僕の頭は授業から遠ざかってしまい,気がついたら昼休 みだっ たりした。面白い,心地よいというものを受け入れる神経のような感覚,それ が脳の 奥の方にあるような気がするが,その実体をはっきりと掴んだことはまだ 無い。 明け方という時間,いつもではないが,一瞬だけその脳の底の部分がはっき りと感じ られたような一瞬があったりする。その感覚は一瞬にして過ぎ去ってしまうの だが。 僕は徹底的に学校という成り立ちそのものに向いていなかった。反抗するという 行い, 不良になったりすること,先生を困らせるというエネルギー,これらもあ る意味で 学校という成り立ちに参加している,参加できているという証であると思 う。僕は 不良にさえ,反抗児にさえ成れなかった。参加できなかったから。もっとヤバい のは, 参加できないということをあまり悩まなかったことだ。とにかく何もかも 無意味に 見えて仕方なかった。その感覚は中学生になると強烈さをまして行った。い わゆる 受験戦争という言葉がまだ生きていた頃である。何れはみな死んでしまう。成 績の 良いものも悪いものも。朝の空気を吸いながら思う数々のこと。思えばよくぞこ こまで 生き残ってきたものだ。